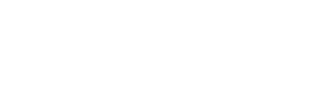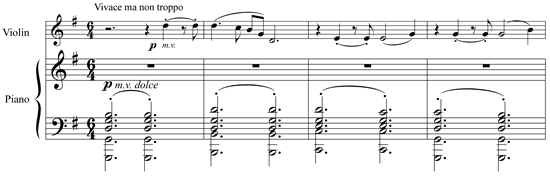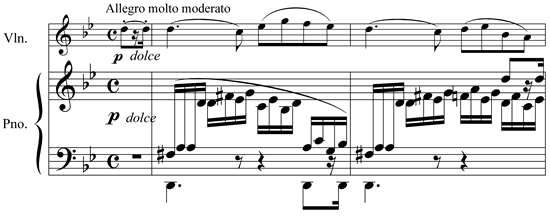Photo by K. Miura.
アクロン:ヘブライのメロディー Op.33
ジョセフ・アクロン
(1886年ポーランド領(現:リトアニア)/ロズデイ生まれ;1943年アメリカ/ハリウッドにて死去)
ヘブライのメロディー Op. 33 (1911年作曲)
ニグンとは、何世紀にも渡り、ユダヤ人の間で受け継がれてきた即興的な音楽で、シナゴーグ(ユダヤ教の礼拝の為の教会堂)でのお祈りやユダヤの伝統を学ぶ機会などに耳にする歌詞のないメロディーです。特に、精神的に自己対峙しているようなタイプのニグンは、19世紀や20世紀の初期に、東ヨーロッパのユダヤ教ハシド派(ユダヤ教の中でも最も伝統を重んじる、戒律の厳しいグループ)の人々の心を捕らえました。アクロンは、祖父が自宅やシナゴーグで口ずさんでいたニグンを元にして、『ヘブライのメロディー』を作曲したものと思われます。
アクロンの父親は子供達の音楽教育に熱心で、ジョセフにはヴァイオリンを、兄のイシドアにはピアノを幼い頃から教えました。ジョセフは特に神童として知られるようになり、7歳のときにワルシャワでデビューしてからは、帝政ロシアの全ての都市でコンサート活動を行いました。1899年に13歳でサンクトペテルブルク音楽院に入学し、伝説的なヴァイオリンの指導者であったレオポルド・アウアーのもとで、ヤッシャ・ハイフェッツやナタン・ミルシュタイン等とともに学びました。
アクロンはサンクトペテルブルクに滞在中、ユダヤ文化を紹介して、振興させることを目的としたユダヤ民族音楽協会の活動に加わりました。彼の作品の多くにユダヤの民族的要素が取り入れられていることからも、この活動が彼に与えた影響の大きさが伺われます。
『ヘブライのメロディー』は、1911年にサンクトペテルブルクで行われたツァー(帝政ロシア皇帝)を称える特別コンサートの終了後に、アンコールとしてアクロン自身によって初演されました。ハイフェッツを含む多くのヴァイオリニスト達がこの曲を直ちにレパートリーの中に取り入れ、たちまち世界中で人気を博しました。
この曲は、心に残る印象的なメロディーが特徴ですが、ただ単に美しい曲というだけではなく、ヴァイオリンがユダヤ文化には欠かせない楽器で、しかも人間の声に一番近い音色をもつことから、この曲の元になったニグンの本来の特徴にも通ずる作品であると言えます。
1922 年にアクロンは、ベルリンにユダヤの音楽を出版する会社を設立しました。1924年にはパレスチナを訪れ、短期間滞在しました。世界情勢が政治的に不安になり、1925年、安住の地を求めてアメリカに亡命しましたが、心の安らぎを得ることはできませんでした。最初はニューヨークのウェストチェスター音楽院で教鞭をとる傍ら、ヴァイオリニストとして再起しようと試みましたが、結局は1934年にハリウッドに移り住み、映画音楽の作曲家として生計をたてるにとどまりました。1943年にアクロンが亡くなったとき、友人の作曲家、アーノルド・シェーンベルグは、追悼記事の中で、「最も過少評価された現代音楽の作曲家」と彼の死を悼みました。
2003年11月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
アダムズ 作曲家基本情報
作曲家基本情報:アダムス
作曲家:
ジョン・クーリッジ・アダムズ John Coolidge Adams

©Christine Alicino
有名な引用:
「一つ一つの小さな動きのあるまとまったモチーフをあたかも対位法を用いて自由に
積み上げるより、私はむしろ大きい構想の下にあたかも細胞が継続的に分裂を繰り返し、
形をなしていくような方法をとった。それは羽目をはずさない単純な様相の中に、
実際はより多様で明と暗そして静けさと激情を形作ったと思う。」
生年月日:
1947年2月15日
出生地/居住地:
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター生まれ/カリフォルニア州サンフランシスコ在住
スタイル:
ポスト・ミニマル
最初に習った楽器:
クラリネット
恩師/影響:
クラリネットを父親に、後にボストン交響楽団クラリネット奏者Felix Viscugliaに師事。ハーバード大学にて作曲をレオン・キルヒナー、ロジャー・セッションズ、アール・キム、デイヴィド・デル・トレディチに師事。スティーヴ・ライヒ、ラ・モンテ・ヤング、フィリップ・グラス、テリー・ライリー、ジョン・ケージやモートン・フェルドマンの影響を受ける。
代表作:
シェイカー・ループス Shaker Loops(1978年作曲)
オペラ『中国のニクソン』Nixon in China(1986年作曲)
ショート・ライド・イン・ア・ファスト・マシーンShort Ride in a Fast Machine (1986年作曲)
オーケストラのためのファンファーレfanfare for orchestra(1986年作曲)
オペラ「クリングホファーの死」The Death of Klinghoffer(1991年作曲)
On the Transmigration of Souls (2002年作曲)
オペア『ドクター・アトミック』Doctor Atomic(2005年作曲)
編集:Andrew Freund
リサーチ・アシスタント:Clara Kim
監修:林田直樹
(2014年9月)
アダムズ:ロード・ムーヴィーズ
ジョン・アダムズ
(1947年アメリカ/マサチューセッツ州ウースター生まれ;アメリカ/カリフォルニア州サンフランシスコ在住)
ロード・ムーヴィーズ (Road Movies ) (1995年作曲)
Ⅰ. Relaxed Groove
Ⅱ. Meditative
Ⅲ. 40% Swing
アメリカ人作曲家のジョン・アダムズは、作曲界においてその世代の先導的な雄として長く認められてきました。彼の傑作には、政治的・社会的論争を誘発する、歴史的・文化的題材を取り扱った扇動的作品が多いですが、幅広い音楽愛好家に人気があり、新しい熱狂的なファンを魅了しながら、現代音楽の最先端で活躍し続けているのは、彼の音楽が卓越しているからに他ありません。
ロード・ムーヴィーズは、アメリカ議会図書館の委嘱作品で、1995年にヴァイオリニストのロビン・ローレンツとピアニストのヴィッキー・レイによって、ケネディ・センターで初演されました。交響曲やオペラなどスケールの大きい作品が多いアダムズとしては、珍しい作品です。アダムズは、和声の進行を強調し、執拗な反復を繰り返す“ミニマリスト”スタイルを経て、1990年代初頭には、室内楽によりふさわしいアプローチであると感じた、メロディックな独自の作曲技法を構築しました。それでも、彼の室内楽曲を聴けば、叙情性の深い、忘れられない美しいパッセージの中にも、スピンしたり、揺れたり、低い声で口ずさんだり、スイングしたり、ウィットに富んだ手法が見られ、典型的なジョン・アダムズの音楽であると思い当たります。
アダムズ自身はロード・ムーヴィーズを「トラベル・ミュージック(旅の音楽)」と呼んでいます。実際、この作品は、昔の名画によく出てくるような、アメリカ大陸の長距離を走る自動車の旅を思い起こさせます。第1楽章と第3楽章は、開けた道をドライブしているようなビートを表現し、ロックやスイングのリズムを利用した絶え間ない動きが展開していきます。特定のリズムの執拗な反復を楽しんでいるかのような、ミニマリストであるアダムズ特有のテクニックが楽曲の随所に見られます。しかし、アダムズは、聞き手の予想を絶えず裏切ることで音楽の旅を活気付けるような真似はほとんど見せず、“トリック”をさしはさんでいるにすぎません。
第1楽章は、冒頭の曲想の上に、新しい断片が繰り返し重なっていく多層的な構造の中で展開していき、全体的にだんだんと濃密な色彩を帯びていきます。規則正しいテンポの中でのオフリズムはテンポを乱すというよりも、ユーモラスな効果をもたらしています。この楽曲における不規則性は複雑な拍の変化からではなく、非対称的な楽曲構成におけるオンビート・オフビートによって巧妙に作り出されたものです。
第2楽章の曲想はブルースの形式で、より黙想的になります。ヴァイオリンの最低音であるG線は全音低いF(ファ)の音にチューニングされます。この楽章では、調性の中心音がG(ソ)なので、F(ファ)の音はG(ソ)の音から数えると7度上の音になります(もしくは1度下の音になります)。7度上の音を強調するのはブルースの特徴で、“ブルース・セブン”として非常によく知られています。全音低く調弦されたG線は、よりゆるい響きを作り出し、この楽章を気だるく、活気など無い雰囲気にしています。リズミックな快活さとパーカッションのようなアーティキュレーションが多用されている前後2つの楽章と異なる静的な曲想が特徴的です。
最終楽章の標題「40% Swing」はMIDIにおけるコンピュータのセッティングに関係しています。ヴァイオリンとピアノは平行してスウィングし、時に合奏し、また時にはそれぞれが独立して演奏します。アダムズは第3楽章を“4WD専用”と述べており、聞き手はただしっかりつかまって、このワイルドな乗り物に身を委ねればよいのです。演奏者は大いに真剣ですが、最後まで含み笑いが出そうな楽章です。
2008年4月/2014年7月改訂 五嶋みどり
(訳:佐野浩介/改訂:花田由美子)
Notes © 2008 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ウィア:247本の弦のための音楽
ジュディス・ウィア
(1954年イギリス/ケンブリッジ生まれ・在住)
247本の弦のための音楽(1981年作曲)
ジュディス・ウィアの『247本の弦のための音楽』は、イギリスでデュオを組んでいるヴァイオリニストのポール・バリットとピアニストのウィリアム・ホワードの依頼で作曲されました。この曲が作曲された1981年当時、彼女はグラスゴー大学の教授をしており、既に彼女の作曲した『木管五重奏』は6年前に出版されていました。1987年に作曲された『中国オペラの夜(The Night at the Chinese Opera)』は高い評価を得て、イギリス国内、またドイツやアメリカでも何度も演奏され、広く放送もされました。
現在ウィアは、折衷主義の作品を多く発表している作曲家として、近年のイギリス出身の新進気鋭の作曲家の一人として確固たる評価を受けています。まだキャリアが浅い頃から、本人のルーツでもあるスコットランドはもちろんのこと、アイスランドやインド、中国などに伝承される民俗音楽に強い関心を抱いており、親しみやすいものとそうでないものをブレンドするという彼女独特の作風にその影響が現れ、音楽コミュニティーを広げることを使命だと考えています。
ウィアは最初にオーボエを習い、次に作曲を学びました。ジョン・タヴァーナー、ロビン・ハロウェイ、ギュンター・シューラーらに師事し、様々な音楽を勉強しました。しかしながら、彼女の音楽は恩師達の音楽とは似通ったところがなく、かといって恩師全員の音楽を凝縮したようなものでもありません。風刺とユーモアにあふれたウィアの作品は、極めて個性的で、どの流派の影もありません。彼女に最も強く影響を与えているのは、劇場音楽やナレーション付きの付随音楽です。
一般に2つの楽器のためのソナタは、言葉の上では、両方のパートが重要性において平等であると言われていますが、実際には必然的に一つの楽器が上位の立場に立っている場合がしばしば見られます。しかし、『247本の弦のための音楽』は、2つの楽器が殆ど全ての面において全く均等に重要性を帯びているのが特徴です。247という数字はピアノとヴァイオリンの弦の数を足した標準的な数です。
10分あまりのこの作品は10の短い曲から構成され、続けて演奏されます。生き生きとした輝きや、あざけるような突然の沈黙、無邪気、グロテスクな真似しあいといったユーモアが全体にちりばめられている曲です。予期しない展開が次々と起こり、聴衆の背中がむずむずしてきそうです。演奏が始まると、リズムが簡潔で、音楽的に“サイモン・セッズ”の独創的なゲーム(*)に似ていることがすぐにおわかりになるでしょう。2つの楽器の共生の関係が続き、補足的なパートナーシップがより明白になっていきます。聴衆は、どちらの楽器がリードしているのか推測するのをやめて、2つの楽器の共同作業を単純に楽しむようになります。
そのほかに興味深い要素では、4曲目に見られるような3本の音域のラインの範囲、つまりヴァイオリンのラインが3本のラインの真ん中にあるという特徴とダイナミックスの非常識的な使用法で、静かなこの作品にコミカルな独自性を生み出しています。また第7曲目では拍子記号がしばしば変化します。第8曲目には感情を高揚させるようなグリッサンドと四分音(半音のさらに半分の音程にある音)があります。最後の曲、第10番は、これぞ完結の感覚があります。最初の緩やかなリズムが消え、充実した低い音で終わります。
(*)子供達が遊ぶジェスチャーゲーム。鬼が「Simon Says……」と言って、例えば「右手を上げろ」「片足で立て」などと参加者に命令します。鬼が命令する言葉の前に「サイモン・セッズ」と言ったときだけ参加者は指示に従います。命令どおりに行動できなかったり、鬼が「サイモン・セッズ」と言わなかったときに、命令どおりの行動をしてしまうと負けとなるゲーム。
2004年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ヴィエニャフスキ:モスクワの思い出 Op.6
ヘンリク・ヴィエニャフスキ
(1835年ポーランド/ルブリン生まれ;1880年ロシア/モスクワにて死去)
『モスクワの思い出』Op.6(1852作曲)
ポーランド生まれの偉大なヴァイオリニスト兼作曲家として知られているヘンリク・ヴィエニャフスキは、8歳でパリ音楽院に入学し、弱冠10歳の若さでヴァイオリン部門において最高得点で卒業しましたが、後に再入学して作曲を学びました。ヴァイオリンの演奏技術は傑出しており、10代のうちからヨーロッパやロシアで幅広くコンサート活動を行っていました。彼の演奏は、パガニーニ(イタリアのヴァイオリンの巨匠)のような完璧な技術に加え、聴衆の心を揺さぶるような感情表現があったと言われています。
『モスクワの思い出』は、弟のピアニストのヨゼフ(1837-1912)を伴って、ロシアに演奏旅行に出かけたときに耳にしたロシア民謡をもとに作られた変奏曲です。モチーフとなった民謡は、『赤いサラファン(The Scarlet Sarafan)』と『馬に鞍をつけて(I Saddle My Horse)』の2曲で、ロシアの歌の教師であり作曲家のアレクサンドル・ワルラモフ(1801-1848)が書き残したものです。『赤いサラファン』は日本語にも訳されており、歌われる機会が多いので、メロディーに耳覚えのある方も多いと思います。サラファンとは、ロシアの農婦が着る特別な民族衣装のことです。この曲はもともとヴァイオリンとオーケストラのために書かれました。
この曲は、『赤いサラファン』のテーマが断片的に使われている長いイントロダクションで始まり、曲の中間部になってようやくそのメロディーが完全な形で姿を現すと、ノスタルジックな甘美な感覚が押し寄せてきます。続いて2つのヴァリエーションが展開し、『馬に鞍をつけて』のヴァリエーションが続きます。農民の踊りを彷彿させるような早いパッセージが続く中で、3つのヴァリエーションが展開し、この作品は最後まで途切れることなく勢いを増して、歓喜の中で終わりを迎えます。
2004年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ウェーベルン:ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 Op.7
アントン・ウェーベルン
(1883年オーストリア/ウィーン生まれ;1945年オーストリア/ミッテルジル(ザルツブルク近郊)にて死去)
ヴァイオリンとピアノのための4つの小品Op.7(1910-1911)
- Sehr langsam
- Rasch
- Sehr langsam
- Bewegt
アントン・ウェーベルンは61年の生涯で31の作品しか残さず、決して多くの作品を作曲した音楽家とは言えません。彼の作品をまとめてマラソンのように聴けば、4時間くらいで全ての作品を聴くことが出来るでしょう。
ウェーベルンは母親からのピアノの手ほどきで、音楽教育を受け始めました。幼少期や青年期には、芸術(特に音楽や詩歌)に取り囲まれていました。生涯に渡って、スケッチや彼自身の考え、他人の作品と同様に自分の作品からの抜粋でいっぱいの日記をつけていました。
1904 年はアーノルド・シェーンベルク(1874-1951)と出会い、彼に師事して定期的に作曲の勉強を始めた年であり、ウェーベルンにとっては重大な転機となりました。年上の作曲家シェーンベルクは、20世紀初期の最も影響力をもった作曲家の一人であり、21世紀となった今でも彼の与えた影響を感じることができます。シェーンベルクの指導のもと、ウェーベルンは作曲技巧や音楽構造を学びました。そしてまた彼はとりつかれたかのように一生涯シェーンベルクの忠実な信奉者となりました。
4つの小品は、プレグルホーフ(オーストリア南部のカリンシア)の別荘で書かれた作品で、短い曲でありながらも音色の種類も豊富で、作曲家の細かい指示がたくさん書かれています。ppp(極めて弱く)、kaum hörbar(ほとんど聞こえない)、col legno(弓の毛ではなく木の部分を使って音を奏でる奏法)、gerissen(すばやく弾ききる)、pizzicato(ピチカート:指で弦をはじく)、ausserst kurz(極端に短く)などといった用語や記号を用い、簡潔に表現されています。この作品は高度に圧縮された緊張感が強い曲です。
それぞれの曲は、9小節、24小節、14小節、15小節しかなく、どの曲も一分以内に終わります。全体としての作品の強靭さが一般的な反応として感じられますが、演奏によっては細部が際立ち、新鮮に感じられます。演奏家にとっては極度の集中力を要する作品で、作曲家の意図を正確に表現するには、個々に独自の表現を維持しながらも、ピアニストとヴァイオリニストは注意深く同時に想像力に富み、かつ自発的でなければなりません。
2003年1月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
エルガー:愛の挨拶 Op.12
エドワード・エルガー
(1857年英国/ロウアー・ブロードヒース生まれ;1934年英国/ウースターにて死去)
愛の挨拶 Op.12 (1888年作曲)
エドワード・エルガーは、イギリス近代音楽の一派を形成したイギリスを代表する作曲家ですが、一番よく知られているヴァイオリン曲のタイトルは『Salut d’amour』というフランス語のタイトル(英語では『Love’s Greeting』と訳されます)がついています。後に彼の妻となる女性との愛にインスパイアを受けて、ヴァイオリンとピアノのために作曲されたこの小品は、様々な形態で演奏され、エルガーの名前が世の中に幅広く知られるきっかけとなりました。
ベートーヴェンからブラームスにいたるドイツ音楽が主流であった19世紀においては、イギリス音楽は殆ど振り向かれることはありませんでした。その後、ビクトリア朝後期およびエドワード七世の時代に、エルガーが作曲した『創作主題による変奏曲エニグマ(謎)』(1898-99年作曲)、『チェロ協奏曲 ホ短調』(1919年作曲)、イギリス愛国的行進曲である『威風堂々』(1901年作曲)が国際的な評価を得て、イギリス音楽に注目が集まるようになったのです。
当時のイギリス階級社会で、准男爵サー・エドワード・ウィリアム・エルガーとなった彼の父親は、プロテスタントが支配的であったイギリスの小さな町のローマ・カトリック教徒であり、ピアノ調律師兼ヴァイオリニストで、音楽関係の店を営んでおり、エルガーはほとんど独学で音楽を習得しました。そんな彼はイギリス社会での自身の脆弱な存在感にセンシティブなところがありました。
エルガーが著名な陸軍士官の娘でかつての生徒であったキャロライン・アリス・ロバーツ(Caroline Alice Roberts)と結婚したのは30代のときです。結婚により勘当されたアリスは、エルガーを上流社会へと押し上げようとするも殆ど実を結ばず、苦しい生活が続きました。しかし、彼女はマネージャーとして彼のキャリアを支え、家庭内では、貴重な擁護者であり、批評家でもありました。
この作品は当初『Liebesgruss』というドイツ語のタイトルで出版されました(彼の妻はドイツ語に長けており、彼自身もドイツ音楽に傾倒していました)が、すぐ後に、フランス語のタイトルに変更され、結果的に国際的な関心が高まり、愛奏されるようになりました。この曲は彼が婚約したときにフィアンセのキャロラインに贈った曲で、彼らの愛の歴史を物語っていますが、その頃の多くのドイツ音楽がそうであったように、ロマンティックになり過ぎていません。『愛の挨拶』は、曲そのものが親しみやすく、可愛らしく、優美で、聴く者の心にダイレクトに響きます。2拍子の明るいホ長調で書かれていて、ヴァイオリンが終始メロディーを奏でます。 “a Carice”(妻の名のCaroline Aliceの組み合わせ)に捧げられたこの曲はロンドンで1889年にオーケストラ版が初演されました。
2016年10月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2014 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
クセナキス:作曲家基本情報
作曲家基本情報:クセナキス
作曲者名:
ヤニス・クセナキス Iannis Xenakis

©Ralph A. Fassey
有名な引用:
「芸術一般でもそうだが、音楽芸術といわれるものにはそこにあらゆる表現に共通する触媒となる基本的な事がある。保守的に受け継がれてきたものを注視し追求、目指すうちに、彼(作曲家)の高揚する意識とあいまって無意識に考えられないような巨大で完璧な(本物)が一瞬にして達成されるものである。」
-Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition
(形式化された音楽:作曲における思考と数学)(IBSN 1576470792)より
生没年月日:
1922年5月29日-2001年2月4日
出生地/没地:
ルーマニア、ブライラ(Brăila)生まれ/フランス、パリにて死去
スタイル:
数学、統計学、物理学を作曲に応用
最初に習った楽器など:
声楽(少年合唱)
恩師/影響:
ギリシャ伝統宗教音楽・対位法・和声:Aristotelis Koundouroff
作曲: オリヴィエ・メシアン
代表作:
『アナステナリア』より『メタスタシス』Metastaseis from Anastenaria (1953-1954年作曲)
音楽劇『オレステイア』Oresteïa(1965-1966年作曲)
プサッファ~打楽器のための Psappha(1975年作曲)
リンク(英語):
Visuals:
Xenakis visual overview: http://www.kapsul.org/public/iannis-xenakis
Xenakis as architect: http://www.iannis-xenakis.org/xen/archi/real.html
Xenakis drawings: http://www.dwell.com/event-spotlight/slideshow/iannis-xenakis-drawings
MOCA past exhibition slideshow: http://www.moca.org/museum/imagerotator.php?exid=429
Blogs and interviews:
Interview with The Drawing Center curators Carey Lovelace & Sharan Kanach:
http://rhizome.org/editorial/2010/jan/13/interview-with-carey-lovelace-and-sharon-kanach/
The Guardian “A Guide to Iannis Xenakis’ music” (Tom Service, Classical Blog): http://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2013/apr/23/contemporary-music-guide-xenakis
Alex Ross (blog on Xenakis/review of JACK Quartet, pub. New Yorker 2010): http://www.therestisnoise.com/2010/03/xenakis-.html
編集:Andrew Freund
リサーチ・アシスタント:Clara Kim
監修:林田直樹
(2014年9月)
クセナキス:ピアノとヴァイオリンのためのディクタス
ヤニス・クセナキス
(1922年ルーマニア/ブライラ生まれ;2001年フランス/パリにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのディクタス(1979年作曲)
クセナキスは20世紀を代表する現代音楽作曲家の一人で、建築家の顔も持つ珍しい経歴の持ち主です。
ルーマニア生まれのクセナキスは、家庭の事情でギリシャに移住し、アテネ工科大学で建築学と数学を学びました。第二次世界大戦末期には、反ナチスのレジスタンス活動に参加し、顔面に大怪我を負い、左目を失ったにもかかわらず、その後もギリシャ内戦で、反政府運動に加わり、幾度も投獄され、死刑判決まで受けながらも、九死に一生を得てフランスに亡命し、ル・コルビュジエ(Le Corbusier –フランク・ロイド・ライトと並び称される近代建築家の巨匠)の事務所で働きました。クセナキスの建築家としての代表作には、ブリュッセル万国博覧会(1958年)のフィリップス館があります。
建築の師であるコルビュジエの勧めで、パリ音楽院にて、オリヴィエ・メシアンに師事。メシアンは30歳目前の異色の弟子に「ハーモニーや対位法を学ぶことも大切だが、ギリシャ人建築家で数学を学んだ経歴を作曲に活かしなさい」とアドヴァイスを送り、それが契機となり、クセナキスは数学や確率論的手法を用いた独自の前衛的作風を築いていきます。1954年に作曲した管弦楽曲『メタスタシス』で一躍大きな注目を集めました。彼の音楽にはその壮絶な戦争体験が影響していると言われています。
ピアノとヴァイオリンのための『ディクタス』(「2つの性質」という意味)は1979年に作曲された作品で、1980年に行われた第30回ベートーヴェン・フェスティバルのためにボン市から委嘱されたものです。
ソロ・ピアノで突然始まる短い半音階のつながりに、息もつかず複雑になるリズムと増え続ける音の重なりが低音部のB♭に行き着く模様は、不可解な予断を許されない現実の世界の矛盾に、躊躇することさえ遮断してしまう緊張感があります。ヴァイオリンは、指示通りに弓の根元に近い部分(au talon)の重力を使い、ダウンボウで一種野生的に我が物顔にそこに割って入ります。しかし、すぐに上昇する半音階から人格が変わったような美しいグリッサンド、ジャズ風のリズム、そしてピアノの応答となり、各楽器の特徴を活かした問答が同時に進行します。
リズムが複雑な上に、何一つとして同一でない異質な言葉は、時として雄弁に、気後れしたように、怪奇にも映る自己本位な過去と未知の世界を押し付けるような作品にしています。中間部で、唯一お互いが支え合うことができなければ先のないことを予知させるようなDの反復があります。しかし、全くロマンを感じさせない無意味なその言葉が後半(約9分を過ぎたころ)から徐々に異論を支え合っていく過程は、あたかもそれが一番自然であることを窺わせ、結果的に最後まで全面同意はしないものの、ヴァイオリンの最終音(G#)に語り尽くせない無念があることを、ピアノが認めて終わります。
勿論、数学的ともいえるリズムの変化に加え、楽器の極限の可能性を求められる音の作り方(演奏)は、演奏者に体力と情感が別物でなければならない状態を習得することを強いる作品です。それは作曲者の情感が体力に左右されることなく発散されているからかもしれません。
サルヴァートレ・アッカルド(Salvatore Accardo)のヴァイオリンとブルーノ・カニーノ(Bruno Canino)のピアノで1980年に初演されました。
演奏時間は12分程度です。
クライスラー: ウィーン奇想曲/愛の悲しみ/愛の喜び
フリッツ・クライスラー
(1875年オーストリア/ウィーン生まれ;1962年アメリカ/ニューヨークにて死去)
ウィーン奇想曲 (1902年作曲)
愛の悲しみ (1910年作曲)
愛の喜び (1910年作曲)
フリッツ・クライスラーは19世紀後半から20世紀前半を飾る伝説的なヴァイオリニストの中でも頂点に位置する人物です。柔らかくて澄んだ音色と甘く感傷的な表現力で知られ、確かにその時代の最も愛されたクラシック音楽家の一人と言えます。
彼は早くからヴァイオリンに並外れた才能を示し、有名なパリ国立高等音楽院で勉強し、わずか12歳で“ローマ賞(芸術を専攻する学生にフランス国家が授与する奨学金付留学制度)”を受賞しています。その後アメリカへの初の演奏旅行では評価は得たものの、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に入団できず、結果として医学と美術を学び、公の場で演奏を再開するのは10年後の1890年代後半になってからです。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との共演と再び行ったアメリカへのツアーが大成功を収め、名声を不動のものにしました。以降、第一次世界大戦中の従軍期間中と第二次世界大戦中の活動中断を除いて、1940年代後半に引退するまで幅広い演奏活動を行いました。
クライスラーの功績は演奏だけでなく、作曲者・編曲者として、ヴァイオリンの小品の名作を数々世に送り出したことです。(彼は大きな作品も手がけましたが、小品ほど好評ではありませんでした。)ヴァイオリニストのレパートリーの定番となっている彼の小品は、ヴァイオリンの作品群の中でも特別な一角を占めていますが、クライスラーは注目を浴びるために自作を名の知られている作曲家の作品を“発見した”或いは“~のスタイルの作品”として紹介することもあり、彼の傑作『プレリュードとアレグロ』(18世紀のイタリアのヴァイオリストで作曲家の巨匠プニャーニのスタイルで書かれた)も最初はプニャーニの作品として発表されました。
『ウィーン奇想曲』は5分にも満たない曲中に、ユーモラスな雰囲気や心優しさを感じるところ、ほろ苦さ、など様々な表情を見せ、まるで霧の中に消えるように終わります。ゆっくりとしたレントラー(ドイツ、オーストリアから起こった遅い速度のワルツに似たもの)のセクションは、香水の香りに包まれたようなメランコリックな甘さが特に印象的です。他の2曲の小品『愛の悲しみ』と『愛の喜び』は、ウィンナーワルツのスタイルで、『美しきロスマリン』と並んで最も人気のあるクライスラーの作品です。『愛の悲しみ』はセンチメンタルで、過去の哀愁を誘います。シンプルな二部形式で、いかに曲想に即した音色で演奏できるかが鍵となります。『愛の喜び』には、溢れ出るエネルギーと喜びが麗しく煌いています。
2016年5月 五嶋みどり
(編・訳:オフィスGOTO)
Notes © 2016 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
グラズノフ:バレエ音楽『ライモンダ』 Op.57より『間奏曲』
アレクサンドル・グラズノフ
(1865年ロシア/サンクトペテルブルク生まれ;1936年フランス/パリにて死去)
バレエ音楽『ライモンダ』Op.57(1896-97年作曲)より『間奏曲』(編曲:コンスタンチン・ロディオノフ)
グラズノフは、若い頃から作曲家としての驚異的な才能を現し、若干 16歳で、『交響曲第1番』がロシアの首都サンクトペテルブルクにて初演されました。グラズノフは、グリンカ等に代表されるロシアの民俗主義音楽を受け継いだ作曲家ですが、チャイコフスキーのような西洋ロマン主義の手法も消化し、彼の師であったリムスキー=コルサコフや、ボロディン、スクリャービン等とともに活躍しました。またロシア革命も経験し、彼の特徴である保守的傾向と伝統的なスタイルは、新しい体制の中で好意的に受け止められたようです。
バレエ『ライモンダ』は、名振付師であるマリウス・プティパの依頼により、1896年から1897年にかけて作曲され、1897年にマリインスキー劇場で初演されました。この作品は、『白鳥の湖』、『くるみ割り人形』、『眠れる森の美女』(作曲チャイコフスキー)の振付を手がけた巨匠プティパの最後の作品で、また、音楽もグラズノフの作品の中で最も高い評価を受けている作品の一つに挙げることができます。
『ライモンダ』は3幕のバレエで、台本は詩人のリディア・パシュコワによって書かれました。中世のヨーロッパを舞台にした恋物語で、ライモンダの恋人の騎士は巡礼の旅に出るため、二人は第1幕の最初の方で離れ離れになってしまいます。恋人が不在中に、ライモンダはサラセンの戦士に横恋慕されるのですが、恋人の騎士が無事帰還して救われます。物語は、ライモンダと騎士が結婚して、めでたく終わります。
『間奏曲』(アンダンテ・ソステヌート)は、このバレエの中の第1幕と第2幕の間に演奏されます。全体的に、夢心地でうっとりとしていて、魔法にかけられたような雰囲気が漂います。冒頭に出てくるクラリネットによるテーマは、コンスタンチン・ロディオノフの編曲版では、ヴァイオリンによって重音(3度)で演奏されます。ロディオノフはヴァイオリンの名匠ダヴィッド・オイストラフと同時代に、モスクワのグネッシン音楽院のヴァイオリン科の主任教授を務めた人物です。
2003年12月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
グリーグ:ヴァイオリン・ソナタ第1番ヘ長調 Op.8
エドヴァルド・グリーグ
(1843年ノルウェー/ベルゲン生まれ;1907年同地にて死去)
ヴァイオリン・ソナタ第1番ヘ長調Op.8(1865年作曲)
第1楽章:Allegro con brio
第2楽章:Allegretto quasi andantino
第3楽章:Allegro molto vivace
22 歳のエドヴァルド・グリーグは、1865年の夏をコペンハーゲン近郊のラングステッドで過ごし、最初のヴァイオリン・ソナタを作曲しました。その当時のグリーグは、数年間にわたる有名なライプツィッヒ音楽院での勉強を既に終えており、ブラームスやシューマンを代表とするドイツ・ロマン主義に深く影響を受けた、向上心に燃える若い作曲家でした。グリーグの作品としては、『ペール・ギュント組曲(1876年作曲)』や『ホルベルグ組曲(1884年作曲)』、『ピアノ協奏曲イ短調(1868年作曲)』など、ノルウェーの伝統文化や民族の特色が強く現れた愛国心の感じられる作品が特に有名ですが、『ヴァイオリン・ソナタ第1番』が書かれた頃から、スカンジナビアの民族伝統、中でもノルウェーの民俗や文化への興味は高まり、作品に民族主義的な傾向が強く感じられるようになります。
グリーグは、生涯で6つの室内楽曲を残しましたが、そのうち3曲がヴァイオリンとピアノのための作品であり、1865年から1887年の間に作曲されました。これらのソナタをグリーグ自身とても気に入っていて、「3つの作品のそれぞれがその時々の自分の進歩を表している。第1番は、繊細で豊富なアイデアがつまっていて・・・、第2番は国粋主義的で・・・・、第3番はより広い視野で書かれている。それぞれ私に大きな幸運を運んできてくれた」と、かつてコメントしました。
グリーグの『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番』の楽譜を見て、フランツ・リストは、若い作曲家にすぐに会いにくるよう招待しました。リストのサポートもあって、グリーグの評判は高まり、この曲は彼の作曲の才能を世に広めることになりました。
ヘ長調のソナタは、若い作曲家が急速に魅せられていたノルウェーの民俗音楽のメロディーやハーモニーの特徴も出ていますが、ドイツ・ロマン主義の色彩が色濃く残っているのは驚くべきことでもありません。冒頭でピアノが2つの静かな和音を奏でた直後に、ヴァイオリンは甘くまた希望に満ちた主要テーマを歌い始めます。メロディーラインに隠れるようにサラサラと吹く風のような印象が、音楽に幻想と新鮮さを付け加えます。
グリーグの音楽は、ありふれているとか、独創的でないとかしばしば批判されることがあります。確かに、「以前どこかで聴いたことがあるのではないか」と思わせるようなパッセージがあります。しかし、グリーグの音楽が際立っているのは、速くてもゆっくりでもテンポに関係なく、流れるような音楽と、幻想的でシンプルな民族的感情の中にも情熱的な気質が感じられるところです。これらの性質は、ヘ長調のソナタを含め、初期の作品の中に既に顕著に現れています。
軽快な第1楽章は驚くほど静かに終わり、スケルツォ形式の第2楽章へと続きます。第2楽章では、イ短調の古風なダンス音楽とイ長調で書かれたお祭りのような民族ダンス音楽が交互に出てきます。スケルツォはゆっくりな楽章に続いて第3楽章で使われることの多い形式なので、このスケルツォ形式の第2楽章は通常のソナタの型には当てはまっていません。第3楽章(最終楽章)のアレグロ・モルト・ヴィヴァーチェは、親しみやすく、陽気な雰囲気が戻ってきます。第1楽章の冒頭よりも激しく、エネルギッシュで、優しい雰囲気の中にもピアノとヴァイオリンの双方にヴィルトゥオーソ的な要素をより多く求めています。
グリーグは『ヘ長調のソナタ』に大変満足していました。1865年にクリスティアニア(現オスロ)で、ノルウェーの音楽ばかりを集めた初のコンサートで初演されましたが、グリーグは、晩年になってからもこの曲を広めるよう努力しました。このソナタは、作曲家と同時期に活躍した偉大なヴァイオリニストであるヨーゼフ・ヨアヒム(1831-1907)によって、しばしばグリーグがピアノを担当して、演奏され、一流と認められました。後にオスカー・シュムスキー(1917-2000)が世界中でリサイタル・ツアーを行っていたときに、この曲を演奏したこともありました。最近ではほとんど忘れ去られていますが、演奏されると、聴衆は必ず魅力を感じる美しくて、わかりやすい曲です。
2006年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2006 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
グリーグ:ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ短調 Op.45
エドヴァルド・グリーグ
(1843年ノルウェー/ベルゲン生まれ;1907年同地にて死去)
ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ短調 Op.45(1887年作曲)
第1楽章:Allegro molto ed appassionato
第2楽章:Allegretto espressivo alla romanza
第3楽章:Allegro animato
19 世紀末から20世紀初頭にかけてのノルウェーにおける文化的状況は、画家のムンク、劇作家のイプセンや音楽家のグリ-グらの活躍で活気に満ちていました。それまでのロマン派の流れからロシア・北欧・東欧を中心に民族主義に根ざした国民学派の音楽が作られるようになりました。政治的には不安定な状況であり、芸術的には、国土への愛着や、民族色の濃い文化作品への傾倒が強く打ち出されていたのです。
グリーグは1843年にベルゲンの音楽一家に生まれました。地元の作曲のクラスで学びながら、6歳のときに初めて母親からピアノの手ほどきを受け、15歳のとき、さらに音楽を学ぶためドイツのライプツィヒに向かいました。そこで、グリーグは故郷では聴いたことのなかったシューマン(クララ・シューマンの演奏による)やワーグナーやシュトラウスの作品に直接出会う機会に恵まれました。
ライプツィヒ音楽院を卒業と同時に、グリーグは短期間ベルゲンに帰郷した後、コペンハーゲンに活動拠点を移しました。当時コペンハーゲンは北欧文化の首都で、オーレ・ブルやノルウェーの作曲家仲間リカルド・ノルドラ-クの影響を受け、ノルウェーの文化や民俗に強く傾倒していきました。その直後から、グリーグの作品にはノルウェーの特色が色濃く現れてきます。グリーグの民族音楽や自然の風景に対する愛着は生涯変わることはありませんでした。代表作にはイプセンの劇につけた『組曲ペールギュント』やピアノ・コンチェルトがあります。
グリーグの3曲のヴァイオリン・ソナタのうち1887年に完成した第3番は、最も人気が高く、彼自身も気に入っていました。このヴァイオリン・ソナタ第3番は、3 つの楽章から構成される曲で、民族的な要素がメロディーやリズムパターンに感じられますが、ハーモニーは伝統的なロマン主義時代のスタイルで書かれています。
第1楽章は、ヴァイオリニストが太くて低いG線上でテーマを奏で(例1)、そのテーマはこの楽章のいたるところに出てきます(例2、3、4)。
例 1:ヴァイオリンとピアノ、最初のテーマ、小節番号 1-2

例 2: ヴァイオリン、小節番号 145-156
![]()
例 3: ヴァイオリン、小節番号 226-233
![]()
例 4:ヴァイオリン、小節番号 247-251
![]()
第2 楽章では、最初と最後の部分がほとんど同じで、中間部はルネッサンス時代に人気のあったパントマイムのような踊りのモリス・ダンスの音楽です。ヴァイオリンが目立つ第1楽章と異なり、第2楽章は抒情詩的なピアノのソロで始まり、孤独な本質を感動的に表現しています。
エネルギッシュな最終楽章は、ソナタ形式に展開部がついたソナチネ形式(A-B-A-B’-Coda)で書かれています。作品の終盤でこのBの部分が現れるときは、さらに激しくなり、ここではピアノが一貫して連続した音符を奏で、カンタービレ(Cantabile:歌うように)に拍車をかけます。そしてプレスティッシモ(Prestissimo:非常に早く)と表記された狂気に近いコーダの部分に突入して、最後は燃え尽きるようにこの曲は終わります。
2002年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
クルターク:ヴァイオリンとピアノのための3つの断章 Op.14 e
ジェルジ・クルターク
(1926年ルーマニア/ルゴジュ生まれ;フランス在住)
ヴァイオリンとピアノのための3つの断章 Op.14 e(1979年作曲)
第1章: Öd und traurig(退屈で憂鬱な)
第2章: Vivo(生き生きと)
第3章: Aus der Ferne: Sehr leise, äusserst langsam(遠くから:極めて小さく、非常に遅く)
ルーマニア生まれのジェルジ・クルタークは、不安定な世界情勢の影響を必然的に受けました。ハンガリーのリスト音楽院で、作曲をS.ヴェレシュとF.ファルカシュに、ピアノをP.カドサに、室内楽をL.ウェイネルに師事するために、1946年にハンガリーに移り住みました。そこでは共産党が政権を掌握した後は、検閲が強化され、革新的な芸術の発展や“ブルジョア”と考えられるものに対しては圧力がかかり、クルタークもハンガリー国内に留まるように抑圧を受けていましたが、1957年から1958年の短期間ですが、国外に留学を許され、パリに滞在し、芸術心理学者のM.シュタインと作曲家のダリウス・ミヨー、オリヴィエ・メシアンに師事しました。クルタークの創造的な個性に最も大きな影響を与えたのはシュタインでした。彼女は、限られた音符のようにはっきりと定義された制限の中で、自分自身を表現するようにクルタークを激励しました。
『ヴァイオリンとピアノのための3つの断章』は、1979年に作曲された3つの歌曲をもとにヴァイオリンとピアノのために書き直されたもので、時間、空間、音の新しい感覚を呼び起こさせます。この作品についての分析も重要ですが、『3つの断章』は、単純に聴衆を特別な世界へと運び、聴衆としての満ち足りた経験を提供します。
クルタークの作品に共通している特徴とも言えますが、『3つの断章』は大変凝縮された作品で、空虚な瞬間はありません。全く装飾が施されていない点も注目に値します。クルターク自身が「1つの音で自分の描きたい曲の全容の殆どを表現することができる」と語ったことがあるように、この曲では、細心の注意と並外れた集中力で、音符を最小限に選んで使っていることがうかがえます。それ程個々の選ばれた音符には無数の表現と意味があり、彼の思い描く人間像が表れています。クルタークは、誇張することなく、内面の創造的モティヴェーションに背くことなく、シンプルで、思慮深く、ダイレクトな音楽を書きます。
そういう意味では、『3つの断章』は、アントン・ウェーベルン作曲の『4つの小品 Op.7』と比較すると興味深いです。クルタークの作品は、ウェーベルンの作品よりも試験的な要素が少ないように感じられますが、両方とも、それぞれの音符の中に無限の世界が広がっているのは確かです。ウェーベルンがジェスチャーや音符の中にメッセージをぎっしりと詰め込もうとしているのに対して、クルタークは、邪魔になるような要因を取り除いてコミュニケートしようとしているようです。
『3つの断章』は、全編にわたり、ヴァイオリンがミュートをしたまま演奏されます。ヴァイオリンの開放弦をふんだんに使用し、ピアノのもたらす音色によって補完された、抑えられた音は、ミステリアスで、奇跡的な響きをかもし出します。3つの断章はどれも短く、雰囲気はそれぞれ特徴的で、第1章の夢のような雰囲気から第2章のスケルツォへ、そして聖歌のような第3章へと続きます。しかし、それらが一体となって、“現実”の異なる本質に対する深い印象を聴衆の心に刻みこみます。
2004年11月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ゲール:ヴァイオリンとピアノのための組曲 Op.70
アレクサンダー・ゲール
(1932年ドイツ/ベルリン生まれ;イギリス在住)
ヴァイオリンとピアノのための組曲Op. 70(2000年作曲)
第1楽章:Prelude
第2楽章:Rain Song “The days of summer are gone”, with variations
第3楽章:Three-part Invention
今日の最も重要なイギリスの作曲家の一人であるアレクサンダー・ゲールは、彼の生きる時代にどうすれば作曲家として生き残れるかということに神経を使い、時代に即した音楽を書くことに執着しているのではないかと言われています。
ゲールの音楽には、様々な影響が感じられます。彼の父親は有名な指揮者のウォルター・ゲールで、シェーンベルクにも師事したことがあり、大変彼のことを尊敬し、12音技法や新ウィーン学派について熟知していました。息子のアレクサンダー・ゲールは一時期12音列スタイルに固執したこともありましたが、結局、シェーンベルクをはじめ、メシアン、ドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキーやヤナーチェクといった作曲家の作品に影響を受け、その上で、彼の場合は故意に12音技法を使用するでもなく、自然にかつ的確にそれが現れている次元に到達しました。
『ヴァイオリンとピアノのための組曲』は、ハーバード音楽協会から委託された作品で、2000年4月25日に初演されました。
この作品は3つの楽章から構成されており、全体的にヘブライ風の性質を帯びており、ゲールが若い頃一時期シオン主義グループの一員であったときの影響が考えられます。第2楽章は、特に、ユダヤ音楽やヘブライ音楽の特徴である増三全音が強調され、心に響く不協和音、声楽スタイルの装飾音符が出てきます。この作品は、いくつかの印象的な旋律やモティーフの移調と転回が繰り返し見られますが、無調です。
第1 楽章のプレリュードは、ヴァイオリンのレチタティーヴォで始まり、この楽章の主要な楽想がすべて紹介されます。速度の変化によって分離された複数の分節があり、それぞれの分節は、オープニングのレチタティーヴォの一部が使われ、何か違うものや新しいものを生み出しています。ゲールは特別そのように呼んではいませんが、実際は、分節ごとの一連のヴァリエーションのような楽章と言えます。おそらく最初にこの曲を聴いたときに、印象に残るのは、曲の最初に出てくる5連符でしょう(譜例1参照)。たとえば、このモティーフは何度もこの楽章に出てきて、ピアノとヴァイオリンの双方によって奏でられますが、それぞれ少しずつ違っています(譜例2、3参照)。この楽章の最後もこのモティーフが現れて終わります(譜例4参照)。
(譜例1:第1楽章冒頭)

(譜例2:小節番号14~15)

(譜例3:小節番号42~43)

(譜例4:小節番号72~74)

第2 楽章は、タイトルが『雨の歌“夏の日々が過ぎて”ヴァリエーションとともに』となっており、出所の確かでない中世(9世紀から11世紀)のヘブライのアクロスティックな詩に基づいています。アクロスティックな詩では、各行頭の文字が作家の名前などの重要な何かをつづっていて、中世のユダヤ文化では一般的な詩の形でした。この雨の歌は、特に、収穫を祝う喜びの歌です。テーマは、オフビートの、いつも小節の第1拍目にくるとも強拍にくるとも限らないアクセントのついた拍によって特徴付けられていて、どちらかと言うと、修辞的でだんだんと装飾が増していきます。テーマの最終分節は、特にノスタルジックで、ヴァイオリンがハーモニックスを奏でることでその感情がより高まります。それぞれのヴァリエーションは明確なリズムパターンで特徴付けられています。2番目のヴァリエーションは、特に、拍子が混交しており、オフビートのアクセント(シンコペーションの変形)があり、演奏者にとっては技量が試されるところです。この種の複雑さは、テンポを高めるリズムの非同期化が行われる新しい音楽の分野では典型的です(譜例5参照)。
(譜例5:第2楽章VARIATION 2 小節番号51~53)


第3 楽章の3パートインヴェンションは、前の楽章を引き継いだ第5ヴァリエーションのようです。他の楽章に比べてはるかに短く、対位法的に書かれており、伝統的な音楽要素を、個性的に現代風に操るゲールの熟練の作曲技術を示した楽章です。この楽章は、特にバッハのスタイルが顕著で、時代を超えても作曲家にとって絶対不可欠の物の一つであると考えられている対位法を熟知し、うまく書かれています。タイトルからも察しがつくとおり、3つのパートに分かれており、その間に2つのエピソードが挟まれています。対位法で書かれた作品に典型的な、全体的にすがすがしい雰囲気がして、激しい部分は曲の最後に現れ、ピアノは一つの音を奏で、唐突ではありませんが、滑稽な印象を与えます。
2004年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
サーリアホ:作曲家基本情報
作曲家基本情報:サーリアホ
作曲者名:
カイヤ・サーリアホ Kaija Saariaho (née Kaija Anneli Laakkonen)

生年月日:
1952年10月14日
出生地/居住地:
フィンランド、ヘルシンキ生まれ/フランス、パリ在住
スタイル:
ポスト・スペクトル音楽、電子的影響
最初に習った楽器:
ヴァイオリンとピアノ
恩師/影響/出身校:
ヘルシンキのルドルフ・シュタイナー学校とシベリウス音楽院にて学ぶ。
フライブルクにてブライアン・ファーニホウとクラウス・フーバーに師事。パリIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)で、ジェラール・グリゼーとトリスタン・ミュライユから最大の影響を受ける。
代表作:
睡蓮Nymphéa (1987年作曲)
デュ・クリスタル(水晶から)Du Cristal (1989年作曲)
彼方からの愛 L’ Amour de loin (2000年作曲)
4つの瞬間Quatre Instants (2002年作曲)
シモーヌ(・ヴェイユ)の受難La Passion de Simone (2006年作曲)
ノーツ・オン・ライトNotes on Light (2006年作曲)
ミラージュ(蜃気楼)Mirage (2007年作曲)
エミリーEmilie (2008年作曲)
D’OM LE VRAI SENS (2010年作曲)
サークル・マップCircle Map (2012年作曲)
編集:Andrew Freund
リサーチ・アシスタント:Clara Kim
監修:林田直樹
(2014年9月)
サーリアホ:カリス(聖杯)
カイヤ・サーリアホ
(1952年フィンランド/ヘルシンキ生まれ;フランス/パリ在住)
カリス(聖杯)(2009年作曲)
第1楽章 Rubato, dolce
第2楽章 Lento. Misterioso
第3楽章 Agitato
フィンランドの作曲家、カイヤ・サーリアホの音楽観は非常に独特で、聴衆を優雅で神秘的な世界へといざないます。受賞歴は華々しく、特に彼女の官能的で謎めいたオペラは高く評価され、クーセヴィツキー音楽財団などから作品を委嘱されています。ヘルシンキ生まれのサーリアホは、地元のシベリウス音楽院で、ヴァイオリンとピアノの教育を受けました。サーリアホの作曲法はIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)での電子音楽研究の影響が色濃く、従来の楽器の音とコンピューターで合成された創作音との組み合わせによる作品を多く書いています。もちろん電子音楽のみの作品も、楽器の音のみの作品もありますが、彼女の作品には、常にコンピューターで生成された音の斬新な響きが感じられるような気がします。
『カリス(聖杯)』は、スペインのマドリッドにあるソフィア王妃高等音楽院の委嘱により、2009年に作曲されました。音楽院では、才能ある学生達が同時代の音楽に触れる機会を増やすために、スペイン国内外の作曲家へ数多くの委嘱を依頼しており、委嘱作品の長さや編成、形式などは全て作曲家に任されています。サーリアホは委嘱を受けて、1994年に自身が作曲したヴァイオリン協奏曲『聖杯の劇場(Graal Theatre)』(1995年のBBCプロムスにおいて、エサ=ペッカ・サロネン指揮のBBC交響楽団とこの曲を献呈されたギドン・クレーメルによって初演)を改作することにしました。
ヴァイオリン協奏曲『聖杯の劇場』は、もともと10作のシリーズからなるフロランス・ドゥレ(Florence Delay)とジャック・ルーボー(Jacques Roubaud)共作の劇『聖杯の劇場(Graal Theatre)』からインスピレーションを受けています。この劇は『アーサー王物語』、『円卓の騎士』、そして『聖杯』の話が一つの作品にまとめられたもので、アリマタヤのヨセフ(Joseph of Arimatheaイエスの遺体を引き取って埋葬されたとされるユダヤ人)とマーリン(Merlinアーサー王の助言者で魔術師)の争いから始まります。これは、タイトルの「聖杯」と「劇場」からもわかるように、神聖なものと世俗的なものが一つの作品の中で対立しており、その相反する2つの概念が本作品『カリス(聖杯)』では描かれています。
サーリアホの作品の中でも上演される機会の多いオペラ『彼方からの愛/遥かな愛(L’amour de loin ? “love from afar”)』も、『聖杯の劇場』や『カリス』同様、中世を舞台にした作品です。サーリアホのサイバネティクス/人工頭脳に触発された音楽を聴き入ると、現代とはかけ離れた神秘的な時代(この作品では、魔術が重宝されていた失われた時代)を探求しているような気持ちになります。
『カリス』は、3楽章からなる15分程の作品で、静的なセクションと、急速に進行する動的でスケールのような線的音形とが、コントラストをなしています。「静」と「動」が対峙するというこの作品の原則は、特殊奏法によって奏でられる「スムース」と「ノイジー」のコントラストと言うこともできます。静けさを表現する際には、スル・タスト(弓を指板寄りに弾く)が頻繁に使用され、一方で、激しいセクションでは、極端なポンティチェロ(弓を駒寄りに弾く)と激しいトレモロが使用されます。またハーモニクスを使うことで不気味さが増し、より幻想的になります。全体を通して、多少ポストセリエスト的なところもありますが、素材が熱狂的に取り扱われることで、激しさも静けさも増幅し、サーリアホの様々な意図がより明確になります。
『カリス』はソフィア王妃高等音楽院のほか、2009年11月にハンブルクにて、北ドイツ放送交響楽団の現代音楽シリーズの中で取り上げられ、ヴァイオリニストのカロリン・ヴィトマン(Carolin Widmann)とピアニストのデーネシュ・ヴァーリョン(Denes Varjon)によって初演されました。
2014年8月 五嶋みどり
(訳・編:佐野浩介)
Notes © 2014 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
サッリネン:4つのエチュード Op.21
アウリス・サッリネン
(1935年フィンランド/サルミ生まれ)
4つのエチュードOp.21 (1970年作曲)
2010年に75歳を迎えたアウリス・サッリネンは、フィンランド出身の優れた現代作曲家の一人で、『騎士(Ratsumies)』(1974年)や『赤い線(The Red Line)』(1978年)などのオペラの作曲で名声を得てから、今日までに8つの交響曲、6つのオペラを含む数多くの作品を生み出しています。壮大なスケールのオペラから、クラシック音楽ではあまり使われない、例えばアコーディオンに代表されるような楽器のための作品にいたるまで、その範囲は幅広く、バラエティーに富んでいます。初期には一時的に、12音技法で作曲したこともありましたが、彼の作風はどちらかというと調性のある保守的なスタイルです。
サッリネンは早くからヴァイオリンとピアノを習い、若い頃にはクラシック音楽だけでなくジャズにも傾倒していました。ヘルシンキにあるシベリウス音楽院に入学し、ヨーナス・コッコネンやアーレ・メリカントのもとで作曲を学び、卒業と同時に、同音楽院での教職と、フィンランド放送交響楽団で人事を担当していました。1981年にフィンランド政府から終身芸術家に任命された後、ようやく作曲活動に専念できるようになりました。最も名誉あるシベリウス賞(1983年受賞)の他にも、錚々たる賞をこれまでに受賞しています。
サッリネンは、数は多くないものの、ヴァイオリンのための作品も手がけており、中でも重要なのは、かなり初期の頃に作曲された『ヴァイオリン協奏曲』(1968年)です。『4つのエチュード』はそれから2年後の1970年に作曲されました。メロディックでスピリチュアルなこの曲は、全体的にノスタルジアやロマンティシズムが感じられます。それぞれの曲は短く、全曲でも5分以内に終わるとても短い曲ですが、繰り返しや様々な異なる要素が強調されています。
ピアノパートは一貫して簡潔に美しく印象的に書かれていて、質感やスタイルには、ショスタコーヴィチやバルトーク的な要素がみられます。4つのエチュードが展開していくにつれて徐々に厚みが増していきます。
ヴァイオリンのパートは音高(ピッチ)の関係性が特徴的です。最初のエチュードは、ヴィオリンの4つの開放弦のうちG、D、Aの3つのピッチを中心としながらも、半音階のような音階が印象的です。これは2つのピッチ間の動きとしては本質的に異なる方法の研究です。
2番目のエチュードは、最初のエチュード同様に、3つの開放弦のピッチを中心に展開しますが、今回はフラジオレットが使われています。サッリネンは3つのピッチのそれぞれをセクションごとの重要なポイントとみなし、リズムの異なるスピードの違いで成果を表現しています。これも3つのピッチを探求するレッスンです。またこのエチュードは、ピアノのアルペジオのハーモニー・コードが際立っています。終盤はヴァイオリンの4番目の開放弦のピッチであるEに到達してクライマックスを迎えます。
3番目のエチュードは最も短く、これまでの要素にトリルが加わります。最終セクションの前段階として、合唱のような荘厳な響きがあります。4番目のエチュードはピアノのやわらかいチャイムのような和音で始まり、2小節に1度ある付点のリズムは音楽の方向性を示しています。最後のエチュードでは、ヴァイオリンはオクターブで、透明で神秘的な音が貫かれています。ヴァイオリンが霧の中に消えていっても、完全な静けさの中に心臓の鼓動が響くようにピアノの和音が続きます。
2010年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2010 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン Op.20
パブロ・デ・サラサーテ
(1844年スペイン/パンプローナ生まれ;1908年フランス/ビアリッツにて死去)
ツィゴイネルワイゼンOp.20 (1878年作曲)
パブロ・デ・サラサーテは、スペインのパンプローナの音楽的で質素な家庭に生まれました。パリ音楽院で学び、ヴァイオリニストとして、作曲家として活躍し、フランスでその生涯を閉じました。彼の作風からは、彼の受け継いでいるスペインとフランスの伝統に加え、ロマ(いわゆるジプシー)的とも言える遊動、悲哀、衝動、情熱、即興の要素がうかがえます。
サラサーテの代表作である『ツィゴイネルワイゼン』は1878年に作曲され、同年ライプツィヒで初演されました。現在でも最も人気の高い有名な作品で、一度聴いたら忘れられない曲です。題名は2つの言葉から構成されています。ツィゴイネルがドイツ語で「ジプシー」を意味し、ワイゼンは「歌」を意味します。この作品はピアノ伴奏で演奏する場合とオーケストラと共に演奏される場合があります。ツィターを真似たような音や鳥の鳴き声のような音、威嚇するような声からすすり泣きまで幅広く表現されており、効果的に演奏されれば必ず聴衆を虜にしてしまう作品です。
この曲にはチャルダーシュという1850年代から1880年代に大変人気のあったハンガリーの田舎の民族ダンスのリズムが頻繁に使われています。チャルダーシュはシンコペーションのリズムをしばしば伴った2拍子の音楽です。威厳や誇りを表す遅いテンポの部分と、速いテンポの部分は交互に組み合わされているのが特徴です。『ツィゴイネルワイゼン』では、アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェから徐々に盛り上がり、聴衆が息をとめて釘付けにさせられるような力強い終わりを迎えます。この曲はロマの音楽家にも好まれ、今日ではコンサートホール以外の様々な場所で演奏されています。
ヴァイオリニストとしてのサラサーテの名声は、彼の完璧なまでの演奏技術によります。楽器を自由自在に操り、技術的に完璧な演奏をすることで有名でしたが、彼の音色は同じように絶賛はされませんでした。彼の奏でる音は基本的には大変美しいものでしたが、その演奏は感情表現の変化に欠け、表情が乏しいと批判されました。彼が作曲した作品も、人の魂に響くことを目的とした深みのある曲ではなく、むしろ、彼の持っている高い技術が存分に発揮でき、聴衆に強い印象を与えるのを目的としたような曲でした。サラサーテは社交上でも大変機転がきく二枚目として知られていました。彼のそのような魅力も、裕福で影響力のあるファンの人気を不動のものにした重要な要素であったと言われています。
サラサーテは、ヨーロッパや南北アメリカ大陸の全ての主要なステージでコンサートを行いました。全盛期には聴衆や音楽家、特に作曲家に賞賛され、当時の作曲家の多くは彼のために曲を書き、献呈しました。サン=サーンスもそうした作曲家の一人で、『序奏とロンド・カプリチオーソ』(同曲の作品解説参照)の他に、3曲あるうちの2曲のヴァイオリン協奏曲がサラサーテに捧げられています。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ
カミーユ・サン=サーンス
(1835年フランス/パリ生まれ;1921年アルジェリア/アルジェにて死去)
序奏とロンド・カプリチオーソ(1863年作曲)
カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)は1835年にパリで生まれ、2歳半より叔母から音楽の手ほどきを受け、3歳で最初の作品を作曲し、7歳のときにピアノ演奏で聴衆を魅了するなど、モーツァルトに匹敵する神童と言われていました。また、音楽以外の分野においても秀でており、その多才ぶりを発揮しました。しかしながら、モーツァルトと違い、サン=サーンスは後世に引き継がれるスタイルを残すことはできませんでした。
パリ音楽院を卒業した後も、サン=サーンスは演奏家として、また作曲家としての活動を続けました。特にピアニストやオルガニストとして名を馳せ、リストからは「世界で一番偉大なオルガニスト」と賞賛され、ベルリオーズからは「サン=サーンスは何もかも心得ている。足りないのは未知の経験だけだ」と言わしめました。
サン=サーンスは、若い頃は古典的かつ近代的な思想の持ち主であったと考えられています。保守派からは一線を画したシューマンやワーグナーに代表されるような作曲家の新しい音楽を熱心に支持しました。しかし、また彼はラモーやヘンデルやグルックといったバロック音楽にも魅力を感じ、彼らの作品を研究しました。ライプツィヒでのメンデルスゾーンと同じように、サン=サーンスもバッハを熱心に擁護し、今日では当然のことと思われているこの偉大なるドイツの作曲家への関心を復活させようとしました。
しかし、サン=サーンスは年をとるに従い保守的になっていきました。ドビュッシーやストラヴィンスキーなどの20世紀初期の現代音楽を容赦なく批判し、また彼の気難しい性格が災いして多くの敵を作りました。
サン=サーンスは40歳頃に結婚しましたが、2人の子供が幼いときに亡くなるなど、結婚生活は幸せなものではありませんでした。サン=サーンスは母親との結びつきが強く、妻との生活もうまくいきませんでした。長期にわたって家を空け蒸発してしまい、サン=サーンスは自分の家庭よりもフォーレの家族と親密な付き合いをするようになりました。
母親が亡くなってからは、悲しみにふけり、仕事や休暇にと頻繁に旅行に出かけるようになりました。彼はアルジェリア、スカンジナヴィアやロシアなど多くの国を訪れ、様々な異なる文化に触れ、その土地独特の「音」にインスピレーションを感じました。
『序奏とロンド・カプリチオーソ』は1863年に作曲され、当時の人気ヴァイオリニストであったサラサーテに献呈されました。サン=サーンスは、他にも『ハバネラ』と『カプリス・アンダルチア』というヴァイオリンとオーケストラのための曲を2曲作曲しました。また3つのヴァイオリン協奏曲も作曲し、中でも第3番ロ短調はよく知られています。
『序奏とロンド・カプリチオーソ』は映画にも用いられるなど、大変人気のある曲です。この曲はサラサーテをはじめとする多くのヴァイオリン名手に好まれ、ハイフェッツやフランチェスカッティはコンサートでよく演奏しました。スペインの影響を感じる向きもありますが、あくまでもフランス作品であると考えられており、当時のフランス音楽を代表する作品の一つと考えられています。
この曲は、ソロと伴奏の役割がはっきりしており、ソロは常に伴奏の上に浮き立つようになっています。序奏の冒頭部分では、オーケストラ(またはピアノ)がヴァイオリンのソロを2小節先行します。オーケストラでもピアノでも、ここの伴奏部分はギターで弾かれた分散和音のような効果があり、この作品の中で最初にスペインの影響を感じさせる部分です。スペイン民謡や映画などに登場するように、ギターをかき鳴らすような響きに短調を組み合わせたところに、スペイン音楽の伝統を引き継いでいることが表れています。冒頭のリズムが繰り返される一方で、ソロ・ヴァイオリンは郷愁の音色で最初のテーマを奏でます。この部分でのヴァイオリンのテーマは、基本的にアルペジオと半音階の変形によって成り立っています。
一連の高揚するトリルで序奏が終わり、その後ロンドの部分が続きます。ソロが冷静で冷めたもの悲しさを表現する一方で、伴奏は執拗に同じリズム・パターンを繰り返します。このもの悲しさは曲全体に漂い、技術的に難度の高い最大の山場の部分ですら、その性格を変えることはありません。
一般的に、ロンド形式というものは活き活きとした性質の主要なテーマ(主題)があり、それが一定の間隔で繰り返されながら、対照的な素材で作られた挿入部をつなぐ役割を果たします。この形式は、モーツァルトやハイドンの作品でもよく使われています。『序奏とロンド・カプリチオーソ』では、ロンドの中間部が同じような憂いを帯びているとはいえ、他の部分とは明らかに様子が異なります。ここには和声にエキゾチックな要素が加わっているからで、スペイン系、またはムーア系の影響を色濃く見せています。短調と長調の要素が入り混じり東洋的(非西洋的)な音階や響きを作り出します。ペルシャやアジアといった東洋の文化を暗示し、ベリーダンスやアジアの景色など、聴く者の想像力をかきたてます。
ロンドの主題が最後に戻ってくると、伴奏を担っていたオーケストラ(ピアノ)がテーマを奏で、ソロ・ヴァイオリンは広範囲に渡って行き来するアルペジオを弾き、従属的な役割に移ります。ロンドは高音のホ音でクライマックスに達し、連続する和音からなる小カデンツァで終わります。そして、これまでには見られなかったような軽快で陽気なコーダが始まります。この旋律はヴァイオリニストにとっては技術的に非常に難しいのですが、一瞬にして通り過ぎ、聴衆を圧倒して終わります。
しばしば小品というものは、音楽的というよりテクニック的に見せることの多いものですが、この作品は音楽的であり技術的にも大変すぐれているため、昨今のヴァイオリニストたちにもよく演奏されるのでしょう。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シェーンベルク:ピアノ伴奏を伴ったヴァイオリンのための幻想曲 Op.47
アルノルト・シェーンベルク
(1874年オーストリア/ウィーン生まれ;1951年アメリカ/ロサンゼルスにて死去)
ピアノ伴奏を伴ったヴァイオリンのための幻想曲Op.47(1949年作曲)
この曲はシェーンベルクが作曲した最後の室内楽曲で、1949年9月、献呈されたアドルフ・コルドフスキー(1905-1951年)によって、シェーンベルクの75歳の誕生日に初演されました。
無調音楽の代表的作曲家であり、十二音技法の創始者であるシェーンベルクの音楽は、彼の弟子のアントン・ウェーベルン(1883-1945年)やアルバン・ベルク(1885-1935年)の作品と同様に、従来の音階に慣れ親しんでいる音楽愛好家には、その難解なイメージから敬遠されている感じがあります。しかし、そのイメージとは裏腹に、「十二音技法は、一般的に思われているように近づきがたく排他的な作曲法ではなく、論理的秩序のもとに構成されるもので、判り易いのが特徴である」と自著『私の発展』(1949年出版)の中で述べています。
シェーンベルクのヴァイオリンのために書かれた作品は『ヴァイオリン協奏曲』とこの『幻想曲』の2曲だけですが、8歳でヴァイオリンを習い始めた彼は、楽器の特性を熟知しており、作曲家としてのキャリアの早い段階から、ヴァイオリン・パートを含んだ作品を書いていました。
『幻想曲』は情熱的で朗々としたメロディーで始まります。全体的にもセクション内でもメロディーは甘美に、また暗く静寂に、ユーモアと神秘をちりばめながら流れていきます。ウィンナーワルツというよりもフォークダンスを髣髴させるセクションのヨーデル(裏声と地声を交互に織り交ぜるように歌うアルプス地方発祥の歌唱法)のような響きの後、情熱的なオープニングのテーマがコーダセクションで再現され、すぐにヴィルトゥオーソのクライマックスへと導かれます。
この作品を細かく分析していくと、シェーンベルクが1オクターブの中にある12の半音を6音ずつ前半と後半の二つのグループに分け、その音列の集合体をベースに、11のグループを作り出し、この曲を構築していることがわかります。構成の精巧さは言うに及びませんが、この作品は、注釈を必要としないほど表現力が豊かで、音楽の素晴らしさがダイレクトに伝わってきます。
2005年/2016年5月改訂 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シマノフスキ:3つの神話 Op.30
カロル・シマノフスキ
(1882年ウクライナ/ティモシュフカ生まれ;1937年スイス/ローザンヌにて死去)
3つの神話 Op.30(1915年作曲)
- アレトゥーザの泉
- ナルキッソス
- ドリュアスとパン
20世紀前半はフーベルマン、クライスラーやイザイなどの偉大なヴァイオリニスト達が多く活躍した“ヴァイオリニスト達の黄金時代”と言えます。驚くべき数の活動的な演奏家がヴァイオリン奏法の基準を高め、世紀を越えて現在に伝えられています。
このような芸術的に活気に満ちた時代に生きたパウル・コハンスキ(1887-1934)もヴァイオリンの巨匠達のうちの一人に数えられるでしょう。ヴァイオリニストとして卓越した技術を持っていただけでなく、コハンスキは音楽仲間からも尊敬される音楽家でした。特に彼が協力し、影響を与えた作曲家は多く、中でもプロコフィエフやストラヴィンスキーや同じポーランド人のシマノフスキらはコハンスキから強い影響を受けました。また彼は他の楽器のために作られた曲をヴァイオリンのために編曲することも得意としていました。
カロル・シマノフスキはコハンスキの5歳年上で、1882年にウクライナで生まれました。20世紀前半のポーランドを代表する作曲家で、現在では作曲家として高い評価を得ていますが、当時は作曲家というよりも偉大なピアニストの一人として知られていました。
シマノフスキの想像力豊かなインスピレーションは、ギリシャやアラビア・ペルシャの古代文学からの発想によるものです。愛の哲学に魅了され、彼は熱情とエクスタシーの世界に引き込まれ、心を奪われます。ヴァイオリンの為の曲を書くにあたり、シマノフスキはコハンスキに協力を求め、技術的なアドヴァイスを受けました。現在シマノフスキのヴァイオリン曲の特徴と認識されている新しい色彩やスタイルは二人で共同して作り上げたものと思われます。
彼ら独特の色彩感覚を明確に簡単に言葉で表すことは出来ません。シマノフスキのフレーズは非現実的で空中に浮かんでいるようです。かすかな光を放ち、時に感覚的であり、ほとんど停止しているかのようなところもあり、不吉で不安感にさいなまれた雰囲気が漂っています。この新しいスタイルが創造され、確固たるものとなったのが“神話”です。「今まで試みられなかった様式の音楽による語りかけ」と本人が述べています。
この曲はギリシャ神話の登場人物に基づく3つの音楽詩で、ヴァイオリンのトレモロやトリル、重音、ハーモニクスやピチカート、ミュート(弱音器)のオン・オフ、またピアノの広音域にわたるアルペジオ、幻想的な和音、ペダルの操作など、多種多様な音響効果を使って、古典文学を想起させます。
- アレトゥーザの泉
水の精アレトゥーザは狩りと森を愛し、男性に心を動かされることはありませんでした。ところが、川の神アルペイオスはそんなアレトゥーザに恋をしてしまったのです。水浴びをしていたアレトゥーザは思わぬ展開に全速力で逃げますが、彼が近づいてくるのに気づき、女神のアルテミスに助けを求め、アルテミスはアレトゥーザをすばやく泉に変えてやります。その伝説の泉はイタリアのシラク-ザのオルティギアに残っています。
シマノフスキはピアニストに両手を自由自在に交差させて演奏させることで水の流れを表現させ、ヴァイオリニストはそのピアノをバックに、ミステリアスな神話的なメロディーを奏でます。水が流れる様子はヴァイオリンのトリルや重音の指を変えながらの上行からも想像することができます。テンポはフレキシブルで、そのときの雰囲気に合わせて、伸びたり、速くなったりします。最後は泉の細かい泡が消えて、神秘的に終わります。
- ナルキッソス
ナルキッソスは泉に映った自分の姿に恋してしまい、どうしようもなく、悲しみに打ちひしがれて、その泉のそばで死んでしまいます。全ての精が彼の死を深く悲しみ、お葬式を準備していると、彼の体が消え、そこに花が咲き乱れました。その花は彼の名前にちなんで水仙(Narcissus)と呼ばれるようになりました。この音楽詩は夢のようななまめかしい雰囲気を持ち、緊迫した不安感があります。まさに恋に落ちているという感覚です。meno mosso (より遅く)と記されている第2セクションは、魔法にかかったような天啓の一瞬です。2つの楽器がお互いを追いかけあい、小さい石が泉に投げられたとき波紋が広がるように、自分の姿が不安げに揺れ動く様子を音楽で表現しています。この音楽詩は謎と自己喪失の暗示の中で消えていきます。
- ドリュアスとパン
パンは半分人間半分動物のマイナーな牧神です。彼の容姿は彼を見てしまった者にパニック状態を引き起こします。パニック(panic)という言葉もこの神話のパン(Pan)の名前に由来しています。彼はヘルメスの子孫で、ヤギ飼いや羊飼いにあがめられており、木の精や森の妖精ドリュアスを次々に好きになり、追いかけまわします。妖精シューリンクスはパンに捕らえられるのを恐れて、父親の川の神ラドウに嘆願し、川の葦に変えてもらいましたが、パンはその葦から笛を作り、常に持ち歩いたと言われています。ヴァイオリンのハーモニクス(楽器の倍音を使った特別な効果を持つ音)がこの笛の音を表現しています。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シマノフスキ:『クルピエ地方の歌』 Op.58より 『いななけ、仔馬よ』
カロル・シマノフスキ(コハンスキ編)
(1882年ウクライナ/ティモシュフカ生まれ;1937年スイス/ローザンヌにて死去)
『クルピエ地方の歌』Op.58より『いななけ、仔馬よ』
カロル・シマノフスキ(1882-1937)は20世紀前半のポーランドを代表する作曲家です。彼は55年の生涯のうちに62曲の作品しか作曲しませんでした。そのうちヴァイオリンのために書かれた曲の中では、2曲のヴァイオリン協奏曲や3 つの音楽詩からなる『神話』が有名です。『クルピエ地方の歌』Op.58は1930年から1933年にかけて作曲された12曲セットの作品で、『いななけ、仔馬よ』はその中の9番目の曲です。この作品はもともと歌曲で、友人のコハンスキ(1887-1934)がヴァイオリンのために編曲したものです。
シマノフスキが20代の頃はワーグナーやリヒャルト・シュトラウスに影響を受けて、『演奏会用序曲』Op.12、『交響曲第2番』Op.19やオペラ『ハギート』Op.25が作曲されました。第一次世界大戦の頃には、シマノフスキはドイツ・ロマン主義の様式から離脱して、アラビアの古代文学、キリスト教、ギリシャ文明の研究に没頭し、また、戦争のために演奏活動が中断されたこともあって、この時期の数年に作曲家として最も創造的な作品を数多く生み出しました。ただ一時期、彼は作曲活動から完全に離れ、夢中になっていた愛やエロティシズムという世界を探求した長編小説を書きましたが、作曲活動の再開は、大曲のオペラ『ロジェ王』でなされ、その中で愛の哲学をさらに発展させています。
シマノフスキが30代後半から40代の頃は、“民族主義”の時代と言われています。シマノフスキは作曲家として、またピアニストとして、同じポーランド人でヴァイオリニストであり作曲家であるコハンスキと若い頃から協力し合い、新しいポーランド音楽のリーダーとなって活躍しました。二人は創造的刺激と技術的なアドヴァイスやデモンストレーションを互いに受け、影響し合って“ポーランド音楽”の活動に没頭し、音楽の民族主義を確立し、作曲したと考えられています。コハンスキ作曲のヴァイオリンとピアノのための小品はシマノフスキの深い影響が見られます。シマノフスキはコハンスキや、やはりポーランド人のピアニスト、アルトゥール・ルービンシュタインと共にコンサートツアーをするなどの交友関係がありました。後に、コハンスキとルービンシュタインはアメリカに移民しましたが、シマノフスキは彼らの熱心な説得にもかかわらず、母国にとどまります。そして、音楽教育を通じて、特に若い作曲家をサポートすることで、“民族主義”に貢献しました。シマノフスキがポーランドの民族的スタイルを取り入れ、その起源を徹底して研究し、独特の音楽言語を形成し、しかも芸術的にも最も水準の高い曲を創作し、集団意識を確立しようとしていた頃、国が念願の独立を果たす歴史的な日を迎え、彼はポーランドに戻ります。タトラ山麓とクルピエ平原の民謡の研究をもとに8年の歳月をかけて彼の代表作の一つ、バレエ音楽『ハルナシェ』が1931年に完成し、その後『クルピエ地方の歌』が生まれました。彼はワルシャワ音楽院のディレクターとなりましたが、あまりに熱心に新しい教育方法を推進し、結果として音楽院の保守勢力の反感を買い健康を害して辞めざるを得なくなりました。
『いななけ、仔馬よ』は、コハンスキがヴァイオリンのために編曲した作品の一つです。原曲はソプラノとピアノの曲ですが、コハンスキの編曲は原曲より優れた効果を発揮しています。『クルピエ地方の歌』Op.58は単純化されたメロディラインで、クルピエ地方の民謡を精巧に磨き上げたような作品です。『いななけ、仔馬よ』の歌詞は、失恋について語るのに馬を暗喩として使っています。
『いななけ、仔馬よ』
嘶け、馬よ、嘶け、
この畑を飛んでいくカラス
窓にたたずむ
僕の恋人にきこえるように。
藁の切り藁がもうなくなってしまったので、
ズドンコフスキ風の飼い葉桶の傍らに馬が立っていた、
だがだれが 私の恋人を待っているか
このズドンコフスキの桶の中で、
ヘイ、急げ、黒馬、坂を下って、
足を踊らせ、
たった一人の、碧い眼の私の恋人のもとへと。
オイ、この惜し気もなく使ってきた、
金色の手綱は惜しくもないが、
ただ 惜しいのは、
私をこんなに虚しくしている
去っていってしまった、お前のこと。
『シマノフスキ-人と作品』p.180-181
田村進[監修] 日本シマノフスキ協会[編] 春秋社
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シマノフスキ:ヴァイオリンとピアノのための夜想曲とタランテラ Op.28
カロル・シマノフスキ
(1882年ウクライナ/ティモシュフカ生まれ;1937年スイス/ローザンヌにて死去)
ヴァイオリンとピアノのための夜想曲とタランテラ Op. 28 (1914-1915年作曲)
作曲家であり、ピアニストでもあったカロル・シマノフスキは、芸術が奨励されるような環境の中で育ちました。小さい頃から、他の4人の兄弟たちと音楽や文学、視覚芸術に接していました。シマノフスキは、叔父のグスタフ・ノイハウス(伝説的なピアニストであるハインリッヒ・ノイハウスの父)から音楽の手ほどきを受けました。しかし、彼の創造力豊かな作風は、同じポーランド人で著名なヴァイオリニスト兼作曲家のパヴェル(パウル)・コハンスキ(1887-1934年)から最も強く影響を受けたと思われます。
シマノフスキは20世紀前半のポーランド音楽界の中心的な人物でした。彼の音の世界は、異国情緒、上品さ、神秘性、情熱といった要素をうまく組み合わせた折衷主義で独特のものです。また、彼の音楽様式は、印象主義、表現主義、ロマン主義が溢れています。コハンスキとともに新しい音楽言語を構築しようと企て、二人の専門楽器であるヴァイオリンとピアノの響きの可能性を引き伸ばそうとしました。シマノフスキのヴァイオリンとピアノのための作品は、互いに影響を与え合うコハンスキとのパートナーシップに恩恵を受け、空想に満ちた特別な音楽的効果を生み出すのに成功しました。官能的で華やかさが徐々に高まりを見せるようなメロディーが印象的です。
シマノフスキの民族主義と彼がギリシャ神話や東洋の古代文学に魅力を感じていたことを考えると、『夜想曲とタランテラ』のスペイン風の曲想は、彼の作品の中では異色であると言えます。おそらく、コハンスキと親しかったマニュエル・デ・ファリャの音楽の影響を受けたのでしょう。ファリャは1914年に『スペイン民謡組曲』を作曲し、コハンスキの妻に献呈しています。
『夜想曲とタランテラ』を作曲した頃は、作曲家として最も脂の乗っていた時期でした。第一次世界大戦の勃発で、公に演奏活動がほとんどできなかったので、シマノフスキはウクライナにある別荘に閉じこもり、文学の研究と作曲に没頭しました。また、この時期は、『ヴァイオリン協奏曲第1番』やギリシャ神話を基にしたヴァイオリンとピアノのための『3つの神話』が生まれた頃でもありました。
『夜想曲とタランテラ』は、ヴァイオリンがミュートを装着し、神秘的に、魂を奪われたかのように、不安な雰囲気が漂う中、煙が渦巻くように、静かに始まります。すぐにスペイン的なリズムが夢のような静寂を打ち破り、夜にきらめく輝きを与えます。それに続くタランテラでは、歯切れのよいアーティキュレーションやリズムが特徴的です。勢いは止まらず、お祭りの踊りを髣髴させるところがあります。それにもかかわらず、陽気であでやかなムードの中で、優雅さが消えることはありません。
2005年2月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第2番イ短調 D.385 Op.posth.137-2
フランツ・シューベルト
(1797年オーストリア/ウィーン生まれ;1828年同地にて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第2番イ短調 D.385 Op.posth. 137-2 (1816年作曲)
フランツ・シューベルトは、古典-ロマン派時代の最も愛される最高の作曲家の一人ですが、一部の熱心な支持者を除いては殆ど知られることなく31年の短い生涯を送りました。早過ぎる死にもかかわらず、シューベルトは600以上の歌曲(歌曲のジャンルでは革命的)、7つの交響曲と、15の弦楽四重奏曲の他に八重奏、弦楽五重奏ハ長調、ピアノ五重奏『鱒』も含む様々な室内楽曲を残しました。
相対的に見ると、シューベルトがヴァイオリンのために書いた曲は彼の作品群の中でもヴァイオリニストのレパートリーとしても中核を成すものではありません。しかしながら、この評価は作品そのものの作曲技法や芸術的価値を反映したものと考えられるべきはなく、ソロ楽器とオーケストラのための曲は数曲書いたものの協奏曲を作曲しなかったことにも一因があるようです。室内楽曲の中でも特に二重奏曲では、2つの楽器のコントラスト、対立、過剰な競い合いなどよりも、むしろアンサンブルの究極の形を探求しているようで、楽器の組み合わせによる理想の作曲方法を反映した彼独自の視点が、自然と大規模な協奏曲の作曲から遠ざけていたのかもしれません。
シューベルトが残したヴァイオリンのための作品には3つの“ソナタ”がありますが、最初からアマチュアにも演奏してもらいやすくするために“ソナチネ”として、死後に出版されました。それが今となっては“ソナチネ”という名前から重要度の低い作品という印象を与えるのか、過小評価や演奏の機会が少ないことにつながっていると考えられます。シューベルトのヴァイオリン作品には、他にも『幻想曲 ハ長調D.934』や『二重奏曲イ長調D.574』、『華麗なロンド D.895』、『ヴァイオリンとオーケストラのためのロンド』があります。3曲のソナチネは交響曲第4番と第5番を書いていた同時期の1816年に書かれました。これらの作品を書いたのはシューベルトがまだ19歳のときですからとても円熟期に到達したとはいえない年齢です。しかし、これらのソナチネには熟達と自信に満ち、確かな楽器の知識と生き生きとした独創性に溢れたシューベルトの天賦の才が感じられます。
『ソナチネ イ短調 D.385』は、3つのソナタの2番目に作曲されたもので、楽章ごとに雰囲気が大いに異なる4楽章で構成されています。冒頭は内向的で物憂げに歌っているかのようなピアノのソロで始まります。ヴァイオリンはどちらかというとドラマティックに登場し、すばやく陽気で純粋なハ長調の第2テーマに移り、変則的にヘ長調に変わり、提示部の終わりにこの曲の調であるイ短調の属音の和音に戻ります。ある調性から別の2つの調性へ移行するのはクラシック音楽のソナタにおいてはかなり珍しいことです。そして、慣習にとらわれない主音の調から始まる速い展開のセクションの後、再現部は他の調であるニ短調で、へ長調で第2主題が再現され、イ短調に戻って終わります。このように調と和声が一つの楽章の中で進行するという独特の性質は、単純に作曲技術の巧みさというよりは、むしろ、シューベルトの大胆な実験であり、自信であり、冒険の表れで、演奏者と聴衆の心をしっかりとつかみ、ひきつける能力があることを示しています。現代音楽へと前進させるのはこういう大胆な表現なのです。
第1楽章で使われた調性は、曲全体から見て、より力強くまとまっている中間の2つ楽章を導いています。ヘ長調のアンダンテのゆっくりな楽章は、シューベルトが生まれた年の1797年に作曲されたハイドンの『弦楽四重奏曲Op.76-3「皇帝」』の緩徐楽章を連想させます。気品のある堂々とした、シンプルで大胆なこの楽章は再び聴衆を違う雰囲気の世界に連れていきます。続くメヌエットとトリオはニ短調で、自信に満ち、少し自由奔放なところもありますが、可愛らしさやユーモアがないわけではありません。最終楽章では、シューベルトは静けさを保ちながらもドラマティックな様相を呈しています。ロンド形式で書かれ、ロンドの主題自体は憂いを帯び、主題の再現部分の間に提示されている素材は対照的な性質で、陽気なものもあれば暗く不吉な雰囲気を帯びたものもあります。ロンドの主題の最後の提示部分はすぐに転調され、ハッピーエンドを予測する聴衆の期待を無視して、感情的に人々の心を掴む2つの劇的な和音が出てくるまで、冒頭のテーマの重々しさが続きます。
現在使われている「原典版」(可能な限り作曲家の意図を再現することを目的とした楽譜)は資料の組み合わせに基づいています。第3楽章と最終楽章の自筆楽譜は殆ど現存しておらず、原典版は、死後の1836年にディアベリ(Diabelli)によって出版された初版に基づいています。
2016年10月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2016 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのロンド ロ短調 Op.70 D.895
フランツ・シューベルト
(1797年オーストリア/ウィーン生まれ;1828年同地にて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのロンド ロ短調 Op.70 D.895 (1826年作曲)
フランツ・シューベルトは詩的なメロディーを残した最高の作曲家で、シンプルさと甘美さを合わせもち、感情的に強く引き付けられる独特な作風で知られています。しかし、音楽が表面上シンプルだからといって、シューベルトの作品に要求される超絶技巧を無視することはできません。とりわけ器楽曲に顕著であり、あたかもヴァイオリン奏者や器楽奏者に特殊な指使いや多くの高度な技術に挑戦することを課しているかに見えるほどです。
このロ短調の『ロンド・ブリランテ』では、歌うような旋律と自然な輝きにシューベルトらしさがよく出ています。晩年(死の2年前)の1826年に、チェコのヴァイオリニストで第2のパガニーニと呼ばれたヨセフ・スラヴィーク(Josef Slavik)のために書かれた、たった約15分の曲中に、麗しさ、感情の高ぶり、陶酔、ドラマが感じられ、多様な個性やユーモアさえも窺える、多彩な雰囲気をもった曲です。シューベルトの本領ともいえる洗練された優美が最大限この曲では表現されています。
この作品は、冒頭のアンダンテとその後の長いロンドの2つの主要セクションに分かれます。ドラマティックなオープニングから盛り上がるコーダまで、ヴァイオリンとピアノはいつも完璧に補足しあう関係にあります。どちらかが短いフレーズを演奏しているときは、パートナーは流れ出るメロディーを、どちらかが揺れ動くメロディーを奏でるときは、もう一方は高く舞い上がり、その上に浮かんでいるかのようです。
アンダンテからロンドに進んでいく過程でも、それぞれのセクション中でも、勢いは常に継続し、移行はスムーズに行われ、機知に富んでいます。アンダンテで示される楽想は、さらに発展して、ロンドで磨きがかかり、この作品を包括的でまとまりのあるものにしています。同時に、意外な転換がちりばめられており、最後まで飽きることはありません。しかしながら、この作品の一番の特色は、最も激しい瞬間でさえも音楽が停滞することなく流れ続ける点にあり、ロ短調の悲劇的で絶望的なオープニングとは対照的に、喜びや幸せに満ちた華麗なロ長調に突入していく、フィナーレで、とりわけはっきりと感じ取ることができます。
2013年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2013 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シューベルト:ピアノとヴァイオリンのための幻想曲 ハ長調 D.934 Op.posth.159
フランツ・シューベルト
(1797年オーストリア/ウィーン生まれ;1828年同地にて死去)
ピアノとヴァイオリンのための幻想曲 ハ長調 D.934 Op.posth.159(1827年作曲)
『幻想曲 ハ長調 D.934』はシューベルトが31歳で亡くなるほぼ1年前の1827年12月に短期間で書き上げた作品で、『二重奏曲 イ長調 D.574』(1817年作曲)や『華麗なロンド D.895』(1826年作曲)に並ぶヴァイオリンとピアノの2つの楽器のために書かれた傑作です。他にも美しく魅力的な『ソナチネ』(1816年作曲)という愛らしい作品もあります。
『幻想曲』は、シューベルトの歌曲『挨拶を送ろう(Sei mir gegrüsst)』の旋律による変奏曲を中核に複数の楽章で構成されています。『挨拶を送ろう』は1822年にドイツの詩人フリードリヒ・リュッケルト(Friedrich Rückert)の詩にメロディーをつけたものです。彼自身の歌曲からメロディーを引用するのは珍しいことではなく、ピアノ五重奏曲『鱒』(1819年作曲)や弦楽四重奏曲『死と乙女』(1824年作曲)などの有名な作品も歌曲の旋律を転用しています。
カール・マリア・フォン・ボックレット(Carl Maria von Bocklet)のピアノ、ジョセフ・スラヴィック(Josef Slavik)のヴァイオリンで、1828年1月にウィーンで行われた初演の評判はよくありませんでしたが、今やこの『幻想曲』は古典時代から現代に伝わるヴァイオリンとピアノのための最も美しい作品の一つと数えられています。「幻想曲」というと形式にとらわれない自由な楽曲という意味合いもありますが、シューベルトはトラディショナルな4楽章(または3楽章)のソナタの構造を保ちながら、『さすらい人幻想曲(Wanderer Fantasy)』(1822年作曲のピアノ独奏曲、ボックレットによって初演)で楽章の切れ目なく演奏する自由なスタイルに至りました。今回演奏する約27分の2つの楽器のための幻想曲も同様で、さらにテーマを反芻する要素を加えることによって伝統からの離脱を図りました。
この作品は静かなトレモロに似たピアノで始まり、その上にヴァイオリンが優しくメロディーを奏でます。イントロダクションのセクションはメロディアスで、まるで暁に夢から覚めるような不思議な雰囲気に包まれます。続く速い動きの“楽章”では、2つの楽器が時には旋律を主導しあい、時にはダンスのパートナーのように寄り添い、輝きを放ちながら変奏曲を展開していきます。
潮騒に翻弄されるが如く、あらゆる感情が止まることのない速いパッセージに投影されています。突如静寂が現れ、『挨拶を送ろう』のテーマと変奏曲が再現されます。変奏曲は冒頭の旋律へと戻り、再び不思議な感覚が蘇りますが、幻想は一瞬で確信へと変わり、雄大なセクションへと盛り上がり、情熱的な力強いクライマックスを迎えます。
『挨拶を送ろう(Sei mir gegrüsst)』より
2016年5月 五嶋みどり
(編・訳:オフィスGOTO)
Notes © 2016 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シューマン:ヴァイオリン・ソナタ イ短調 Op.105
ロベルト・シューマン
(1810年ドイツ/ツヴィッカウ生まれ;1856年ドイツ/ボンにて死去)
ヴァイオリン・ソナタ イ短調 Op. 105(1851年作曲)
第1楽章:Mit leidenschaftlichem Ausdruck(情熱的な表現で)
第2楽章:Allegretto(快活に)
第3楽章:Lebhaft(生き生きと)
シューマンは、メンデルスゾーンのことを“我々の中に存在する神”と称え、またブラームスのことを“天才”と呼びました。シューマンは、仲間の作曲家や、同時代あるいは過去の偉大な作曲家を尊敬していただけでなく、優れた音楽に対しても深い敬愛の念を示しました。
シューマンは成人してからずっと精神障害で苦しみました。彼がヴァイオリンのためのすばらしい作品を5曲完成させたのは、彼の創作活動の最後の時期でした。イ短調Op.105とニ短調Op.121の2つのソナタは1851年に作曲されました。3つ目のイ短調のソナタ(ディートリッヒとブラームスとの合作である「F.A.E.」ソナタの第2、第4楽章に、新たに2つの楽章を加えたもの)、ヴァイオリンとオーケストラのための幻想曲Op. 131、そして、ヴァイオリン・コンチェルトは、全て1853年に書かれました。その翌年、彼は精神病院に収容され、そのまま2年後に亡くなっています。
ソナタ イ短調Op. 105は、1850年からオーケストラとコーラスの音楽監督として職を得ていたデュッセルドルフで作曲されました。この作品に限らず全ての作品には、彼の心の動きが克明に写しだされており、自分自身の心理状態を鋭く分析した跡が見られ、厳しい自己反省の結果生じる不安が常に感じられます。シューマンの音楽を聴くということは、彼の精神的状況を考慮に入れても、感受性が研ぎ澄まされ、誇張して表現された世界に身を置くようなものです。“ロベルト・シューマン=ロマン派作曲家”と言われるほど、ロマン派を象徴しています。
この作品を作曲した前後から、ますます精神障害が彼を支配するようになっていました。驚くほど気分のむらが激しくなり、彼自身ばかりでなく、家族や友人にも被害は及びました。ある特定のメロディーを書くように天からお告げがあったとか、悪魔に脅かされているなどと言うようになり、まわりの人を戸惑わせました。単なる幻覚でも、彼にとっては自信を失わせるものであり、数年後には死を招く深刻な問題だったのです。この作品の中でも、悲劇的で、落ち着きがなく、まるで有罪宣告に怯えているような精神的苦痛が曲全体から伝わってきます。苦痛から解放されホッとする場面もありますが、そういう時ですら苦痛の影から完全に逃れることはできません。
第1楽章は、Mit leidenschaftlichem Ausdruck(情熱的な表現で)と表記されており、ヴァイオリンのG線上で弾かれるイ短調の豊かな旋律で始まります。ピアノは16分音符で伴奏をし、表情を付け加えます。ヴァイオリンが旋律を弾き終わらないうちに、6小節目からピアノが同じ旋律を6度上げてニ短調で奏ではじめ、またすぐにヴァイオリンがピアノにとってかわりヘ長調で旋律を奏でます。通常、転調は曲の中間部または展開部で見られることが多いのですが、この楽章では、最初から転調が繰り返され、それが大きな特徴となっています。楽章の終盤では、ヴァイオリンは16分音符を、ピアノはオクターブの旋律をちりばめた連続的な和音を奏で、この楽章は冷酷無情に終わります。
第2楽章は、Intermezzo(インテルメッゾ:中間曲)に相応しいヴァイオリンのへ長調の美しい旋律で始まりますが、この旋律は完結しておらず、短いフォークダンスのような旋律がその後に続きます。美しい旋律とフォークダンスを思わせる旋律との組み合わせは、転調されたり、変形されて、度々現れます。そして、最後にはピアノの柔らかい和音とヴァイオリンの優しいピチカートが楽章を美しく優雅に飾ります。
最終楽章は、Lebhaft(生き生きと)と表記されていますが、16分音符の連続にもかかわらず、全体的に暗い雰囲気が漂っており、精神的抑制の中で、ヴァイオリンとピアノの掛け合いが続きます。およそ5分続くこの楽章のところどころで抑えられた不安が、天国のハミングのようなテーマの暗示によって解放されますが、この平穏は長くは続きません。終盤では、第1楽章のオープニングの旋律の断片が再現され、冒頭の無気味なエコーが聞えてきます。そしてソナタは悲劇的な終焉へ先を急ぐように向かっていきます。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18
リヒャルト・シュトラウス
(1864年ドイツ/ミュンヘン生まれ;1949年ドイツ/ガルミッシュ=パルテンキルヒェンにて死去)
ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18 (1887-1888年作曲)
第1楽章: Allegro, ma non troppo
第2楽章: Improvisation: Andante cantabile
第3楽章: Finale: Andante – Allegro
リヒャルト・シュトラウスは、人生の大部分を活発な音楽制作活動に捧げた人物です。プロのホルン奏者を父にもつシュトラウスは、音楽に囲まれて育ちました。ピアノのレッスンを4歳のときに始め、2年後には作曲を始めていました。そして亡くなる1年前の1948年、健康状態の悪化でやむなく筆を折るまで、作曲活動は続けられました。今日では作曲家として想起されるシュトラウスですが、名高い指揮者でもあり、当時のドイツの作曲家兼指揮者として、グスタフ・マーラーと並び称されました。
シュトラウスは幼少の頃、大変保守的な父親の監督の下、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンやシューベルトといった古典作品について、徹底した教育を受けました。シュトラウスの父親が、当時アバンギャルドで前衛的と考えられていたワーグナーの音楽を嫌悪していたにもかかわらず、後に息子がワーグナーの音楽の強力な支持者・理解者となり、まして1880年代後半に入り、シュトラウスがワーグナーに次いで、最も重要な進歩的ドイツ人作曲家と見なされるようになったのは、大変皮肉なことです。
シュトラウスを神童と呼ぶ人はあまりいませんが、16歳になるまでに、作品は出版・演奏され、その頃のドイツの音楽界では権力のあったハンス・フォン・ビューローに「ブラームス以来の注目株」と呼ばれていたこと、また、後に交響詞やオペラを発表し、交響的な音と形式のコンセプトを再定義するなど、早い時期からその才能は注目されていました。
シュトラウスの『ヴァイオリン・ソナタ』は、20代前半に作曲されました。8歳のときにヴァイオリンを始め、1882年には既に『ヴァイオリン協奏曲』を作曲していたことからも、彼がヴァイオリン音楽に造詣が深く、楽器についても熟知していたことは明白で、ヴァイオリンに超絶技巧を求める室内楽曲が多いのも頷けます。
『ヴァイオリン・ソナタ』は、シュトラウスの最後の“古典的”な作品と見なされています。1890年以前にはあまり多くの室内楽を作曲していませんが、その頃の作品には保守的な父親の影響がまだ残っており、古典的な形式を踏襲しています。
彼の妻となるソプラノ歌手のパウリーネ・デ・アーナとの恋愛中に、この『ヴァイオリン・ソナタ』は作曲されました。若いエネルギーと希望に溢れた作品で、後の作品で顕著となる彼独自の音楽言語が既にこの曲の中には感じられ、特に第2楽章では、熱烈な歌のような旋律が後に作曲される彼の歌曲やオペラを彷彿とさせます。ヴァイオリンとピアノの2つのパートが濃密に書かれ、メロディーラインが交錯する交響的な曲想は、ソナタでありながら、まるで2つの楽器がダブル・コンチェルトを弾いているかのようで、シュトラウスが若い頃に作曲した『チェロ・ソナタ』、『ピアノ・ソナタ』、『ヴァイオリン・ソナタ』の中では、最も成熟した作品であると考えられています。
第1楽章の冒頭は、短く、ファンファーレのようなピアノで始まり、すぐに思慮深い、悲しみに満ちたヴァイオリンの旋律にとってかわられます。しかし、この沈んだ雰囲気は長く続かず、2つの楽器がすぐに高音域へ上り詰めます。第2楽章は、Improvisation(即興的に)と表記されており、シュトラウスはヴァイオリンを歌い手のように扱っています。伝統的なa-b-aの形式で書かれたこの楽章のaの部分は特に甘美です。bの部分は、楽章の中間部で、気まぐれで即興的ですが、絶えず優雅です。この中間部分は、ヴァイオリンにミュート(弱音器)を装着して演奏されます。第3楽章は、平穏でありながらもドラマティックな導入部がすぎると、勇壮で華麗な音楽へと突入していきます。
この作品の特徴として、付点音符と三連音符がミックスされたリズムパターンがあります。第1楽章と第3楽章で、この形が全体的に見られ、繰り返し使われるこのリズムが、3つの楽章を見事にまとまった一つの作品にしています。
シュトラウスの『ヴァイオリン・ソナタ』は、ヴァイオリンのために書かれた作品群の中では、最も完成されている作品とは言われていませんが、昨今の主要なヴァイオリニストたちのレパートリーには欠かせない曲であり、心を打つメロディーは今日の聴衆も魅了してやみません。
2002年/2006年改訂 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シュニトケ:作曲家基本情報
作曲家基本情報:シュニトケ
作曲者名:
アルフレッド・シュニトケ Alfred Schnittke

©Sikorski
有名な引用:
「私が作曲を始めた頃は今と全く違うスタイルで作曲していたが、思えば、私の個性というものが表れていなかった。最近になって過去の音楽の歴史をさかのぼって、それらの様式や(音楽で表された)代表的語彙を引用して作曲しているが、そこに私自身の伝えたいことがはっきりと表現されているのに気づいた」とシュニトケは1988年のインタビューで答えた。続けて「単に折衷主義そのものに価値を求めているというのではない。例えば、バロック音楽の要素にあるあたかも消滅して、再現できないような美しい書法を回想するがごとくに引用しているのです。ですから、そこに悲劇的感情が伴っていると思います。私には、一つの曲の中で、“深刻”と “滑稽”が相反することなく存在し、そのどちらかだけで成り立つことはないのです」(ニューヨークタイムズ訃報欄より)
「本来のあなた自身を追求することがいかに大切か!多くの人は誰にでも巨大な力が潜ん
でいるのを発見せずに死ぬ」(Boosey & Hawkes profile pageより)
生没年月日:
1934年11月24日-1998年8月3日
出生地/没地:
ヴォルガ・ドイツ人自治ソヴィエト社会主義共和国エンゲリス生まれ/ドイツ、ハンブルクにて死去
スタイル:
多様式主義(ポリスタイリズム)、折衷主義
最初に習った楽器など:
声楽(合唱指揮)、 後にピアノ
恩師/影響/出身校:
初期作品にはショスタコーヴィチの影響が色濃く感じられる。
モスクワ音楽院にて、エフゲニー・ゴルベフEvgeny Golubev(作曲)とニコライ・ラコフ
Nikolai Rakov(オーケストレーション)を学ぶ。Josif Ryzhkinに音楽理論の個人レッスンを、Vassily Shaternikovにピアノを習う。 マーラー、アイヴズ、プッスールの影響を受ける。
代表作:
交響曲第1番 (1969–1972年作曲)
合奏協奏曲第1番 (1977年作曲)
弦楽四重奏曲第2番 (1980年作曲)
弦楽四重奏曲第3番 (1983年作曲)
弦楽三重奏曲 (1985年作曲)
バレエ音楽『ペールギュント』(1985–1987年作曲)
交響曲第3番 (1981年作曲)
交響曲第4番 (1984年作曲)
交響曲第5番 (1988年作曲)
ヴィオラ協奏曲 (1985年作曲)
チェロ協奏曲第1番 (1985–1986年作曲)
オペラ『愚者との生活』(1992年作曲)
編集:Andrew Freund
リサーチ・アシスタント:Clara Kim
監修:林田直樹
(2014年9月)
シュニトケ:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番
アルフレッド・シュニトケ
(1934年旧ソヴィエト連邦/エンゲリス生まれ;1998年ドイツ/ハンブルクにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番 (1963年作曲)
第1楽章:Andante
第2楽章:Allegretto
第3楽章:Largo
第4楽章:Allegretto Scherzando-Largo
アルフレッド・シュニトケは1963年に最初のヴァイオリン・ソナタを作曲し、次の年にモスクワで、彼自身がピアノを担当し、この曲を献呈したヴァイオリニストのマルク・ルボツキーとともに初演を行いました。シュニトケは、1960年代は主に室内楽曲を作曲し、ヴァイオリン・パートの傑出している作品が多く残されています。彼は音楽を人生の記録とみなしていたようで、人間の声に近いヴァイオリンの音質は、個人的な感情を表現するのに最適であると考え、好んでヴァイオリンのための曲を書きました。
シュニトケは1934年にエンゲリス(旧ソヴィエト連邦)で、ユダヤ人の父とドイツ人の母の間に生まれました。彼は旧ソヴィエトでドイツ語を日常語として話し、ユダヤ人として育ちましたが、特にユダヤ文化やユダヤ教とはかかわりませんでした。また成長期のある時期をウィーンで過ごしました。シュニトケは、後にロシア市民としてドイツに居を構えて、晩年の20年は洗礼を受けカトリック教徒になりました。複数の文化の影響を受け、どこにも強い帰属意識を感じていなかったであろうと見られるのは、作曲言語が多様式であることからも伺われます。
『ヴァイオリン・コンチェルト第1番』も含めて、シュニトケのヴァイオリンのための作品は、ドミトリ・ショスタコーヴィチの影響を強く受けています。ショスタコーヴィチの『ヴァイオリン・コンチェルト第1番』は1948年に作曲されたものの作曲家自身によってしばらく封印されていましたが、1955年にダヴィト・オイストラフによって初演され、若いシュニトケに強い衝撃を与えました。彼は、ソロのヴァイオリンとオーケストラとの衝突や、楽器や楽章によって劇的に異なる雰囲気をもつショスタコーヴィチのヴァイオリン・コンチェルトを高く評価しました。
シュニトケの『ヴァイオリン・ソナタ第1番』は、12音音階で書かれています。冒頭はヴァイオリンのもの悲しい独白で始まります。そして、ピアノがスタッカートで入ってきて、不気味で恐ろしい雰囲気を助長します。この楽章のクライマックスはヴァイオリンがミ♭とドの和音をfffで伸ばすところで、容赦ない厳しさを表現しています。強烈な音量はすぐに和らぎますが、ヴァイオリンのピチカートが不気味な余韻を残してこの楽章は終わります。
第2楽章は、諷刺の利いた皮肉っぽい雰囲気に支配されています。二つの楽器がまるで相手の足にまとわりついているようです。クライマックスに向けて、ピアノパートが静かに、神経質に、この楽章の主題を繰り返し、ついにクライマックスにきたところで、ヴァイオリンが単独で攻め立てるようにカデンツァのような1小節を演奏します。その後、ピアノとヴァイオリンがカノン形式で同じメロディーを独自の速さで奏でます。それぞれの速さが利己的なため、追いかけあっているようでもあり、この点においても2つの楽器が協調しているようには思えません。この楽章には明確な終わりがなく、アタッカ(休みなし)で第3楽章の最初の音(ハ長調の和音)に突入します。
第3楽章は荘厳な雰囲気を持ち、このソナタの中では最も旋律の美しい楽章です。シュニトケはこの楽章で偉大なる作曲家バッハに敬意を表していると言われています。バッハ(BACH)の綴りをドイツ式の音名として解釈し、音に直すと「シ♭-ラ-ド-シ♮」となります(参考1)。ヴァイオリンがソの音(ヴァイオリンで演奏可能な一番低い音)を伸ばしている間、ピアノは4つの和音を奏でますが(参考2)、ピアノの右手の高音部は「B-A-C-H」の音を2度(一音分)上げた音「ド-シ-レ-ド#」の音(参考3)を奏でます。ヴァイオリンが短いソの音を繰り返した後でメロディーを弾くところでは、シュニトケはビブラートをかけないように要求しています。単純なメロディーをビブラートなしに演奏することで、この楽章の性格が際立たされます。また、この楽章の最後は、バロック・フルートの音を模したようなハーモニクスが連続的に用いられ、この楽章を支配する超現実的な雰囲気に拍車をかけます。この楽章も終わりらしからぬ終わり方をします。
(参考1)

(参考2)

(参考3)

最終楽章は、2つの楽器が第2、第3楽章を客観的に分析し、お互いを真似し合い、からかっているようです。終焉に向かうと、この曲の最初のテーマがピアノをバックにヴァイオリンによって再現され、ピアノの4つの和音へと続きます。この和音の右手の高音部は、第3楽章の和音と同じように、「B-A-C-H」の綴りを発端とする「BACHメロディー」とも言えるような音列を奏でます。そして、ヴァイオリンは最終楽章の最初のテーマからの断片をピチカートで3回演奏して、この曲は終わりますが、不気味な継続感があとに残ります。
2002年12月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シュニトケ:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番
アルフレッド・シュニトケ
(1934年旧ソヴィエト連邦/エンゲリス生まれ;1998年ドイツ/ハンブルクにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番(1994年作曲)
第1楽章:Andante
第2楽章:Allegro molto
第3楽章:Adagio
第4楽章:Senza tempo
ヴァイオリンの音色が人の声に近いと感じていたシュニトケは、ヴァイオリンという楽器に特別な親近感を抱いていました。生涯を通じて、3つのソナタ、4つの協奏曲、ヴァイオリンが主役のコンチェルト・グロッソ(合奏協奏曲)、独奏作品や小品など、数多くのヴァイオリンのための曲を残しました。ユダヤ人の父とドイツ人の母の間に生まれたシュニトケはロシア市民としてドイツに住んでいましたが、カトリックの洗礼を受けました。彼の作風は、新旧様々な音楽形式を1つの作品中に巧みに取り入れることから、「多様式主義」と形容されています。「多様式主義」と聞くと、作曲家としてのシュニトケのアイデンティティが無いように思われがちですが、全くそのようなことはありません。彼の音楽は皮肉っぽく、シンプルだけれどもドラマティックで、情緒的な魅力のある表現が入り交じっていることが特徴的で、どの作品にも彼の個性が感じられます。
シュニトケは、多様な文化や芸術の影響を受けた独自の作曲法を用い、探求すべき新しい何かを聴衆と演奏家へ示唆しています。しかしながら、彼は同時に「古典主義者」とも形容されています。シュニトケは少年時代を過ごしたウィーンで音楽教育の手ほどきを受け、チャイコフスキーやラフマニノフといったロシア・ロマン派より、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトのようなドイツの巨匠たちに心酔していました。ショスタコーヴィチからは、特にソ連の現代作曲家がどのように音楽の歴史と、シュニトケの熟達した音楽観は独自の複雑な世俗的感覚を反映しています。
1953年に作曲されたヴァイオリン独奏のための『フーガ(Fuga)』は初期に出版されたシュニトケの作品の一つでしたが、ヴァイオリンとピアノのための『ソナタ第3番』は晩年に書かれた作品の一つです。この最後のソナタは、教会のソナタ(sonata da chiesa)として1994年に作曲されたもので、『ソナタ第1番』同様、バロックや古典の慣習を踏襲した緩急緩急の4楽章の形式で書かれています。他の作品からの引用はなく、その音楽観はシュニトケ独自のものです。時にシンプルですが、もちろん彼の音楽は簡単に聴けるようなものでは決してありません。理解するのが容易ではないユーモアが染み付いたシニシズム、不安、情熱、暗いノスタルジアが共存しています。
シュニトケの晩年は度重なる致命的な脳卒中の発作により、部分的に麻痺が残るなど、厳しいものでした。作曲作業は困難を極め、その結果、このソナタの楽譜は少しずつ書き留められていきました。あまりにも指示表記がまばらで、解釈の余地に幅があり、演奏家自身のシュニトケの作風の知識に委ねられるところがあります。音域が上下に飛んでいるように聴こえますが、音そのものは音階を前後しながら順にたどる、実にシンプルな構成となっています。
第1楽章:ピアノが不協和音を奏でる中、ヴァイオリンはスピードを増しながら上昇型の音列を演奏し、緊張感が高まります。四分音が耳障りな不協和音を作り出し、グリッサンドの使用によりそれぞれの音が「伸ばされたように」聴こえ、極限に達するような印象を与え、更に激しさを増していきます。
第2楽章:たちの悪いいたずらが無邪気さによって救われるような、全体的にプロコフィエフの音楽を髣髴させる楽章です。リズミカルで快活で、かつ溌剌とした曲調はコミカルでもあり、風刺的でもあります。楽章全体はアーティキュレーションがはっきりとした短い音符で構成されています。
第3楽章:この作品の中で最も陰鬱かつロマンティックな楽章で、2つの楽器が対話をしているという感覚が、非常に強く感じられるセクションです。楽章を通して、静かな情熱が描かれており、そこに内在するノスタルジアは決して甘いものばかりではないことを思わせます。
第4楽章:「センツァ・テンポ」(Senza tempo一定の速度なしに)と表記されたこの楽章には、厳密に定められたテンポというものがなく、さまようような感覚が、静かな緊張感を生み出しています。楽章の冒頭は探求的といえますが、エネルギーの爆発が徐々に激しくなり、ノンストップで高音域に達し、クライマックスは容赦なく、断定的です。時間から解き放たれた音楽の非規則性は、聴衆に強い不安と緊張感を残します。
2014年9月 五嶋みどり
(訳・編 佐野浩介)
Notes © 2014 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
シンディング:古い様式で書かれた組曲イ短調 Op.10
クリスチャン・シンディング
(1856年ノルウェー/コングスベルグ生まれ、1941年ノルウェー/オスロにて死去)
古い様式で書かれた組曲イ短調Op. 10 (1889年作曲)
第1楽章:Presto(速く)
第2楽章:Adagio(遅く)
第3楽章:Tempo giusto(適宜なテンポで)
クリスチャン・シンディングは、ノルウェーの生んだグリーグに続く秀でた重要な作曲家で、グリーグ、ヨハン・スヴェンセンと共にノルウェー音楽の黄金時代の偉大なる作曲家の一人と考えられています。ヴァイオリンを学んでいたシンディングは、ライプツィヒ音楽院の学生だった頃、初めて真剣に作曲に取り組みはじめました。ライプツィヒ音楽院は1843年にフェリックス・メンデルスゾーンによって設立され、メンデルスゾーン、シューマン、マックス・レーガー、グリーグ、フェルディナント・ダヴィット等の著名な音楽家が教授として教えたり、指導を受けたりした由緒正しい音楽院でした。
シンディングは後期ロマン派の作曲家に属し、生存中は大変著名で、尊敬されており、作品も評価されていました。1941年の彼の死とともにその評価が急激に下がったのは、反ロマン主義の影響が強くなってきたことに加え、彼は“時の人”でありながら、生前に歴とした独自の新しいスタイルを確立していなかったからではないかと思われます。
1889年に作曲されたヴァイオリンのための『古い様式で書かれた組曲』と1896年に作曲されたピアノ曲の『春のささやき』以外の作品は、最近ではほとんど忘れ去られています。『古い様式で書かれた組曲』が、今日でも繰り返し演奏され、広く親しまれているのは、ヴァイオリンの巨匠ヤッシャ・ハイフェッツの功績が大きく、彼がレパートリーに取り入れたことによって再び脚光を浴びたからです。
3つの楽章から成り立つこの組曲は、タイトル通り、シンディングが意味するところの“古い様式”、つまりバロック・スタイルで書かれています。第1楽章では、バロック時代の典型的な和声の進行に基づいた絶えまない動きが終始見られますが、彼はこれらの和声の多くをロマン派の音楽的気質を表すかのように装飾しています。この楽章は短く、表情豊かな第2楽章の序奏のような印象を与えます。第2楽章では、優しさと温かさが溢れ出て、ロマン派の気質が一層深みを増します。第3楽章は、踊っているような雰囲気はあるものの、決して陽気で快活な感じはしません。冒頭のメロディーはバロック様式で、すぐにロマン派的なメロディーが現れます。また、この楽章には、バロック時代の作曲法に基づく複雑なカデンツァがあります。最後はイ長調の分散和音を駆け上がって終ります。それまで短調であったのが、作品の最後の最後を長調で締めくくる方法は、バロック時代の典型的な作曲法の一つです。
2003年11月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ダヴィドフスキー:作曲家基本情報
作曲家基本情報:ダヴィドフスキー
作曲者名:マリオ・ダヴィドフスキー Mario Davidovsky
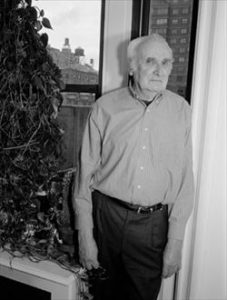
©Thomas Roma
有名な引用:
「シンクロニズムスの主要なアイディアのひとつに、アコースティック(楽器本来の音)とその対照的な電子音を、単一の論理的にも美学的にもかなった空間に埋め込む方法を探究することがある」
生年月日:
1934年3月4日
出生地/居住地:
アルゼンチン、メダノス/アメリカ、ニューヨーク在住
スタイル:
特になし(電子音楽の影響あり)
最初に習った楽器:
ヴァイオリン
恩師/影響:
ギジェルモ・グラエツェルGuillermo Graetzer
ミルトン・バビットMilton Babbitt
代表作:
『シンクロニズムス』シリーズ (1963-2006年作曲)
編集:Andrew Freund
リサーチ・アシスタント:Clara Kim
監修:林田直樹
(2014年9月)
ダヴィドフスキー:シンクロニズムス第9番~ヴァイオリンと電子音のための~
マリオ・ダヴィドフスキー
(1934年アルゼンチン/メダノス生まれ;アメリカ/ニューヨーク在住)
シンクロニズムス第9番 ~ヴァイオリンと電子音のための~(1988年作曲)
マリオ・ダヴィドフスキーは1963年から2006年の間に、『シンクロニズムス』という12曲からなる連作を作曲しました。いずれの作品も、予め録音されたテープ音楽とソロ楽器やアンサンブルの生演奏を「シンクロ」させています。1971年には、『シンクロニズムス第6番 ~ピアノと電子音のための~』で、ピューリッツァー賞音楽部門を受賞しました。
アルゼンチン出身のダヴィドフスキーは、バークシャー音楽センター(現タングルウッド音楽センター)で、作風の異なる2人の作曲家、アーロン・コープランド(Aaron Copland)とミルトン・バビット(Milton Babbitt)から教えを受けるため、1958年にアメリカへ渡りました。2人とも彼の作品を高く評価し、バビットは最先端のコロンビア・プリンストン電子音楽センターのポジションを紹介しました。ダヴィドフスキーはそのセンター長を1981年から1993年まで勤め、シンクロニズムスの「電子音」はまさにこの電子音楽研究ラボで録音されました。彼は1974年までにシンクロニズムス全曲のうち8曲を書き上げ、その後10年以上も電子音楽から離れて伝統的な器楽曲を作曲していましたが、1988年にヴァイオリンと電子音のための『シンクロニズムス第9番』を作曲し、“電子音響”の作品に戻りました。しかし、この40年間で電子音を使用したのは、シンクロニズムスの最後の4曲だけです。
演奏家が聴衆の目の前で実際に演奏する楽器の生音と、コンピューターやテープで再生される電子音の2つの異なる音の感覚を同時に存在させるというシンクロニズムスに見られる画期的な手法は、歴史的にも極めて重要な意味をもっています。ダヴィドフスキーの才能は、生音とテープ音楽を油断のならない強制的なやり方でフィットさせながら、両方を自然に作曲するところで、常にどちらかというと離れた存在に思える音を融合しようとしています。彼の作品はどれも非常に上品かつ誠実で、使用する楽器の基本的特徴や機能が尊重されていると思います。
『シンクロニズムス第9番』は、ヴァイオリン(ダヴィドフスキーが幼い頃に習っていた楽器)と電子音のためのデュオ作品で、他のシンクロニズムス作品と同様に、伝統的な音楽様式からの逸脱ではなく、クラシック音楽における最新のトレンドのように聴こえる音作りに成功したと言えます。この曲が実際のところ、どの程度“普通”の音楽なのか、と興味を持たれる方もいるかもしれません。彼のレトリック(作曲法)は確かに現代的ですが、実際にやっていることは他の作曲家と変わりなく、耳慣れない音が詰まったショーケースを用意するだけでなく、それらを用いて筋道の通った音楽の物語を紡ぎだしています。(そう考えてみると、タイトルの『シンクロニズムス第9番』という複数形は誤った名称かもしれません。というのも、この作品は複数のジェスチャーの集合体ではなく、「シンクロニズム」が拡張されたような、1つの全体的な作品であるからです。)ヴァイオリンと電子音が優雅に絡み合う、悲しげで繊細な、入念に手をかけられた素晴らしい作品です。
ダヴィドフスキーの作品を解釈するという挑戦は、いかに楽器とテープ音楽のアンサンブルを確立させていくか、というところにあります。機械であるテープと“対話”する演奏家というと矛盾しているように思えるかもしれませんが、電子音は一種の楽器以外の何ものでもありません。双方のパートはそれぞれが入り交じり、相互に影響するように作曲されています。ところが、現実的にはテープ音楽は、一旦スタートしてしまうと、何も変えることはできませんし、調整も不可能です。しかし、テープ音楽に反応するように楽器パートを演奏すると、非常に協力的な意識が働きます。(これこそが重要で、テープ音に反応するように演奏するのと、テープ音に沿って演奏するのでは大きな違いがあり、単純にテープ音に沿って時間通りに演奏するよりも、テープ音に反応して演奏する方が、より高度なスキルと柔軟性、そして自信も必要になります。)
2014年9月 五嶋みどり
(訳・編:佐野浩介)
Notes © 2014 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ダニエルプール:バージャンタンに日が暮れて
リチャード・ダニエルプール
(1956年アメリカ/ニューヨーク市生まれ・在住)
バージャンタンに日が暮れて(As Night Falls on Barjeantane)(2001年作曲)
リチャード・ダニエルプールは同世代のアメリカ人作曲家の中で最も成功を収めている作曲家の一人です。彼の作品は、色彩豊かで、音の強弱の幅も広く、大胆なロマン主義的な手法も見られます。特に、彼の抒情的な作風は神秘主義によって引き立てられ、聴衆を平穏の世界、激情の世界、魅惑の世界へと引き込んでいきます。
ダニエルプールは、ヴァイオリンのための曲をいくつか作曲しています。ヴァイオリンとオーケストラのためのコンチェルトである『A Fool’s Paradise(愚か者の天国)』(2000年作曲)、ヴァイオリンとチェロとオーケストラのためのダブルコンチェルト『In the Arms of the Beloved(愛する者の腕の中で)』(2001年作曲)、そして同じく2001年に作曲された『As Night Falls on Barjeantane(バージャンタンに日が暮れて)』です。
ダニエルプールは2001年の初夏を南フランスにあるヴィルクローズ(Villecroze)という中世の村で過ごしました。そこで彼はデ・トレイユ財団(Fondation des Treilles)の音楽 部門であるヴィルクローズ音楽院(Academie musicale de Villecroze)でマスタークラスを開いていました。プロヴァンスのアルプスとコートダジュールの素晴らしい景色が広がる風光明媚なところに、選抜された若いプロの音楽家が集まり、11日間徹底的に勉強します。ダニエルプールのような優れた教師陣と直接交流しながら集中的に学ぶことができ、芸術的なインスピレーションを得るには理想の場所です。
バージャンタンは、音楽院にある家の名前です。ダニエルプール自身の言葉を借りると、「南フランスのたそがれ時から暗くなるときが特に夏は長くて美しい。この作品は、このような美しい場所と時間帯に喚起され生まれたものである。」
『バージャンタンに日が暮れて』は、インディアナポリス国際ヴァイオリン・コンクールから委託された作品で、2002年のセミ・ファイナルに選出されたコンクール参加者によって演奏されました。この作品を献呈されたのは、デ・トレイユ財団の理事長でヴィルクローズ音楽院の学長であるアン・ポステル=ヴィネイ(Ann Postel-Vinay)で、彼女は1989年に設立されたこの2つの組織の創設者であるA.G.シュルムベルガー(Anne Gruner Schulumberge)の孫娘です。
『バージャンタンに日が暮れて』はダニエルプールのヴァイオリンとピアノのために作られた唯一の曲で、短く劇的なピアノの序奏で始まります。この曲に求められるかすかに光るような音質は、ヴァイオリン特有の音質にぴったりと合っています。ヴァイオリンの気品ある出だしの後で、ピアノがオクターブでメロディーを奏でます。ヴァイオリンのテーマは、終始、シンプルで、遠くから聞こえてくるような、繊細でなおかつ美しい音色で奏でられ、主要なメロディーが何度か繰り返されます。最後は、神秘的に静かに遠くに消え去るように終わります。
2004年1月 五嶋みどり
(訳・編:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
チャイコフスキー:ワルツ=スケルツォ Op.34
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
(1840年ロシア/カムスコ=ヴォトキンスク生まれ;1893年ロシア/サンクトペテルブルグにて死去)
ワルツ=スケルツォ Op. 34(1877年作曲)
『ワルツ=スケルツォ』は、軽快で優雅な曲です。もともとヴァイオリンとオーケストラのために書かれたこの曲は、チャイコフスキーのバレエ音楽の中に出てくるワルツの特徴をよく表しています。流れるようなメロディーは、卓越した技巧を要しますが、その難しさを感じさせることなく、洗練された華麗な雰囲気だけが漂っています。不幸な結婚で深く傷ついたチャイコフスキーの私生活とは裏腹に、『ワルツ=スケルツォ』は陽気で活気に満ち溢れた曲です。
この作品は、すぐ後に書かれた有名なヴァイオリン協奏曲にも影響を与えたヨーシフ・コーテク(Yoshif Kotek)に献呈されました。チャイコフスキーの他の器楽曲でも見られるように、『ワルツ=スケルツォ』は3つの部分とカデンツァから成り立っており(A-B-カデンツァ-A)、演奏者に高度な技術が要求される曲です。機敏さと滑らかさが求められるだけではなく、3拍子のワルツ特有の弾むような軽さと同時に冷静さも要求されます。ヴァイオリン・パートのダブル・ストップ(重音)は、単一のメロディーラインに複声を加え、威風堂々とした19世紀のコスモポリタン気質を効果的に示しています。難しい技巧を必要とするカデンツァは大胆奔放であり、気まぐれです。
2005年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
チャイコフスキー:メロディ 変ホ長調 Op.42-3
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
(1840年ロシア/カムスコ=ヴォトキンスク生まれ;1893年ロシア/サンクトペテルブルグにて死去)
メロディ 変ホ長調 Op. 42-3(『懐かしい土地の思い出』より)(1878年作曲)
チャイコフスキーはメロディ作りの達人で、彼の作品は、湧き出る音楽の泉から自然に流れ出てきたかのようです。彼の作風には自己陶酔と独特の甘さが感じられるものの、ロマン主義の影響が力強く表れています。彼の音楽は情熱的でありながらも気品が漂い、哀楽に関係なく、心に深く残ります。
早熟であったチャイコフスキーの芸術的な才能に、両親は早くから気づき、5歳からピアノを習わせましたが、息子を音楽家にする意志はなく、10歳でサンクトペテルブルグにあった法律学校に寄宿生として入学させました。チャイコフスキーは21歳で本格的に音楽の勉強をするようになるまで、法律を学び、法務省に勤務していました。
彼が作り出す美しい音楽とは対照的に、チャイコフスキーの人生には困難や不幸な事件も多かったようです。1877年は特に悲惨な年で、アントニーナ・ミリュコーヴァと結婚しましたが、数週間で失敗し、自殺未遂を図り、精神衰弱を患い、医師からは回復のために全く違う環境に身を置くように忠告されました。
チャイコフスキーは、この不幸な結婚をする少し前から、富豪のナジェジダ・フォン・メック未亡人との文通を始め、二人が生涯会わないことを条件に援助を受けるようになっていました。フォン・メック夫人は彼女の領地の一つであるブライロフでの療養をチャイコフスキーに勧めました。ブライノフには主のフォン・メック夫人はいませんでしたが、森や美しい庭に囲まれた豪華な家には、楽譜や楽器が揃っており、チャイコフスキーは快適な生活を送ることができました。
『懐かしい土地の思い出』は、チャイコフスキーが1878年にブライロフを去るときに、感謝の気持ちとしてフォン・メック夫人に渡してくれるように、夫人の使用人に預けたものです。この作品は、『瞑想曲』(ヴァイオリン協奏曲の第2楽章用に書かれながらも結局使われず単独曲として再利用されたもの)、『スケルツォ』、『メロディ』というヴァイオリンとピアノのために書かれた3曲の小品で構成されています。アレクサンドル・グラズノフ(1865-1936)が後にヴァイオリンとオーケストラ用に編曲しています。
『メロディ』は単独で演奏される機会も多く、チャイコフスキーの心の平静とノスタルジアが伝わってくるような甘美で魅力的な短い曲です。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ドヴォルザーク:マズルカ Op.49 B.89
アントニン・ドヴォルザーク
(1841年ボヘミア(チェコ)/ネラホゼヴェス生まれ;1904年チェコ/プラハにて死去)
マズルカOp.49 B.89 (1879年作曲)
マズルカはポーランドの民族舞踏に起源を発する音楽スタイルで、フレデリック・ショパンがピアノのための50のマズルカを作曲し、成功を収めたことで、器楽曲の人気のある形式の一つとなりました。ドヴォルザークをはじめとする多くの作曲家が、瞬く間に評判となり称賛されたショパンのマズルカに追随して作曲しました。
ドヴォルザークの『マズルカ』は1879年に作曲され、ヴァイオリニストの巨匠パブロ・デ・サラサーテに献呈されました。ヴァイオリンとピアノのための二重奏版とヴァイオリンとオーケストラのための2つの版がありますが、今日では主要なレパートリーとして扱われることはありません。しかしながら、『マズルカ』は、民族的な要素や優雅で美しい旋律といったドヴォルザークの音楽の魅力を余すところなく表現しています。
この作品の質朴な田舎風の曲想は、曲が始まるとすぐに現れ、殆どヴァイオリンの重音で奏でられますが、ピッチの研ぎ澄まされた感覚と機敏な左手の指と力が要求されるので簡単ではありません。この曲全体を通じて最初の主題が断続的に再現される中、旋律的な第2主題が演奏されます。甘美で、無垢で、ついハミングしてしまいそうな、典型的なドヴォルザークの特徴を捉えた感銘的で美しいこの旋律は、舞曲的な部分とは違った魅力と静けさを呈しています。
ノスタルジックであり同時に素朴なこの作品は、伝統的な3拍子で書かれています。ドヴォルザークは、時折、通常の3拍目よりも他の拍を強調することで、心が惹かれる曲にさらに彩りを加えています。
ドヴォルザークは、出版元のジムロック社から、ボヘミアやスラブの旋律に溢れる市場性の高い作品を作曲するようにかなりの圧力を受けていましたが、彼にとっては何の問題もありませんでした。と言うのは、彼は母国、その音楽、人々を愛していたからで、このような圧力の中、今日でも人気のある『スラブ舞曲』や『マズルカ』が作曲されました。これらの作品は、即座に人をひきつける魅力があるからといって芸術性や創造性に欠けるというわけではありません。ドヴォルザークは、民族的、古典的、ロマン主義的要素を大変魅力的に混ぜ合わせ、彼独自の音楽的アイデンティティーを作り出しました。
2005年1月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ドヴォルザーク:4つのロマンティックな小品 Op.75
アントニン・ドヴォルザーク
(1841年ボヘミア(チェコ)、ネラホゼヴェス生まれ、1904年プラハ(チェコ)にて死去)
4つのロマンティックな小品 作品75(1887年作曲)
第1曲 Allegro moderato
第2曲 Allegro maestoso
第3曲 Allegro appassionato
第4曲 Larghetto
アントニン・ドヴォルザークは、1841年にボヘミア(チェコ)のネラホゼヴェスで生まれました。ドヴォルザークの一家には優れたアマチュア音楽家がいたものの、父親は旅館と精肉店を経営しており、長男のドヴォルザークは少年時代から家業を継げるように修行しながら、オルガンやヴァイオリン、ヴィオラ、作曲を学び、後に音楽を専門に学ぶようになるまで、叔父の援助を受けていました。
同郷のヤナーチェクやスメタナも、クラシック音楽界では尊敬されるべき重要な作曲家に数えられていますが、ドヴォルザークは、『交響曲第9番 ホ短調 作品95, B.178「新世界より」』や『スラブ舞曲』、『チェロ協奏曲 ロ短調 作品104, B.191』、『弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 作品96, B.179「アメリカ」』、『ユーモレスク』、『我が母の教え給いし歌』など、誰でも一度は聴いたことのあるような名作を残し、一般の音楽愛好家にも人気の高い、ボヘミア出身の最も愛されている作曲家です。
ドヴォルザークは、多くの作曲家たちと違い、生前から成功を収めていましたが、『4つのロマンティックな小品』が作曲されたのは、3度目のイギリス訪問を終え、国際的な名声を確立した後の1887年のことでした。ドヴォルザークは、義理の母のところに下宿していた若い化学者がその先生と二人でヴァイオリンを演奏するのを聴いて、自分も演奏に参加したいと思い、アマチュア奏者のために、楽しみながら作曲した『2つのヴァイオリンとヴィオラのためのテルツェット』という弦楽三重奏曲がもとになっています。結果的には、この曲はアマチュア奏者には難しすぎたため、ヴァイオリンとピアノのための曲にアレンジされ、独自のアイディアが加えられたのが『4つのロマンティックな小品』です。作曲者自身がピアノを弾き、カレル・オンドジーチェクのヴァイオリンで初演されました。
第1曲はアレグロ・モデラートと表記された短い曲で、ヴァイオリンが抒情的な美しいメロディーを奏で、ピアノ伴奏のリズムパターンが素朴さを出しています。
アレグロ・マエストーゾの「マエストーゾ」という言葉は「荘厳に」という意味ですが、第2曲は、全体的に軽快で気まぐれな雰囲気の曲です。しかしながら、そんな中で冒頭や何度となく使われている重音が荘厳さをかもし出しています。
第3曲は、アレグロ・アパッショナートと表記されている通り、ヴァイオリンが終始情熱的な美しいメロディーを奏でるロマンティックな曲です。
第4曲のラルゲットは、哀愁漂う調べが印象的な、まさに哀歌です。ピアノの繊細なアルペジオの伴奏が哀しみを増長させます。
それぞれの曲が単独で演奏されることもありますが、通常は4つの作品を4楽章に見立て、続けて演奏されます。4つの作品には独自の温かさと抒情的なテーマがあり、牧歌的なメロディーに心が惹かれます。
2007年11月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2007 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ドヴォルザーク:ソナチネ Op.100 B.183
アントニン・ドヴォルザーク
(1841年ボヘミア(チェコ)/ネラホゼヴェス生まれ、1904年チェコ/プラハにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ Op.100 B.183 (1893年作曲)
第1楽章:Allegro risoluto
第2楽章:Larghetto
第3楽章:Scherzo: molto vivace
第4楽章:Allegro
アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)は、ボヘミア(チェコ)出身の作曲家です。同郷のヤナーチェクとスメタナは重要な尊敬されるべき作曲家として、クラシック音楽界では受け入れられていますが、ドヴォルジャークはそれ以上に音楽の専門家にも一般の音楽愛好家にも人気が高く、ボヘミア出身の作曲家の中では最も愛されている作曲家ではないでしょうか。彼の人気の秘密は、大変大衆的な曲をいくつか作曲したところにあります。おそらく彼の魅力は陽気な気質と純真に見えるところにあるのでしょう。
ドヴォルザークの音楽を聴くと、都会の洗練された生活というよりも、土の香りのする田舎の自然を感じることができます。ドヴォルザークは田舎育ちで、田園生活を心底好みました。彼が受け継いでいるボヘミアの伝統は彼の音楽の基盤となっています。
私が最初にドヴォルザークに関心を持ったのは、まだ幼かった頃、黒沼ユリ子さんが子供向けに書かれた伝記を読んだときでした。黒沼さんはプラハに留学経験があり、日本にドヴォルザークの音楽を積極的に広めたヴァイオリニストです。
ドヴォルザークは1841年にボヘミアのネラホゼヴェスで生まれました。ちょうど政治的な民族主義が、文化的にも芸術的にも波及してきた時代で、ドヴォルザークは後に中央ヨーロッパやアメリカで音楽界の民族主義に貢献する重要人物となります。
父親は宿屋と肉屋を経営しており、長男だったドヴォルザークは将来肉屋の免許がとれるように、少年時代から訓練されていました。音楽家の基準からすると、彼が最初に受けた音楽的訓練は乏しいレベルでした。音楽の勉強に集中できるようになるまで、彼は肉屋の見習いとして働いていました。
多くの作曲家たちと違い、ドヴォルザークは生前から成功を収めていました。しかし皮肉にも彼は世界的な名声を得て贅沢な複雑な生活を送るより、質素な生活を求めるような生来の恥ずかしがりやで、勲章を授与されたときも困惑したようです。彼は母国を愛し、彼の音楽からは母国やその人々に対する愛情や愛着が伝わってきます。19世紀半ばという時代は、音楽の分野だけでなく、絵画や文学といったあらゆる芸術的分野の最前線で民族主義がテーマとして現れてきた頃です。この傾向は世界のいろいろな場所で見うけられ、18世紀にアメリカやフランスで起こった革命が影響を与えていると主張している歴史家もいます。
1892年にドヴォルザークは渡米し、ニューヨークのナショナル音楽院の院長に就任しました。のんびりとした母国ボヘミアを後にし、ニューヨークの都会の喧騒に身を移したわけです。もちろんヨーロッパ大陸からの移民はたくさんいましたが、“民族”という感覚や故郷を思わせる田園もありませんでした。
強く母国を愛し続けていたドヴォルザークが、新しい環境に慣れるためどれほどの苦労をしたかは容易に想像できるでしょう。しかし、このアメリカ滞在中に作曲されたのが『チェロ協奏曲』、『ユーモレスク』、『交響曲第9番“新世界より”』といった名作でした。
実質3年間という短い滞在中、信じられないほど充実した創作活動を行ったドヴォルザークですが、それらの曲の一部は、ボヘミアからの移民が入植していたアイオワ州の町で作られました。ドヴォルザークの存在はコープランドやアイヴズといったアメリカの作曲家に多大な影響を与えたと言えます。彼自身はアメリカ先住民の音楽に代表される“アメリカ的”な音にインスピレーションを得て、その重要性や価値を若いアメリカの作曲家に説きました。
ドヴォルザークは弦楽四重奏曲『アメリカ』は特に有名ですが、他にも多くの室内楽を作曲しました。その一つが『ソナチネ Op. 100』で、自分の愛する子供たちに捧げられました。4つの楽章からなるこの作品は、ある一人のボヘミア人がアメリカ滞在中に経験した幸福な生活をよく表現していると思われます。
アレグロ・リゾルートの第1楽章はソナタ形式をとり、ファンファーレによく似た感じで始まります。第2主題は、ト長調の作品にしては、属調であるニ長調ではなく、ホ短調で書かれています。
第2楽章のラルゲットは、ドヴォルザークがミネソタのセント・ポール近くの滝を訪れたときにひらめき、自分のシャツの袖にとりあえずメモしたと言われています。ドヴォルザークの出版社ジムロックは、本人の同意なくこの楽章だけ別にして、いろいろな楽器用にアレンジして、出版しました。ヴァイオリニストのクライスラーは『インディアンの子守唄』という題名をつけてアレンジして、コンサートで演奏し、たちまち話題を呼びました。
第3楽章はスケルツォで、田園風な様子が伝わってきます。モルト・ヴィヴァーチェと記されていますが、興奮した音楽ではなく、むしろ素朴な、威厳と優雅さが漂う楽章です。
最終楽章は、高揚した気持ちが表現されています。しかし、ここでもドヴォルザークの音楽に特徴的な、故郷を思う気持ちが形を変え、見え隠れします。この民族主義は母国を本質的に称えるようなものではなく、母国への愛情がうかがえます。
ソナチネがジムロック社から出版されたとき、ドヴォルザークは「若い人達に(私の子供達に)捧げるが、大人達にも楽しんでもらえるように」と注釈を入れました。この作品は大変短い期間に思いつき、下書きされ、完成されました。滝を訪れたのは1893年の9月で、この曲が完成したのは12月3日。しかも正式にこの曲を手がけ始めたのは11月19日となっています。この曲はニューヨークのアパートで彼の子供のうちの2人によって“特別”に初演が行われました。
円熟した作曲家(このときドヴォルザークは52歳)が作曲したにしては、あまりにも簡単で単純過ぎるという理由で、最近ではこの作品は演奏家から軽く見られる傾向があります。しかし、この曲特有の幸せな子供時代を彷彿させるような純粋な優雅さ、飾り気のないかわいらしさ、無邪気さを十分表現するのは大変難しいことです。ここでドヴォルザークの言葉をもう一つ引用します。「自然と生まれた考えがいかに素晴らしいものであっても、それは私達の功績ではない。しかし、その考えを上手く実現し、そこから何か偉大なものを作りあげることは、最も難しいことであり、それこそが芸術なのである」。
『ソナチネ Op. 100』は、ボヘミアにルーツを持ちながら、アメリカのインスピレーションを得て書かれ、ドヴォルザークの才能によって芸術作品に仕上げられた音楽です。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ドヴォルザーク:我が母の教え給いし歌
アントニン・ドヴォルザーク
(1841年ボヘミア(チェコ)/ネラホゼヴェス生まれ;1904年チェコ/プラハにて死去)
歌曲集『ジプシーの歌』より『我が母の教え給いし歌』(1880年作曲)(フリッツ・クライスラー編曲)
ドヴォルザークは、1880年に7曲からなる歌曲集『ジプシーの歌』の4曲目として、『我が母の教え給いし歌』を書きました。それまでに『スラブ舞曲』(1878年作曲)が大成功を収め、ドヴォルザークは作曲家として名声を獲得しつつありましたが、彼を偉大な作曲家として位置づけるには至っていませんでした。声楽の分野では、歌曲集『糸杉』(1865年作曲)、『夕べの歌』(1876年作曲)、3曲組の『モラビアの二重唱』(1876年-77年作曲)、本格的規模の合唱曲『スターバト・マーテル』(1876-77年作曲)を既に発表していました。
『ジプシーの歌』は、チェコの詩人アドルフ・ヘイドュクがドイツ語で綴った詩にドヴォルザークが曲をつけたもので、ロマの生活をロマンティックに描いています。音楽や歌への愛着に重点を置いた詩で、ドヴォルザークの音楽は温かく、民族的な匂いがします。
『我が母の教え給いし歌』は単独で、最も愛され、よく演奏されるドヴォルザークの作品の一つになりました。素朴で、なんとなくもの悲しく、それでいて漠然と希望がある主旋律の4分の2拍子に対して、伴奏パートは、アルペジオ風の和音が8分の6拍子で演奏されるリズムの重なりが特徴です。後にフリッツ・クライスラーがヴァイオリンとピアノのために編曲し現在まで愛奏されています。
2004年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ドビュッシー:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
クロード・ドビュッシー
(1862年フランス/サン・ジェルマン=アン=レー生まれ;1918年フランス/パリにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ (1916-1917年作曲)
第1楽章:Allegro vivo
第2楽章:Intermède, fantasque et léger
第3楽章:Finale: Très animé
クロード・ドビュッシーが様々な楽器のための6曲のソナタを作曲しようというプロジェクトに着手した1915年には、既に癌に侵されていました。徐々に悪化する健康状態とそれに伴う苦痛にもかかわらず作曲を続けたのは、経済的な理由もあったようです。6曲のソナタのうち、3番目の『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』を作曲した後、残りの3曲のソナタを完成させることなくこの世を去りました。
ラベルには評価され、サン=サーンスには批判されましたが、ドビュッシーはフランス文化を擁護するのに力を尽くした愛国心あふれる音楽家でした。1902年に作曲されたオペラ『ペレアスとメリザンド』は、フランス音楽史上画期的な作品の一つと考えられており、彼の仲間や後世の作曲家に多大な影響を与えました。また、彼のスタイルには、ジャポニズムの影響が垣間見られ、モダンで、控えめなところもあり、感情的な温かみに溢れ、ドビュッシーは印象派音楽を作り上げた重要な作曲者として認知されています。
ドビュッシーのヴァイオリン・ソナタを演奏するときのチャレンジと言えば、感覚や精神のコラボレーションです。ドビュッシー以前の時代に書かれたソナタや同時期でも彼以外の作曲家の手によるソナタとは異なり、彼のソナタは、本質的に2つの楽器がお互いを伴奏しサポートしあうことは殆どありません。また一方が問いかけ、他方が答えるという関係でもなく、むしろお互いの意見を出しあっている感じがあります。あるものに向かって両者が独自の印象や感覚を表現しあい、徐々にその全体像が浮かび上がり、聴いている者にも一つのものとしてとらえられていくようなところが、従来のソナタとは違った響きや雰囲気を生み出しています。
この『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』はドビュッシーが完成した最後の作品となりました。3つの楽章から構成されていますが、まず1916年10月に最終楽章(第3楽章)が作曲され、その4ヶ月後に他の2楽章が完成されました。この作品は、深く物思いにふけったような感じの曲で、幻想、自由、情緒的な深さといったドビュッシーならではの特徴を、極めて簡潔に具体的に表現しています。
第1楽章のAllegro vivo(活発なアレグロ)の冒頭でピアノが奏でる心に響く和音は、聴衆を一瞬である抑圧された雰囲気へと導き、ノスタルジアと物思いの雰囲気に包みこみます。この楽章は、テンポとしてはどちらかというと緩やかなわりに勢いが途切れることはありませんが、全体にリズム的にも和声の進行の上でも不明瞭なところが存在します。それに対して第2楽章は、Fantasque et léger(幻想的と軽やかに)という表記通り、軽快で空想的な楽章です。なまめかしさもわずかながら感じられる気まぐれな部分とメロディアスで感覚的な第2主題とのはっきりとしたコントラストが滑稽さを醸しだしています。
最終楽章のTrès animé(極めて元気に)は、前楽章の第2主題のメロディーで強調されたピアノの速い動きで始まります。続いて、ヴァイオリンが第1楽章の冒頭のノスタルジックなテーマを少しアレンジしたような形で入ってきます。しかしながら、派手に機敏さを見せびらかすようなところが大部分を占め、この楽章を特徴付けています。特に、ドビュッシーは、ヴァイオリンで出せる音の範囲を最大限に使い、開放弦のG(ソ)の音(ヴァイオリンで出る最低音)から、真ん中のC(ド)から3オクターブと半音高いC#(ドのシャープ)まで行ったり来たりします。ピアノにはタッチの軽い雰囲気を出させるためにトレモロのような速度が要求されています。
2004年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ドビュッシー:美しい夕暮れ
クロード・ドビュッシー
(1862年フランス/サン・ジェルマン=アン=レー生まれ;1918年フランス/パリにて死去)
美しい夕暮れ(ハイフェッツ編)
&
ガブリエル・フォーレ
(1845年フランス/パピエ生まれ;1924年フランス/パリにて死去)
3つの歌より『ゆりかご』Op.23-1
フランス芸術歌曲「メロディ」は、主に19世紀に活躍した作曲家のフォーレとドビュッシーによって、当時の高踏派詩人のボードレール、ユーゴ―、ヴェルレーヌなどの詩に曲をつけたという点でドイツにおける「リート」の存在と似ています。「メロディ」は、19世紀半ばのベルリオーズ(1803-1869年)が名づけ、20世紀のプーランク(1899-1963年)の頃にかけて盛んに作られました。
「メロディ」と「リート」は歌詞にあたる詩そのものが文学的に高い評価を得ている点が、それまでの伝統民謡に曲をつけた「ロマンス」と一線を画します。またドイツの「リート」との明確な違いは、数小節ごとに旋律のリピートがなく規則的なリズムに捉われず、フランス語独特の詩と密接に流れる歌詞と韻律が生かされています。哲学的思想や人生観を見事に表現する短い作品「メロディ」は、歌曲のジャンルにおいて重要な部分を占めていると言えるでしょう。
文学的な観点では、フォーレの『ゆりかご』はルネ・フランソワ・シュリ・プリュドムの詩に、ドビュッシーの『美しい夕暮れ』はポール・ブールジェの詩に曲を付けたもので、2つの詩はフランス芸術の移り変わりを反映しています。様式上では同じ「メロディ」に分類されますが、あえていえば、フォーレはロマン派と印象派の過渡期の作曲家であり、ドビュッシーは印象派の作曲家(本人はそのような分類を嫌っていましたが)に分類することは可能です。両曲共に太陽と波について語る作品を同時に取り上げることで、興味深い比較ができるように思います。
『ゆりかご』は、3曲で構成されるフォーレの「Op.23」の中の1曲で、1882年に国民音楽協会(Société Nationale de Musiqu)の演奏会で、ピアニストと歌手によって初演されました。ピアノのアルペジオで穏やかな水面を感じながらゆりかごを揺らす母親のイメージから、歌手は、あやしている子供たちもやがて成長し、注がれた愛情を忘れ、海に出て行ってしまう、という逃れられない女性の性(さが)を表現しています。全体的に絶望感の中でも繊細さやピュアなところに、この曲の魅力があります。
『美しい夕暮れ』はドビュッシーの歌曲の中でも演奏される機会の多い作品の一つであるにもかかわらず、正確な作曲時期には諸説あり、最新の研究では1890年頃であると言われています。「沈みかけた夕陽が穏やかに川面と畑を照らしている。人間の命には限りがあって、やがて墓場へと導かれるように、あの夕陽も沈んでいく」という比喩的な詩を曲にしたものです。冒頭は、フォーレの『ゆりかご』に似て、穏やかな波と小麦畑を赤く染める太陽の終焉の煌めきをピアノが表現し、やがて太陽が地平線に落ちてこの曲は終わります。
ヴァイオリンとピアノで演奏されるときは、ヴァイオリンが歌の部分を演奏しますが、言葉はなくてもオリジナルの「メロディ」の魅力は十分に伝わります。楽譜を見ただけで波の様子が連想されるなど、これらの曲は詩(言葉)と音楽の融和が視覚的にも図られていることを付け加えておきたいと思います。
2019年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2019 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ハーシュ:『花の骸』-チェスワフ・ミウォシュの詩や散文による21の小品
マイケル・ハーシュ
(1971年アメリカ/ワシントンD.C.生まれ;アメリカ/フィラデルフィア在住)
『花の骸』-チェスワフ・ミウォシュの詩や散文による21の小品(2003年作曲)
『花の骸』は、ポーランド生まれのノーベル文学賞作家であるチェスワフ・ミウォシュ(1911-2004)の文章を伴った21の小品で構成された作品で、2003年に完成されました。それぞれの小品が簡潔で要を得ており、それらがまとまって、ミウォシュの文章に対する作曲家の考えを映し出しています。
マイケル・ハーシュは短期間で有名になり、同世代では最も知られたアメリカ人作曲家の一人になりました。彼の音楽言語は、無調性と調性の間をさまよっており、作曲法の常識には当てはまりにくいように見える音群や唐突なリズムの変化が際立った強烈な表現力の基礎となっています。特に、最近は、素材の効果的な活かし方や、時に簡潔になりすぎるほど凝縮された表現を強調しながら、多数の楽章を伴った曲を作る傾向にあり、楽章数も少なく、スケールの大きい作品を作っていていた20代の頃の作風とは明らかに異なります。
チェスワフ・ミウォシュは、人類の残忍な性質を見つめ続けた、20世紀を代表する偉大な詩人の一人です。数々の悲劇的な結末を目の当たりにし、人類とは図らずも限りなく残忍になれることを実感した彼の作品には、人間の存在自体に対する深い同情が感じられます。1911年にリトアニアで生まれ、第一次世界大戦中は定住することなく、第二次世界大戦中は、ナチの占領下のポーランドで地下演劇・文学・出版活動をし、その後ポーランドの外交官になりました。1951年にはフランスに亡命し、その後カリフォルニア州立大学バークリー校のスラヴ言語・文学部の教授になり、2004年8月14日にポーランドのクラクフで亡くなりました。
『花の骸』は、ミウォシュの散文と詩から19の断片とその中の2つの断片が反復された21のテキストに基づいて作曲されました。ハーシュは、伝統的な歌の様式のように歌詞として用いるのではなく、その断片を取り出し、楽器で反応しました。
全ての曲は短く、旋律の美しい瞬間は殆どありません。30分に及ぶこの作品は、最初から最後まで、ヴァイオリンとピアノが密着しながらも実質的には独立した関係を保っています。スコアには表現に関する指示が多く書かれており,分厚いものとなっていますが、この作品は、ある程度自由に、自然に弾かれるべきです。作曲家からのリズムやダイナミックに関する指示は厳格な命令というよりは、ガイドラインして捉えられるべきものだと思います。
簡単に言うと、『花の骸』は、オープンで密着した音、ピアノの長く伸ばしたペダルの音、静かなコルレーニョ(ヴァイオリンの弓の毛ではなく木の部分を使って弾く奏法で特殊な音響効果が得られる)の音の組み合わせで、ヴァイオリンもピアノも最広域の音域を使用しています。装飾的な音からも、対位法表記という限度の中で最大限に表現された感情の丈が伝わってきますが、その抑圧感がある種の力強さとなっています。また、声の導きに従順するあまり、調整に関係なく、古典的あるいは伝統的な基調から逸脱しているような新しい独特な音が、この作品では聴かれます。
『花の骸』は五嶋みどりの委嘱によって作曲された作品で、2004年から2005年のシーズン中に、五嶋みどりのヴァイオリンとロバート・マクドナルドのピアノで初演されます。マイケル・ハーシュは、モスクワ音楽院とボルティモアにあるピーボディ音楽院で学びました。また彼はタングルウッド・インスティテュートの出席者でもありました。ハーシュはピアニストとしてもアメリカやヨーロッパで活躍し、室内楽の録音は2003年にヴァンガード・クラシックスのレーベルで発売されました。モートン・フェルドマン、ヴォルフガング・リーム、ジョスキン・デ・プレらの作曲家の作品とともにハーシュ自身の作品も演奏した新しいCDも同じレーベルから発売されています。
2004年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ハートキ:作曲家基本情報
作曲家基本情報:ハートキ
作曲家名:
スティーヴン・ハートキ Stephen (Paul) Hartke

©Robert Millard
生年月日:
1952年7月6日
出生地/居住地:
アメリカ、ニュージャージー州オレンジ生まれ/カリフォルニア州グレンデール在住
スタイル:
特になし(非常に多様なスタイル)
最初に習った楽器など:
ピアノ、声楽
恩師/影響/出身校:
Mary Miley (ピアノ)
イェール大学、ペンシルベニア大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に学ぶ。
恩師:レオナルド・バラダLeonardo Balada、ジョージ・ロックバーグGeorge Rochberg
影響:中世音楽、ストラヴィンスキー、非西洋音楽
代表作:
The King of the Sun (1988年作曲)
Pacific Rim (1988年作曲)
The Horse with the Lavender Eye (1997年作曲)
Gradus (1999年作曲)
Beyond Words (2001年作曲)
Symphony No. 3 (2003年作曲)
The Greater Good (2003-2006年作曲)
A Brandenburg Autumn (2006年作曲)
編集:Andrew Freund
リサーチ・アシスタント:Clara Kim
監修:林田直樹
(2014年9月)
ハートキ:『根付』ヴァイオリンとピアノのための6つの楽章
スティーヴン・ハートキ
(1952年アメリカ/ニュージャージー州オレンジ生まれ;アメリカ/カリフォルニア州ロサンゼルス在住)
『根付』ヴァイオリンとピアノのための6つの楽章(2011年作曲)
スティーヴン・ハートキは幅広い作曲法を巧みに使いこなすことで知られ、特に人気のある現役アメリカ人作曲家の一人です。ハートキはトレンドや作曲流派といった型にとらわれず、ビバップ(bebop)やストラヴィンスキー、また中世音楽等の幅広い分野から影響を受けています。彼の作品はどれもユニークで、どの作品とも似たところがありません。そのため、「独自のスタイルが無い」ことこそがハートキの特徴と言えます。彼の作品を聴くと、理性と感性の双方が揺さぶられ、好奇心がかき立てられます。彼が与える影響の広さや、作曲スタイルの幅広さにはいつも驚かされています。
『根付』は日本の伝統的工芸品を題材にした6つの楽章からなる作品で、2011年に作曲されました。根付とは彫刻が施された小さな留め具で、その始まりは17世紀に遡ります。元々は小物入れなどを紐で帯から吊るして持ち歩く際の留め具として使用されていましたが、徐々にその美しさや作りを楽しむ芸術品として評価されるようになりました。根付は象牙や漆といった繊細な素材から作られ、日本民話をモチーフとした形状が多いと言われています。
ハートキが作曲した『根付』はロサンゼルス郡立美術館で常設展示されている次の6つの作品に影響を受けています。
1. 天狗:信仰の薄い者を食べる変幻自在の生き物
2. 平忠盛と油泥棒
3. 三味線を弾く狸
4. 獏:人の悪夢を食べる伝説上の生き物
5. 金持ちを地獄へ運ぶ鬼達
6. 山の上のお屋敷が彫られた知恵の宝玉
ハートキはこの作品について、以下のように述べています。
「第1楽章において、天狗は信仰の薄い人間を彼の住処へと誘い込むために僧の姿をしています。2つ目の根付は忠盛と油泥棒で、泥棒に間違えられてしまった奉公人と侍との真夜中の取っ組み合いが、今にも動き出さんばかりに表現されています。狸の根付では、一匹の狸が着物姿で静かに三味線を弾いています。私の作品では、三味線の演奏は、日本の劇音楽においてよく聴かれるタイプの音楽と考えています。獏は、象の頭とライオンのたてがみをもっていることからおどろおどろしい見た目をしていますが、悪夢を食べるという素晴らしい性質をもった生き物です。第5楽章のモチーフとなった根付では、金持ちの男が籠にのって旅へ出発する様子を表現しているように見えますが、7匹の鬼がいつもの運搬人にとってかわっており、金持ちの男を地獄へと嬉々として運んでいます。最後の根付は、穏やかな山の光景が涙型の象牙の中に表現されています。風が吹いてねじれたような木々と優雅なお屋敷の廊下(縁側)が霧の中に観られます。」
根付は小粋な面白さと繊細な職人技の組み合わせで成り立っています。インスピレーションの元は「オリエンタル」ですが、この作品は小手先でそのような感じを出しているものでは全くありません。ハートキの作風はヴァイオリン・パート、ピアノ・パートのどちらもが、非常に独創的かつ創意工夫に富んだものになっています。ハートキは決して既存の作曲法や音楽観をよりどころにしません。彼の作品に触れると、これまで長い間「良い」音とされてきたものの常識が覆され得ることに気づきます。それぞれの楽章の曲調は、心地よい美しい音楽という既存概念を踏襲するのではなく、モチーフである根付の描かれ方が感じ取れるようなものになっています。
天狗:第1楽章は高音域と低音域に分かれたピアノの駆け抜けるような速いパッセージで始まります。ヴァイオリンはそのピアノの速いパッセージに対し、和声的かつコラール風のメロディーを奏でます。楽章の途中で、ピアノとヴァイオリンの役割は逆転し、ヴァイオリンが速いパッセージを弾く一方で、ピアノはコードを演奏します。楽章の終盤に向けて音楽は駆け抜けていき、あたかも煙だったかのように消えていきます。
忠盛:第2楽章の冒頭は、忠盛の狂気的性格を表すかのような極めて速いパッセージがヴァイオリンとピアノによって演奏されます。第2楽章は両方の楽器にとって、その速さと常に変わりゆく(と言うよりも予測できないような)拍の変更が技術的に難しく、合わせるのは至難の業です。ハートキも言っていることですが、ジャズの影響がところどころに色濃く現れています。前半2つのセクションとは対照的に、終盤は遠くからささやくような曲調が特徴的で、このような表現は、ヴァイオリンのグリッサンドやポルタメント、四分音などの特殊奏法によって演奏されます。
狸:第3楽章は聴き慣れない特殊効果が用いられていて、恐らく最も「オリエンタル」な空気を感じられるものだと思います。ヴァイオリニストはこの楽章のほとんどをピチカートで、しかもバルトーク・ピチカートや指の代わりにギターのピックでピチカートをするなど、色々な種類のピチカート奏法が使われています。ギターのピックを使ってヴァイオリンの弦をはじくと、三味線のような音色がします。一方、ピアニストは楽章の冒頭でピアノ内部の支柱を叩きます。
獏:ハートキは人の悪夢を食べる生き物を描写するために、ノイズのようなガリガリした音色を求めています。獏の噛む音が聴こえてくるような非常に刺激的な音楽です。
鬼:鬼達は闊歩して、金持ちの男を乗せて地獄へと向かいますが、結局、何も起こらなかったかのように音楽は終わります。地獄へ堕ちていく身の毛のよだつような衝撃的な表現はジャズ的要素と即興的要素によって強調され、手に汗握るような忘れられない音楽です。高度な演奏技術がヴァイオリニストとピアニストの双方に求められます。作曲家の意図を伝えるためには、グロテスクな様相を強調するようなジェスチャーや表現が求められます。
知恵の宝玉:前楽章の熱気冷めやらぬ中、最終楽章は霊的でミステリアスな側面をもちつつも、穏やかかつ静かで、精神的充足感を感じさせます。ピアノの独奏によって楽章は始まり、終始複雑な拍子の中で演奏されますが、緩やかな楽章であるため、拍感はほとんど感じられず、自由な音楽の流れとなっています。豊かなハーモニーで非常にロマンチックな楽章です。
『根付』はアメリカ議会図書館マッキム基金より委嘱され、2011年アメリカ議会図書館において、エイト・ブラックバード(eighth blackbird)のメンバーであるマット・アルバート(Matt Albert)とリサ・カプラン(Lisa Kaplan)によって初演されました。
2014年8月 五嶋みどり
(編・訳:佐野浩介)
Notes © 2014 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調 BWV1003
ヨハン・セバスティアン・バッハ
(1685年ドイツ/アイゼナッハ生まれ;1750年ドイツ/ライプツィヒにて死去)
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調 BWV1003(1720年作曲)(『6つのソナタとパルティータ』より)
第1楽章: Grave
第2楽章: Fuga
第3楽章: Andante
第4楽章: Allegro
ヨハン・セバスティアン・バッハは、言うまでもなく偉大な作曲家として世界的に尊敬されており、その作品は「音楽が国際語である」と実感させる力をもっています。バッハの人物像については、生涯で二人の女性と結婚し、20人の子供に恵まれたことや、熱心なルター派の信者で、教会や宮廷で長い間複数の要職に就いていたことの他にはあまり一般的には知られていないようです。
1750年に亡くなってから100年近くの間、バッハの音楽はほとんど顧みられず、彼を知る少数の人も作曲家としてよりはむしろオルガン奏者としてバッハの存在を認識していました。1802年にドイツの音楽史家のヨハン・ニコラス・フォーケルによる伝記が出版され、その中で「この尊大なる天才、音楽界の大家・・・他の音楽家を寄せ付けないほど卓越した地位にいる」というバッハに関する記述があり、バッハの再認識が始まりました。バッハの作品は、彼が職務についていたライプツィヒの教会以外で演奏されたことはありませんでしたが、1829年に初めて、ベルリンで『マタイ受難曲』の演奏がフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ(1809-1847)の指揮で行われました。同じく1833年にはライプツィヒで『ヨハネ受難曲』も演奏されました。また、カミーユ・サン=サーンスがバッハの作品を編集し、多くの人に知られるようになりました。1850年には、バッハの全作品の完全校訂版が着手されましたが、完成までに50 年の歳月を要しています。
バッハは、6年間(1717-1723)アンハルト=ケーテン侯レオポルドに仕え、無伴奏ヴァイオリンのための『6つのソナタとパルティータ』を1720年に完成させました。ケーテンは教会音楽への関心が薄く、バッハは前の職場で求められていたような多くの宗教的な仕事から解放されました。したがってケーテン時代に書かれた作品は、非宗教的な器楽曲がほとんどで、『ブランデンブルク協奏曲』、『平均律クラヴィーア曲集』、『無伴奏チェロ組曲』もこの時代に書かれたものです。
『6 つのソナタとパルティータ』も他の作品と同じように、バッハの死後長い間忘れられていましたが、ヴァイオリニストのフェルディナンド・ダヴィッドによって 1843年に全曲セットが出版されたのをきっかけに、再び音楽界に紹介されることとなりました。ヨーゼフ・ヨアヒムがその中の何曲かをコンサートで演奏し、一般に親しまれるようになりました。メンデルスゾーンは、その中の『ニ短調のパルティータ』の『シャコンヌ』をピアノ伴奏付で演奏し、1854年にはロベルト・シューマンによって全曲がピアノ伴奏付きに編曲・出版されました。その後に、ブラームスとブゾーニは『シャコンヌ』をピアノ用に編曲しました。それにもかかわらず『6つのソナタとパルティータ』がヴァイオリンのレパートリーの傑作として正当な評価を受けるようになるのは20世紀になってからのことです。『6つのソナタとパルティータ』(正確には3つのソナタと3つのパルティータ)は、その複雑さと美しさという点で、ヴァイオリンのレパートリーの頂点に立つ作品と言われています。感情的にも力強く、情熱的で、演奏家に技術だけでなく音楽的にも無欠性が求められます。多くのヴァイオリニストが一生かかってもマスターするのは難しいと感じる偉大な作品です。
時代とともに大きなホールで演奏する機会が多くなるにつれて楽器の音を大きくする必要に迫られ、現在一般的に弾かれているヴァイオリンには、バッハの頃に比べ、弦の張力が高くなるように、楽器の様々な部分に調整が施されてきました。バッハの時代には、ヴァイオリンは短い指盤と低い駒が使用されていたので、同時に2つの音や3つの音を奏でることは、現在使用されているヴァイオリンで同じことをするほど難しいことではありませんでした。バッハの作品は、対位法により作曲された傑作で、旋律が独立性を保ちながらも同時に複声が演奏されなければなりません。例えば、『無伴奏ソナタとパルティータ』のソナタのフーガでは(バッハはテンポの遅い-速い-遅い-速いという楽章の構成にしたがっているので、3つの全てのソナタは第2楽章が4声のフーガになっています)、様々な旋律が相互に絡み合い、それぞれの旋律を別のヴァイオリニストが弾いているかのように演奏されなければなりません。
ソナタ第2番イ短調は、グラーヴェ(ゆっくりと、荘厳に)の楽章で厳粛に始まります。陰鬱なオープニングではメロディーは叙情的ですが、装飾が多く施されていて、バロック音楽にしては珍しく音の高低差があります(3つのソナタの第1楽章の中では確かに一番大きな跳躍があります)。最後の2小節半は次の楽章、フーガへの橋渡しの役割を果たしていて、フーガの4声の最初の9つの音符は、楽章全体のリズムの基本で、それぞれのラインがリーダー的な役割を入れ替わりに果たしていきます。この長い楽章には明らかにわかるような休みはありません。音楽は最後のクライマックスまで持続的に密度を高めていきます。
第3楽章はアンダンテで、行進に似ています。2声のうち一つはアリアのようなメロディーで、もう一つは正確なオスティナート的な8分音符というはっきりとした役割が与えられ、楽章全体を通して一貫してその役割を維持していきます。3楽章最後の静かな分散和音は、4楽章(最終楽章)の自由気ままな雰囲気の中に消えていきます。この楽章では、バッハ自身によるフォルテやピアノといったダイナミックスや、レガートや、音符のアーティキュレーションを決めるボウイングの表示も見られます。32分音符が方向性や傾向を示し、快い驚きをもって流れるような勢いを巧みに操っているかのようです。
2005年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ヒンデミット:ソナタ変ホ長調
パウル・ヒンデミット
(1895年ドイツ、ハナウ生まれ、1963年フランクフルトにて死去)
ソナタ 変ホ長調 Op.11-1 (1918年作曲)
第1楽章: Frisch
第2楽章: Im Zeitmass eines langsamen, feierlichen Tanzes
パウル・ヒンデミットは多才な音楽家で、また音楽を含む芸術関係の主催・企画にも才能を発揮しました。彼の活動の全盛期は、第1次世界大戦後から第2次世界大戦が始まるまでの時期で、指揮者や作曲家として活動しただけでなく、ヴィオラ奏者、ヴァイオリン奏者、クラリネット奏者としても名をあげました。その頃の主だった音楽理論家で、教育者でもあったヒンデミットは、ドナウエッシンゲン音楽祭(ドイツ)を取り仕切り、また、トルコ政府から依頼された仕事も受けていました。
ヒンデミットの母国、ドイツでは、ナチズムの台頭によって自由な発想を抑圧されたため、彼は渡米せざるを得なくなりました。1946年にはアメリカの市民権を取得しましたが、後にヨーロッパに戻り、活動を続けました。彼の才能が多岐に渡っていたのと同じように、音楽に関しても好奇心の対象は幅広く、中世やルネッサンスの音楽や古楽器を熱心に擁護しました。
彼は1917年から1919年にかけて、Op. 11のソナタ集を作曲しました。1917年に手がけた最初の11-1の作品は彼自身によって破棄され、1918年に作曲されたこの変ホ長調のソナタに11-1の番号がつけられました。この作品は2つの楽章で終っているので、未完成のような印象を受けます。彼は、本来ならば最終楽章となるべき第3楽章のインスピレーションがわかず、作曲しなかったので、2つの楽章で完結したソナタとしました。
このソナタは、無調様式で作曲されています。理論的に分析して、古典スタイルとはかけ離れた無調様式の要素をはっきり指摘しなくても、この曲を聴けば、まず始めの部分の主要なテーマの直接性に聞き手は気づくはずです。この作品全体における、リズムの軽快さに補足された無調の効果は、奇妙で、不思議な、人の気をそそる愉快な滑稽さにあります。
第1楽章(快活に)の形式は、全体的に見ると、A-B-C-B-Aのパターンを形成しており、回文的な特徴があります。この楽章の始めと終わりを飾るAセクションは、堂々とした力強い旋律で始まります。このセクションの基本の和音は、E♭-G-Bで、変ホ長調の主和音の第5音が半音高められています。普通、変ホ長調の主和音はE♭-G-B♭、短調では E♭-G♭-B♭になりますが、第5音が半音高められた主和音は、2つの長3度の組み合わせであり、三和音の第5音の長3度上の音はD♯(E♭)で、三和音のGとBの音がE♭からE♭の1オクターブを3等分していることがわかります。1オクターブを均等に分割するやり方は、19世紀後半から20世紀全般で、好まれていた作曲技巧の一つでした。
第1楽章の第1セクションAのテーマは、音符が上下に幅広くジャンプしているのに対して、第2セクションBのテーマは、一つの音から次の音へ滑らかに移っていくように奏でられます。嬰ト短調(G♯minor)で始まり、徐々に変イ長調(A♭Major)になります。 勿論、G♯とA♭は同じ音程です。
次はA-B-C-B-Aの移行部分であるCのセクションです。ハーモニーがどのようにして徐々に第2テーマBに戻っていくのか見極めるのは難しいです。第2テーマが再現されたとき、エネルギーは充満していますが、すぐに静かに、甘く、優しくなり、それとは対照的な冒頭のテーマAに戻るフィナーレを迎えます。興奮絶頂の中で、変ホ長調の主和音でこの楽章は終わります。
もともと3楽章あるソナタの真ん中の楽章として作曲された第2楽章(ゆっくりとしたテンポで、厳粛な踊り)は、ピアノが奏でるE♭のオクターブの2音で始まります。オスティナートのように、反復されるリズムは葬送曲(葬送行進曲のリズムではない)を思い浮かべてしまいます。この楽章は、ヴァイオリンはミュート(弱音器)をつけて演奏され、夢の中に身を置いているような感覚を助長します。
分析を加えると、始めと終わりのセクションは半音の動きが多く使われているのに対し、中間部では和声に基づく分散音が多用されているのが特徴です。この楽章の終わりは、半音階的な音の動きが繰り返され、主音のE♭で終りますが、 雰囲気はどちらかというと終始不安定で、無気味な様相を呈しています。
2003年10月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ヒンデミット:ソナタホ調
パウル・ヒンデミット
(1895年ドイツ/ハナウ生まれ;1963年ドイツ/フランクフルトにて死去)
ソナタ ホ調 (1935年作曲)
第1楽章: Ruhig bewegt
第2楽章: Langsam – Sehr Lebhaft
2013年はパウル・ヒンデミットの没後50周年に当たります。ワーグナーやヴェルディの生誕200周年、ルトスワフスキやブリテンの生誕100周年の影に隠れがちですが、この記念年にヒンデミットの多大な功績の価値も広く見直されています。
彼は世界的なヴィオラ奏者として活躍しましたが、ヴァイオリン奏者、指揮者、作曲家でもあり、音楽祭も取り仕切り、アドミニストレーターや高名な教育者としての顔も持ち合わせるなど、最も多才な音楽家の一人であると言えます。いずれの面でもヒンデミットが音楽の世界に与えた影響は大きく、その一部は彼の著名な弟子たちの功績を通じて現在でも感じることができます。
ヒンデミットは、混沌とした時代にあっても権力に媚びることなく悪習を打破するドイツ人で、ゲルマン音楽をプロパガンダに利用していたナチスとの関係は、複雑で緊張したものでした。ヒトラーと宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスにとって、芸術、特に音楽は文化政策の標的で、彼らの人種理論に則して、しばしば芸術家を利用したり、弾圧したりしました。
ナチ統治下では、ヒンデミットの作品は芸術的に好ましくないとしばしば批判され、ユダヤ人ハーフの女性との婚姻や、ユダヤ人やユダヤ系の演奏家との共演を非難されるなど、不遇の時代を過ごしていました。1934年の「ヒンデミット事件」(指揮者のフルトヴェングラーが、ヒンデミットの新作オペラ『画家マティス』の初演に先駆け交響曲版を初演した後で、ナチス政権によってオペラの上演を禁止されたことに対し、作曲家を擁護する論評を書き、それが新聞に掲載され反響を呼んだ事件)を受け、ゲッベルスは “無調の騒音製造者”と容赦なくヒンデミットを排斥したのです。
政治的弾圧は、ヒンデミット夫妻がドイツを離れる決定的な要因となりました。多くの偉大な芸術家たちがドイツやヨーロッパ諸国から亡命していった現実は耐え難いものがあり、夫妻も1935年にまずトルコに移住し、1938年にはスイス、1940年にはアメリカに渡り、彼はイェール大学で教授に就任しています。
生涯にわたって作曲を続けたヒンデミットは、新古典主義、対位法、後期ロマン主義や表現主義を経て、1930年代には、無意識のうちに気品と自信と安楽が感じられる独自のスタイルを完成したと言えるでしょう。『ソナタ ホ調』は日々のストレスを殆ど感じさせない作品に仕上がっています。
ヴィオラ奏者として有名な彼も、最初はヴァイオリンを習っていました。この2楽章から構成される10分程のソナタは、ヴァイオリンとピアノのために書かれた3番目の作品で、前2作品は1918年に作曲されました。この作品は、全ての楽器のためにソナタを1曲ずつ作曲しようとしたシリーズの最初の作品で、以後20年の間に26曲のソナタを残しました。
1935年の夏に書かれたこのソナタは、彼の作風の真髄を表した作品です。三声の対位法のカノン形式で書かれており、流れるような旋律と、コントラストのはっきりした別の雰囲気をもつセクションが共存しているところが特徴的です。冒頭は春のように心地良く、旋律は独唱のようです。中間部では、不吉な雲の影が忍び寄り緊迫してきますが、破滅はしません。この楽章の最後は、ノスタルジアと静かなユーモアが見え隠れして終わります。このソナタの中心である第2楽章は、ゆったりとした葬送曲のような荘厳な雰囲気の中でさえ凝縮された感情の揺れが見られるグラーヴェ(grave)のセクションと、陽気さと不安が入り乱れスリリングな気配も漂う、ダンスのようなタランテラ(tarantella)の対照的なセクションから成っています。コーダでは、両方のセクションからの要素が組み合わされ、希望に満ちた煌びやかなホ長調で幕を閉じます。
『ソナタ ホ調』は1936年2月に、スイスのジュネーブで、ステファン・フレンケルとマルーシャ・オルロフによって初演されました。
2004年7月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ヒンデミット:ソナタハ調
パウル・ヒンデミット
(1895年ドイツ/ハナウ生まれ;1963年ドイツ/フランクフルトにて死去)
ソナタ ハ調 (1939年作曲)
第1楽章:Lebhaft
第2楽章:Langsam-Lebhaft-Langsam, wie zuerst
第3楽章:Fuge
パウル・ヒンデミットは、作曲だけでなく、音楽学やアート・マネジメントにも力を発揮した多才な人物で、またヴァイオリン奏者としても、ヴィオラ奏者としても指揮者としても活躍しました。モダニズム音楽が“芸術のための芸術”という哲学を包含している時代に、ヒンデミットはゲブラウフスムジーク(Gebrauchsmusik)、または“実用音楽”といわれる特定の実用的な目的のために作曲され、アマチュア奏者たちによっても演奏可能な作品を支持していました。
スイスに亡命中に書かれた『ソナタ ハ調』(1939年作曲)は、ヒンデミットがヴァイオリンとピアノのために残したソナタ4曲のうちの一つです。3楽章から構成されたこのソナタは、音楽言語としてはマーラーの作品と類似しているところがあります。
Lebhaft(元気に)と表記された第1楽章はファンファーレのようで、作品冒頭の主要テーマが曲の進行とともに展開していきます。このテーマは楽章全体の基礎を成しており、あたかもブロックを積み重ねているような構造になっています。冒頭は大胆で朗々とした低い音で始まり、徐々に盛り上がって最後には高い音へ展開していき、この楽章は終わります。
第2楽章のLangsam-Lebhaft-Langsam, wie zuerst(ゆっくりと-元気に-最初のようにゆっくりと)は、第1楽章に比べかなり繊細な性格を帯びており、偏在するバロック音楽のような要素は大胆でエネルギッシュな前楽章とは対照的です。第2楽章は3つのセクションに分かれており、最初と最後のセクションは同じ素材を使いながらも、はっきりと異なった様式で書かれていて、全体的にバロックの特徴が暗示されています。真ん中のセクションは意図的に冷静を装いながらも、8分の5拍子の変拍子で、常に踊っている感じがして、コミカルでチャーミングなところがあります。最後には、楽章の最初と同じように単調な4分の2拍子が戻ってきます。
最終楽章に漂う厳粛な雰囲気は、三声のフーガ(Fuge)の効果によるものです。この曲によって、ヒンデミットが三声のフーガ形式の作曲技術を完璧にマスターしていることがよくわかります。フーガの展開とともに緻密に重なり合う縦の響きが緊張感を高め、鋭く荘厳なフィナーレを迎えます。
2007年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2007 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ファリャ:スペイン民謡組曲
マニュエル・デ・ファリャ
(1876年スペイン/カディス生まれ;1946年アルゼンチン/アルタ・グラシア死去)
スペイン民謡組曲(1914年作曲)(コハンスキ編曲)
1. ムーア人の織物
2. ナナ
3. カンシオン
4. ホタ
5. アストゥーリアナ地方の歌
6. ポロ
パウル・コハンスキは他の作曲家の作品をピアノとヴァイオリンのために編曲することを得意としていましたが、彼の編曲はいつも原曲の美しさをとどめ、ヴァイオリンがオリジナルの楽器の代わりというような使われ方はされず、ヴァイオリンの特徴を最大限に活かした独特のスタイルを持っています。
マニュエル・デ・ファリャの『7つのスペイン民謡』は、原曲は声楽とピアノのための曲で、コハンスキの尽力でヴァイオリンとピアノのための曲に編曲されました。コハンスキによって編曲されたこの組曲は今日のコンサートでは最も演奏される機会の多い曲の一つになっています。コハンスキの努力に感謝したデ・ファリャは新しく編曲されたこの作品をコハンスキの妻に再び献呈しました。
デ・ファリャはアルベニスやグラナドスとともに当時のスペイン民族音楽の先駆者として活躍しました。興味深いことに、デ・ファリャに民族音楽をもとにして作曲をすることを思いつかせたのはノルウェーの作曲家のグリーグでした。デ・ファリャはスペイン南部のカディスで、アンダルシア出身の父とカタロニア出身の母の間に生まれました。
彼はパリで勉強し、ドビュッシーの影響を受けるようになりました。彼は第一次世界大戦が始まった夜にスペインに戻り、その後すぐにマドリッドでこのスペイン民謡組曲を書きました。
この6つの組曲全てが民族音楽を素材として書かれたわけではありません。『ポロ(フラメンコの踊り)』と『ホタ(アラゴンの踊り)』は完全に民族音楽のスタイルで書かれていますが、それ以外の『エル・パーニョ・モルーノ(ムーア人の織物)』、『アストゥーリアナ(スペイン北部の子守唄)』、『ナナ(アンダルシアの子守唄)』と『カンシオン』は、その地方で当時もてはやされていた音楽素材を用いながらも、オリジナルの和声の伴奏部に新鮮な解釈が付け加えられています。これらの歌は大変印象的で脳裏に焼き付きます。オリジナル版の組曲(7曲)では、狭い音域の中で鼻をつまんだような、ハミングのような音質がラテン的でムーア的なこの曲の性質に、さらに緊迫感と権威と激情を付け加えます。
コハンスキのヴァイオリンとピアノのための編曲はオリジナルから『ムルシア地方のセギディーリャ』が省かれ、全部で6曲です。曲の順番は演奏者が自由に決められます。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調 Op.13
ガブリエル・フォーレ
(1845年フランス/パピエ生まれ;1924年フランス/パリにて死去)
ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調 Op. 13 (1875-76年作曲)
第1楽章: Allegro molto (きわめて速く)
第2楽章: Andante(やや遅く)
第3楽章: Allegro vivo(生き生きと速く)
第4楽章: Allegro quasi presto (プレストのように速く)
19世紀後半のフランスでは、印象主義の影響はまだ現れていませんでしたが、独特の音楽を作ろうという意識が復活する傾向がありました。ドイツでは、シューベルトやシューマンに代表される純ドイツ歌曲に端を発する歌曲がロマン主義の主流で隆盛を極めており、フランスでは、その風潮を受けて、フォーレや彼と同時代の作曲家が、ユーゴーやボードレール、モリエール等の書いた詩に曲をつけ、膨大な量の歌曲を作曲しました。特に、フォーレは生涯100以上の歌曲を残し、「フランスのシューベルト」と呼ばれていたことからも、フランス歌曲の偉大なる巨匠と考えられていたことが察せられます。
フォーレは、幼い頃から音楽に頭角を現し、教会音楽をカリキュラムに取り入れて、オルガン奏者や聖歌隊の指導者を養成することで有名であったニデルメイエール古典宗教音楽学校に入学し、創設者のニデルメイエールのもとで、古くから教会で用いられている単旋聖歌等の教会音楽や、ルネサンスのポリフォニー (多声音楽)、オルガン音楽について勉強しました。ニデルメイエールの死後は、特にピアノと作曲のクラスを引き継いだ若いサン=サーンスから当時最先端の様式を学びました。この中には、シューマンやリストやワーグナーといった作曲家の音楽も含まれていました。
イ長調のヴァイオリン・ソナタは、フォーレの初期の三大傑作の一つと考えられています。1875年から76年にかけて作曲され、ヴァイオリニストのポール・ヴィアルドーに捧げられ、1877年にパリにて、フォーレのピアノで初演されました。ヴィアルドー一族は傑出した音楽一家で、特にオペラ界では有名でした。ポールの母親のポーリーヌは歌手で、その娘のマリアンヌとフォーレは一時婚約していたこともありました。
このソナタ第1番は、全体的に感情が溢れ出て、心に伝わる曲です。歌曲のような素直なメロディーが次から次へと展開し、勢いを増していきます。優雅な雰囲気だけでなく、若々しく爽やかで、希望に満ち溢れた様子が洗練された手法で表現されています。第2楽章は、全体的に穏やかで、もの悲しさが漂います。続く第3楽章のスケルツォの始めと終わりは、軽快で速いテンポですが、中間部は朗々として楽しげです。このスケルツォ楽章のスタイルは、後にラヴェルやドビュッシーといったフランスの作曲家も好んで用いました。最終楽章は、 華麗さに大胆さも加わり、光り輝いて堂々と終わります。
2003年11月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
フォーレ:3つの歌より『ゆりかご』 Op.23-1
ガブリエル・フォーレ
(1845年フランス/パピエ生まれ;1924年フランス/パリにて死去)
3つの歌より『ゆりかご』Op.23-1
&
クロード・ドビュッシー
(1862年フランス/サン・ジェルマン=アン=レー生まれ;1918年フランス/パリにて死去)
美しい夕暮れ(ハイフェッツ編)
フランス芸術歌曲「メロディ」は、主に19世紀に活躍した作曲家のフォーレとドビュッシーによって、当時の高踏派詩人のボードレール、ユーゴ―、ヴェルレーヌなどの詩に曲をつけたという点でドイツにおける「リート」の存在と似ています。「メロディ」は、19世紀半ばのベルリオーズ(1803-1869年)が名づけ、20世紀のプーランク(1899-1963年)の頃にかけて盛んに作られました。
「メロディ」と「リート」は歌詞にあたる詩そのものが文学的に高い評価を得ている点が、それまでの伝統民謡に曲をつけた「ロマンス」と一線を画します。またドイツの「リート」との明確な違いは、数小節ごとに旋律のリピートがなく規則的なリズムに捉われず、フランス語独特の詩と密接に流れる歌詞と韻律が生かされています。哲学的思想や人生観を見事に表現する短い作品「メロディ」は、歌曲のジャンルにおいて重要な部分を占めていると言えるでしょう。
文学的な観点では、フォーレの『ゆりかご』はルネ・フランソワ・シュリ・プリュドムの詩に、ドビュッシーの『美しい夕暮れ』はポール・ブールジェの詩に曲を付けたもので、2つの詩はフランス芸術の移り変わりを反映しています。様式上では同じ「メロディ」に分類されますが、あえていえば、フォーレはロマン派と印象派の過渡期の作曲家であり、ドビュッシーは印象派の作曲家(本人はそのような分類を嫌っていましたが)に分類することは可能です。両曲共に太陽と波について語る作品を同時に取り上げることで、興味深い比較ができるように思います。
『ゆりかご』は、3曲で構成されるフォーレの「Op.23」の中の1曲で、1882年に国民音楽協会(Société Nationale de Musiqu)の演奏会で、ピアニストと歌手によって初演されました。ピアノのアルペジオで穏やかな水面を感じながらゆりかごを揺らす母親のイメージから、歌手は、あやしている子供たちもやがて成長し、注がれた愛情を忘れ、海に出て行ってしまう、という逃れられない女性の性(さが)を表現しています。全体的に絶望感の中でも繊細さやピュアなところに、この曲の魅力があります。
『美しい夕暮れ』はドビュッシーの歌曲の中でも演奏される機会の多い作品の一つであるにもかかわらず、正確な作曲時期には諸説あり、最新の研究では1890年頃であると言われています。「沈みかけた夕陽が穏やかに川面と畑を照らしている。人間の命には限りがあって、やがて墓場へと導かれるように、あの夕陽も沈んでいく」という比喩的な詩を曲にしたものです。冒頭は、フォーレの『ゆりかご』に似て、穏やかな波と小麦畑を赤く染める太陽の終焉の煌めきをピアノが表現し、やがて太陽が地平線に落ちてこの曲は終わります。
ヴァイオリンとピアノで演奏されるときは、ヴァイオリンが歌の部分を演奏しますが、言葉はなくてもオリジナルの「メロディ」の魅力は十分に伝わります。楽譜を見ただけで波の様子が連想されるなど、これらの曲は詩(言葉)と音楽の融和が視覚的にも図られていることを付け加えておきたいと思います。
2019年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2019 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ断章スケルツォ
ヨハネス・ブラームス
(1833年ドイツ/ハンブルク生まれ;1897年オーストリア/ウィーンにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ断章 スケルツォ ハ短調 (1853年作曲)
まだ駆け出しの音楽家だったブラームスにとって、1853年は、ユダヤ系ハンガリー人で著名なヴァイオリニスト、指揮者、興業主、作曲家でもあったヨーゼフ・ヨアヒム(1831-1907年)から当時音楽界のパワーカップルであったロベルト・シューマンとその妻クララを紹介され、夢にも思わなかったチャンスに恵まれた年でした。ヨアヒムとブラームスの年の差はたった2歳でしたが、既に偉大な音楽家として名を馳せていたヨアヒムはブラームスの才能と将来の成功を確信し、二人の交流は生涯にわたって続きました。
『ソナタ断章』はもともと1853年にロベルト・シューマンの発案でヨアヒムへの誕生日のプレゼントとして3人の作曲家によって作られた『F-A-Eソナタ』の一部で、シューマンが第2楽章と第4楽章を、彼の教え子のアルベルト・ディートリヒが第1楽章を、そしてブラームスが作曲したのが第3楽章のスケルツォです。“F-A-E”は、ヨアヒムが好んだドイツ語のエピグラム「Frei aber einsam(「自由だが孤独に」という意味)」の頭字語で、「F.A.E. : 尊敬され愛される我らの友の到着を待ちわびて、このソナタはR.S.とJ.B.とA.D.によって書かれました」と献呈のところに記されています。クララ・シューマン(ピアノ)とともにこのソナタを演奏したヨアヒムは、直ちに3人のうち誰がどの楽章を書いたか正しく当てたそうです。
今日『F-A-Eソナタ』が一度に全曲演奏されることはめったにありません。シューマンは同年後半に、『F-A-Eソナタ』のために作曲した第2楽章と第4楽章を再利用して、『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番』を完成させました。ブラームスが担当したスケルツォの第3楽章は、彼の死後の1906年に楽譜を保持していたヨアヒムの要請で、一つの作品として出版されました。残りの楽章もその後出版されましたが、ブラームスのスケルツォだけが独立した作品として今日でもヴァイオリンのスタンダードなレパートリーとなっています。
『ソナタ断章』はブラームスのキャリアの中では初期のものですが、 彼が偉大な輝く作品を生み出していく兆候が随所に見られます。この5分ほどの作品の中で、壮大さ、ドラマ、情熱的なロマンチシズム、豊かなハーモニー、独特な拍子の取り方、のすべてが繰り広げられます。受け取り方は様々ですが、ヴァイオリンで演奏できる最低音の連続したGの音で始まるオープニングは、行進を思わせる緊迫感があり、激しい気質にさらに刺激を加えるようなところは、ヨアヒムを意識したのかハンガリー風とも言えるかもしれません。すぐに希望溢れるパッセージに変わり、抒情的な雰囲気が支配しますが、冒頭の繰り返される3連符のリズムは、性質を変えながらも常に存在し、この曲全体をまとめる役割を果たしているとも言えます。スケルツォの典型的な形式で作曲され、詩情豊かでエレガントな中間部のセクションは美しく、若々しさが感じられます。すぐさま耳慣れた3連符の再現部に移り、長く伸ばす音符で演奏される部分が続き、最後はハ長調のシンフォニックコードに向けて昇りつめていきます。
2019年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2019 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番ト長調 Op.78
ヨハネス・ブラームス
(1833年ドイツ/ハンブルク生まれ;1897年オーストリア/ウィーンにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番ト長調 Op.78(1878-79年作曲)
第1楽章: Vivace non troppo
第2楽章: Adagio
第3楽章: Allegro molto moderato
ロベルト・シューマン(1810-56年)に「天才」と呼ばれたブラームスの作品は、それまでの伝統的な古典的スタイルを踏襲しながらも、ドイツロマン派の気質が感じられ、力強い交響曲から歌曲のささやくような繊細な感じまで、実に幅広い響きを持っています。
ブラームスは実直かつ寛大で、控えめな性格であったと言われています。シューマン一家への終生変わらぬ献身ぶりは有名ですが、ロベルトの未亡人クララとその子供達への愛情は、独身を貫いた彼には、感情的にも、彼の音楽人生にとってもなくてはならない存在でした。
シューマン夫妻の息子でヴァイオリニスト・詩人であったフェリックス(ブラームスが名付け親)が24歳で亡くなった直後に作曲されたこの曲は、ブラームスの悲しみが投影されていますが、落胆よりもクララへの思いやりの気持ちが全体的に感じられます。
1878年と79年の夏に南オーストリアのポルトシャッハで書かれた『ソナタ ト長調』は、ヴァイオリンのレパートリーの中でも最も愛されている作品の一つである『ヴァイオリン協奏曲 Op.77』に続いて作曲されました。それまでにもブラームスはヴァイオリン・ソナタに取り組んでおり、このソナタを完成させるまでに3~5曲試作したと言われています。
このソナタは3楽章から構成されていて、その第1楽章と第3楽章には、1873年に自身が作曲した『雨の歌(Regenlied)Op.59-3』と『余韻(Nachklang)Op.59-4』の主題が用いられています。友人のクラウス・グロートによる詩とセットで、彼らは象徴的かつ詩的に雨を表現しました。最初の詩では、雨は「子供の頃の夢を呼び覚まし、純真で子供じみた畏敬の念で私の魂を濡らす」もので、2番目の詩では、「雨粒と涙が混ざり、太陽が再び輝き始めると、草はさらに倍に青くなり、私の頬を流れる熱い涙もさらに倍に燃える」と語られています。この作品は標題音楽ではありませんが、作品が展開するに連れて、演奏者や聴衆だけでなく、ブラームス自身の心の奥底が垣間見えるようです。
第1楽章は、ピアノもヴァイオリンもmezza voce(半分の音量)で始まります。ヴァイオリンが付点のリズムのD(![]() )の音を繰り返す印象的なメロディーで主題を奏でます。
)の音を繰り返す印象的なメロディーで主題を奏でます。
特に楽章の始まりのリズムの形は、ブラームスの典型的なパターンで、ヴァイオリンとピアノの強拍がほとんど重なることはないので、重なったときのインパクトは深く響いてきます。2つの楽器の不規則なメロディーラインが、長いフレーズを作っています。
最初の3つの付点音符のリズムは、第1楽章の至るところで散発的に用いられているだけでなく、第2楽章の中間部でも用いられ、葬送行進曲のような重苦しい感じで、前後の心温まるセクションとは明白に異なる雰囲気をもっています。
最終楽章(この作品には伝統的なソナタにあるScherzoの楽章がありません)でも、再び3つのDの音のパターンが現れます。付点のリズムで始まるメロディーとともに、雨か涙の滴を想わせる十六分音符の静かな伴奏が聴こえます。
その後、第2楽章の主題が再現され、意気揚々と希望に満ちた幸福の絶頂へと徐々に向かいます。再び冒頭の主題が聴こえ、過去を優しく回想しながら、この曲は静かな終焉を迎えます。
2003年/2016年5月改訂 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番イ長調 Op.100
ヨハネス・ブラームス
(1833年ドイツ/ハンブルク生まれ;1897年オーストリア/ウィーンにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番イ長調 Op. 100(1886年作曲)
第1楽章: Allegro amabile
第2楽章: Andante tranquillo
第3楽章: Allegretto grazioso
ヨハネス・ブラームスは、19世紀のドイツのロマン派を代表する作曲家です。幼い頃からコントラバス奏者であった父親の影響を受け、音楽に親しみ、ピアノをマスターし、演奏家として、また指揮者としても活躍しました。作曲家としては、ロベルト・シューマンによって最初に認められ、また、シューマン夫妻には音楽的にも強く影響を受け、ロベルトの死後も妻であるクララとは生涯深い友情によって結ばれていました。1868年に作曲した『ドイツ・レクイエム』の初演の大成功により、ブラームスの名声は不動のものとなりました。1875年からは、作曲活動を中心に行い、1885年までに壮大な交響曲を4曲書き上げました。その後、主に室内楽を作曲し、1890年以降、主だった作品は残していません。ブラームスは室内楽や器楽曲などあらゆる分野で傑作を書いていますが、生涯に渡り、特に歌曲に強い興味を持ち、150曲以上の歌曲を残しました。
ブラームスは、かなり内向的な性格をしており、その性格が彼の作品に反映されていると言われています。ロマンティシズムに基づきながらも、激しい情熱はあくまでも内に秘めたようなところがあるのが特徴です。
ヴァイオリン曲としては、1853年に『スケルツォ』が最初に作曲されました。ブラームスは、ヴァイオリンの曲でも、歌曲に使われるような表示法を多く使用しているのが特徴です。ソナタは3曲残されており、第1番は1879年に、第2番は1886年に、第3番は1888年に完成されました。『ソナタ第2番イ長調』は、ウィーンで初演された後、1887年にジムロックから出版されました。
第1楽章は、Allegro amabile(速く、愛らしく)で、冒頭から第1主題の旋律が、ピアノによって大胆に奏でられ、5小節目で、ヴァイオリンがピアノの旋律に相槌を打ち、6小節目からまたピアノの旋律に戻ります。メロディーラインが長く、その間に他の楽器が応答するような形はブラームスの作品に多く見られます。この楽章では、第1主題自体が、ピアノによる第2主題の序奏の役割を果たしています。旋律は美しく、常に歌曲の風合いが漂います。最後は晴れ晴れしく終わります。
第2楽章はAndante tranquillo(やや遅く、静かに)で、叙情的なアンダンテとヴィヴァーチェが交互に現れ、フォークダンスを彷彿させるところもあります。
第3楽章はAllegretto grazioso(quasi Andante)(やや速く、壮大に)で、冒頭からヴァイオリンが重厚な旋律を奏で、ピアノは和音とアルペジオで表情に厚みを加えます。歌曲を連想させる楽章ではありますが、終盤に向かって、徐々に盛り上がりを見せ、ヴァイオリンがダブルストップ(重音)で旋律を奏で、合唱の響きのようなヴァイオリンとピアノの和音でこの曲は終わります。心に重く浸透するような響きが胸に残る曲です。
演奏する側としては、単純な旋律が多く、深い理解力が要求される曲です。リズムも小節単位で区切られておらず、解釈の仕方は容易ではありません。ピアノの中低音からイメージが膨らむところも多く、どちらかと言うと、ピアノに重心が置かれ、ヴァイオリンと応答しあうため、入念に分析される必要があります。技巧を誇示した作品でないだけに、作曲者の意図をいかに明確にくみ取ることができるかが重要なポイントとなります。
2003年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ブラームス:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番ニ短調 Op.108
ヨハネス・ブラームス
(1833年ドイツ/ハンブルク生まれ;1897年オーストリア/ウィーンにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第3番ニ短調 Op.108 (1888年作曲)
第1楽章:Allegro
第2楽章:Adagio
第3楽章:Un poco presto e con sentimento
第4楽章:Presto agitato
ブラームスは1886年から1888年まで毎夏スイスのトゥーン湖の畔にあるホフシュテッテンという街に滞在しました。この頃までにブラームスは、4曲の交響曲も含む壮大な作品を多く発表しており、既に国際的な名声も得て、作曲活動から引退しようとしていました。それにもかかわらず、この牧歌的な土地で、『チェロとピアノのためのソナタ第2番ホ短調 Op. 99』や、2曲のヴァイオリンとピアノのためのソナタ(『第2番イ長調 Op.100』と『第3番ニ短調 Op. 108』)を含む数々の歌曲や室内楽を作曲しました。
この『Op. 108』は、他の2曲のヴァイオリン・ソナタと較べて、より外向的でヴィルトゥオーソ的な性質を持ち合わせている点が特徴的です。室内楽という言葉通りサロンタイプの部屋で演奏されるよりも、むしろ、もっと多くの聴衆が入るコンサート・ホールのような場所で演奏されることを念頭に作曲された感じがします。特に、最終楽章では、交響曲的な特徴のあるスケールの大きいセクションがあり、確かに音がよく響く広々としたスペースで演奏される方が効果的です。
ブラームスのヴァイオリンのための作品には、3曲のソナタの他に、FAEソナタのスケルツォ、コンチェルトが1曲、ヴァイオリンとチェロのためのダブル・コンチェルトがありますが、数的に決してヴァイオリンのために多くの作品を残したとはいえません。しかしながら、若かりしブラームスが1853年にツアーの伴奏をしたエドゥアルト・ホフマン (通称レメーニ)や偉大なヴァイオリンの巨匠で作曲家でもあるヨーゼフ・ヨアヒムとの親交から、ヴァイオリンという楽器を熟知していたことは明らかです。
ブラームスの『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』の第1番と第2番は、3楽章の構成で書かれていますが、この作品は、4つの楽章で構成されています。第1楽章は、ヴァイオリンの美しい微かな輝きのある叙情的な主題で始まり、ピアノはシンコペーションのリズムで緊迫した感情を表現しながらヴァイオリンをサポートします。シンコペーションのリズムまたはその変形(弱拍が強拍よりも強調されている)は、楽章全体に見られます。また展開部でピアノのオスティナート(ある一定の短いフレーズやメロディーが同じピッチで反復されること-ここでは低音が繰り返される)が46小節も続くのが大変印象的です。
第2楽章と第3楽章では、シンプルさが際立つ旋律の美しさと、さりげないユーモアというはっきりとしたコントラストを見せてくれます。哀愁を帯びたメロディーで、落ち着いた雰囲気がある第2楽章のアダージョのあとに、感傷的なスケルツォが続きます。スケルツォは通常慣習的に3拍子のものが多いですが、この作品のスケルツォは2拍子(4分の2)です。
最終楽章は、燃えるような興奮を呼び起こし、この曲の中で最も交響的様相をもった楽章です。シンコペーションがこの楽章でも特徴的な要素となっています。この作品のクライマックスは、陰鬱なエネルギーを保ちながら、ニ短調で終わります。
ブラームスの作品は、ワーグナーやチャイコフスキー、ジョージ・バーナード・ショー(当時は音楽批評家として活躍)らに酷評されたときもありましたが、ロバート・シューマン、クララ・シューマンやこのソナタを献呈された指揮者でピアニストのハンス・フォン・ビューローらはブラームスの熱心な信奉者で、生前から偉大な作曲家として尊敬を集めていたことは明白です。この作品は1888年12月22日にブタペストでハンガリーのヴァイオリニストであるイエネ・フバイと作曲家自身がピアノを弾き、初演されています。
2004年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
フランク:ソナタ イ長調
セザール・フランク
(1822年ベルギー/リエージュ生まれ;1890年フランス/パリにて死去)
ヴァイオリン・ソナタ イ長調 (1886年作曲)
第1楽章: Allegretto moderato
第2楽章: Allegro
第3楽章: Recitativo-Fantasia
第4楽章: Allegretto poco mosso
セザール・フランク作曲の『ソナタ イ長調』は、ヴァイオリンとピアノのために書かれたソナタのレパートリーの中では古典に属し、美しく、刺激的で、空想的で、痛烈なところもあり、ドラマに満ち溢れています。フランクの他の主要作品が、彼の死後から現在に至るまで、流行り廃りを繰り返してきたのに対して、この『ソナタ イ長調』は、常に演奏家からも聴衆からも愛されてきました。
ベルギー生まれのフランクは、その人生の殆どをパリで過ごしました。父親は息子がコンサート・ピアニストになることを望み、1830年にリエージュ音楽院に入学させましたが、その後、一家はパリに移住し、フランクはパリ音楽院でも学んでいます。彼は父親の期待通りのすばらしいピアニストになり、コンサート・ツアーを行い、様々な賞も受賞しましたが、ソリストとして輝かしいキャリアを築いていくためには自分で自分を売り込んでいかねばならず、性格的に向いていませんでした。
フランクは若いときから作曲に興味を持っていましたが、父親はあまり快く思っていませんでした。彼が作曲に本気で取りかかれるようになったのは、パリのサント・クロチルド教会の首席オルガン奏者になった1858年頃からです。彼は生涯この教会でオルガン奏者を務め、1872年からはパリ音楽院のオルガンの教授として後進の指導にあたりました。教え子の中には、ヴァンサン・ダンディ、アンリ・デュパルク、エルネスト・ショーソンらの熱心な生徒がいました。
フランクは、古典的なスタイルで半音階的和声進行を確立したロマン派の作曲家です。晩年の10年間に、『交響曲ニ短調(1888年作曲)』、『ピアノとオーケストラのための交響的変奏曲(1885年作曲)』、『ピアノのための前奏曲、コラールとフーガ(1884年作曲)』といった名作を次々と生み出しました。ヴァイオリンとピアノのために書かれた唯一の『ソナタ イ長調』もこの密度の濃い時期の作品で、ベルギー出身のヴァイオリニストであるウジェーヌ・イザイの結婚のお祝いとして贈られ、1886年9月に初演されました。公の場での初演は、イザイのヴァイオリンとイザイ夫人のレオンティーヌ・マリー・ボルド=ペーヌのピアノによって、3ヵ月後にブリュッセルにある近代美術館で行われました。
このソナタは4楽章から構成されており、テンポがゆっくりな楽章と速い楽章が交互に組み合わされています。第1楽章が始まると、中断されることのないメロディーとバルカロール(ゴンドラの船頭が歌う舟歌)の優しい揺れを思い起こさせるようなリズムで満ちたストーリーが始まります。情熱とエネルギーが詰まった火の玉のような第2楽章は、ヴァイオリンとピアノのデュオ作品の中で最も難しいパッセージの一つとされているピアノのソロで始まります。速いテンポで絶え間ない動きが続くにもかかわらず、メロディーのなめらかさは傑出していて、躍動感とともに緊迫感に包まれます。第3楽章は幻想に満ちた瞑想的な楽章です。暗く、精神的に抑えたような雰囲気の中で流れるうっとりとしたメロディーが放縦さをかもし出し、平穏で達成感のある第4楽章とは効果的なコントラストを見せています。第4楽章冒頭のピアノによる4分音符の流れるようなメロディーは、カノン形式で、すぐ後にヴァイオリンが続きます。2つの楽器は全体を通してカノンを先導する立場を交替で受け持ちます。ソナタは活気に満ちて、エレガントに終わります。
2005年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
プロコフィエフ:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番ヘ短調 Op.80
セルゲイ・プロコフィエフ
(1891年ウクライナ/ソンツォフカ生まれ;1953年ロシア/モスクワにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番へ短調 Op.80 (1936-1946年作曲)
第1楽章:Andante assai
第2楽章:Allegro brusco
第3楽章:Andante
第4楽章:Allegrissimo
セルゲイ・プロコフィエフ(1891―1953年)は、『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番ニ長調 Op. 94a』を1944年に完成し、その後1946年に『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番へ短調 Op. 80』を完成させました。一見作品番号が年代に反しているようですが、実は、ヘ短調のソナタの構想を 1936年頃に始めていたので、完成した年に関係なく、へ短調のソナタの方を『第1番』としたのです。
プロコフィエフは、まだ若い頃の1918年に、ロシア革命の混乱を避け、彼の作品が支持され、よりよく受け入れられそうな芸術環境を求めて、母国を後にしましたが、1936年にソヴィエト市民として残りの人生を過ごすためソ連に戻ってきました。
幼少の頃のプロコフィエフは、帝政ロシアの特権階級の家庭で育ちました。作曲と指揮とピアノを専攻したサンクトペテルブルク音楽院では反抗的と言われ、当時院長であったグラズノフから同情的な支持を得たにもかかわらず、手に負えない問題児で嫌がられました。しかしながら、彼の作品はそれなりの話題を呼び、作曲家として、またピアニストとしての道を歩むことができました。彼はやがてストラヴィンスキーの『春の祭典』に惹かれ、偉大なロシア・バレエ界の興行師のディアギレフと知り合いになりました。
革命の気運が高まり、ロシアは不安定な状況となって、プロコフィエフはペテルブルクの社会環境が、自分の音楽が受け入れられるにはふさわしくないと思うようになりました。その決意はストラヴィンスキーやディアギレフといった西洋化したロシア人に啓発されたものであったようです。プロコフィエフは、自身の音楽語法に何らかの刺激となり、自分の音楽を受容してくれる安住の地を求めました。シベリア・日本を経由して、ロシアを離れ15年間、主としてアメリカとパリで暮らしました。しかしながら、1930年代初期、彼はたまらなく母国に帰りたくなります。彼は快適ではあるものの、故郷のロシアに思いを馳せながら生活を続けるのが嫌になったのでしょう。そして何よりも二人の子供達にロシアで幼年時代を過ごさせてやりたいと思ったようです。
その時点では、プロコフィエフは、ソヴィエト連邦の政治的状況が彼の芸術的・創造的環境に与える影響をあまり深く考えなかったように思われます。彼がナイーヴだったためか、政府が聴衆に彼の音楽を聴くことを禁じるかもしれないとか、創作活動を干渉されるかもしれないといった現実を直視しませんでした。彼がロシアを去り、後にまたロシアに戻る決意をした理由は、音楽的な自由・発展と理解を求めたからでしたが、その結果は皮肉なことに、彼の晩年の創作活動を抑圧するものでした。それでも彼はオペラやバレエ音楽を中心に作品を書き続けましたが、創作活動の変更を余儀なくされることが多かったようです。
プロコフィエフが戻った1930年代のソヴィエト連邦はスターリン主義の真っ只中でした。芸術的観点からすると、この時代は創作活動が最も厳しく制限されていた頃で、ソヴィエト共産党が芸術関係の全ての側面を監視下におさめていました。形式主義の音楽はブルジョアと非難され、検閲されました。ソ連邦作曲家同盟が演奏を認可する公式な権限を持ち、その指導方針がプロコフィエフやショスタコーヴィチといったソヴィエトの作曲家に多大な影響を与えました。例えば、ショスタコーヴィチの『ヴァイオリン協奏曲第1番』やオペラ『鼻』のような作品は、政治的な抑圧を受けました。プロコフィエフのソヴィエト帰国直後の作品にはこれらの抑圧の影響はあまり見られませんが、徐々にその影響は明らかになっていきます。官僚主義支配が、彼の特徴であった大胆な作品の制作を妨げました。“スターリン主義に妥当な、ふさわしい”音楽に書き直しを迫られることもありました。
1940年代には、転倒と脳震盪が原因でプロコフィエフの健康状態は悪化し、『ヴァイオリン・ソナタ第1番』を完成させた1946年頃には、ほとんどモスクワ近郊の別荘に閉じこもっていました。この作品自体には彼の健康不良による弱々しさは全く見られません。むしろ、機転、皮肉、不気味、活気、回想への耽溺といった特徴が感じられます。この作品全体が感情的色彩に富み、抒情的で、演奏上高度な技術が要求されます。プロコフィエフはこの作品について次のように述べています。「ソナタ第2番よりも敬虔な雰囲気のある曲で、第1楽章のアンダンテ・アッサイは、重厚な性質を帯び、活発な動きを見せながらも第2の主題が現れる第2楽章のアレグロの序奏という役割を果たす。第3楽章はゆっくりとした、穏やかな、やわらかな感じの楽章で、最終楽章は速いテンポで複雑なリズムで描写されている」(ロフト著『ヴァイオリンと鍵盤楽器、二重奏曲のレパートリー』第2巻、288頁から引用)。
また、プロコフィエフの伝記を書いたイスラエル・ネスティエフによるこの曲についての次のような視覚的イメージに満ちた叙述は注目に値します。「祖国の運命を詠む古代吟唱詩人の瞑想、闘争中の勢力の容赦ないぶつかり合い、若い女性の嘆きの詩的なイメージ、武装したロシアの力をたたえる歌、人々の自由と力の歓呼の声」。
この曲は1946年10月にダヴィッド・オイストラフとレフ・オボーリンによって初演されましたが、プロコフィエフは彼らにこのソナタの第1楽章の終わりは「墓場に吹く風」のように演奏するよう指示しました。この同じ旋律が4楽章の最後にもう一度姿を現わします。これは、あたかもスターリン統治下のソヴィエトにおける音楽の限界をプロコフィエフが暗示しているようです。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第1番ニ長調 Op.12ー1
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第1番ニ長調 Op. 12-1 (1797-1798年作曲)
第1楽章: Allegro con brio
第2楽章: Tema con variazioni (Andante con moto)
第3楽章: Rondo: Allegro
ベートーヴェンはピアノとヴァイオリンのためのソナタを1797年から1813年の間に10曲書きました。それ以前にモーツァルトもハイドンも2つの楽器のためのソナタを書いていますが、いずれもピアニストの立場から書かれたもので、ヴァイオリンよりピアノに比重を置いた作品でした。ベートーヴェンは、先例に従ってピアノとヴァイオリンのためのソナタを作曲しましたが、ヴァイオリンとピアノが対等に影響しあえるように作曲された点が、その頃の形式とは異なっていました。
しかしながら、ピアノ・パートはベートーヴェンの『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ』全曲で決定的な役割を果たします。ベートーヴェン自身がピアノの名手だったので、ピアノの新しい可能性を継続的に探り続けました。その頃、ピアノはちょうどベートーヴェンの要求にも応えられるような楽器へと改良が進んでいました。したがって、現代のヴァイオリニストがこれらのソナタを弾く場合は、ベートーヴェンの時代のピアノ的な音、色彩、アーティキュレーションを考慮に入れ、演奏することが望ましいと言えます。ベートーヴェンのソナタにおけるピアノ・パートは、ヴァイオリニストが作品を解釈する上で、不可欠な最も重要な道標となっています。ベートーヴェンの作品には新しいことをやり遂げるときの抵抗感と、達成感がしばしば感じられますが、この特性を聴いている人に十分に伝えなくてはなりません。
『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第1番ニ長調』は、恩師の一人であるアントニオ・サリエリに献呈されました。ベートーヴェンは1792年にハイドンに師事するため初めてウィーンに行きますが、ハイドンとの師弟関係はあまり長続きしませんでした。ベートーヴェンの気難しい愛敬のない性格とハイドンの度重なる海外旅行によるすれ違いで、理想的な親密で友好的な師弟関係を築くことができなかったと考えられます。その結果、ベートーヴェンはアルブレヒツベルガーやサリエリなどに引き続きウィーンで師事することになります。
ハイドンから受けた形式的な教育は限られた期間に行われたものでありましたが、ベートーヴェンはハイドンに感化され、最初の交響曲やカルテットを書きました。またハイドンの『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ』は、ベートーヴェンが同種のソナタの作曲に取り組むのに重要な役割を演じました。また、ベートーヴェンが面倒を見ていたクールラント(現ラトヴィア)出身のヴァイオリニスト、カール・アメンダの強い影響もありました。
1797 年から1798年にかけて作曲された『ソナタ第1番』は3つの楽章から構成されています。その頃にはもう既に聴覚の異常な徴候が確実に現れており、精神的にも極端に不安定で、医学的にも精神異常の状態でしたが、この事実に反するように、全体的に喜びに溢れた、生き生きとした元気のよい曲です。アレグロ・コン・ブリオ(生き生きと速く)、アンダンテ・コン・モート(動きをつけてやや遅く)、アレグロ(速く)と続きます。
この作品は力強いユニゾン(ピアノとヴァイオリンが同時に同じ音を演奏する)で始まり、その後すぐに最初はヴァイオリンによって、次にピアノによって、美しい調べが奏でられます。そして、流れるような速い音符や突然現れる緊張感のある和音が、だんだん短い間隔で登場し、あたかも2つの楽器が会話を楽しんでいるようで、興奮していく様子が伝わってきます。しかし、ベートーヴェンはユーモラスにその前進する動きを一時止め、次のセクションでは、ピアノが前よりも多少穏やかにメロディーを奏で始め、ついには軍隊に魅了されたかのような堂々とした和音へと導かれ、勢いのある16分音符が続きます。次のセクションでは、楽章の中間部では珍しく調がヘ長調に変わり、耳覚えのあるピアノのダイナミックな和音で始まり、軍隊行進曲を髣髴させます。この部分は長くは続かず、勝ち誇ったようにオープニングの音楽に戻り、この楽章はほぼ同じように繰り返されます。
第2 楽章はテーマとそのテーマに基づいた4つのヴァリエーションからなります。旋律がピアノによって奏でられ、ヴァイオリンが追随して伴奏をするパターンとその逆の場合があります。第1ヴァリエーションはピアノが旋律を弾き、ヴァイオリンが伴奏を担当しますが、第2ヴァリエーションは立場が逆転し、ヴァイオリンが旋律を奏で、ピアノが伴奏に徹します。第3ヴァリエーションでは、ピアノもヴァイオリンもバランスよく使われています。テーマと第1、第2ヴァリエーションはイ長調で書かれていますが、この第3ヴァリエーションだけイ短調です。最後の第4ヴァリエーションで長調に戻り、到達感を与えます。
最終楽章のアレグロは8分の6拍子のロンド形式をとっています。テーマがオフビートのスフォルツァンド(強音)とシンコペーションで陽気に奏でられるのが特徴です。この特徴はベートーヴェン後期の作品でより顕著になっていきます。最終楽章の中間部は第1楽章と同様にヘ長調です。ピアノとヴァイオリンが、旋律と伴奏という役割を交互に果たしながらも、幸福感に満ちて踊りたくなるようなこの楽章の性質は失われることはありません。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第3番変ホ長調 Op.12-3
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第3番変ホ長調 Op.12-3 (1797-1798年作曲)
第1楽章:Allegro con spirito
第2楽章:Adagio con molta espressione
第3楽章:Rondo: Allegro molto
ベートーヴェンの時代になっても、ピアノとの組み合わせによる器楽曲のソナタの場合、ピアノ以外の楽器が伴奏の役割を担い、ピアノがメインで華やかさを前面に出すような曲が一般的でした。モーツァルト(1756-1791年)もハイドン(1732-1809年)も、特に初期の作品にはピアノとヴァイオリンのためのソナタが多く見られ、その中ではピアノを重視する姿勢がはっきりと表れています。
ベートーヴェンがソナタを書き始めた頃には、二つの楽器はかなり均等に取り扱われるようになっていました。にもかかわらず、完成後まもなく出版されたOp.12の初版には、『ヴァイオリンつきのハープシコードまたはピアノのためのソナタ集』と書かれていたことは注目に値します。
ベートーヴェンの音楽言語は明らかに鍵盤を中心に考えられています。その頃の伝統に従えば、ピアノ・パートが重視されていて当然ですし、彼自身がピアノの達人であったという事実も影響しているに違いありません。確かに、ベートーヴェンは20代半ばから音楽の都ウィーンでピアニストとして活躍していました。こうした理由から、ベートーヴェンのピアノとヴァイオリンのために書かれたソナタ10曲の全てにおいて、ヴァイオリンのメロディーは、鍵盤の音を念頭において解釈されなければならないのです。
ベートーヴェンの人生は、聴覚の障害、気分の浮き沈みや気難しさが、天才振りとともに今日ではよく知られています。確かに、彼の烈しい気性は数多くの作品の中で感じられますが、『Op.12』のように、面白くてやさしくて冒険好きといった彼の別の一面が感じられる作品もあります。
『Op.12』は3つのソナタ(『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第1番~第3番』)のセットで、1797年から1798年にかけて作曲され、ベートーヴェンの師の一人でウィーンのハプスブルク宮の楽長という要職に就いていたアントニオ・サリエリに捧げられました。『ピアノ・ソナタ第4番』や『ピアノ・ソナタ第7番』、『弦楽三重奏 Op. 9』、『弦楽四重奏 Op.18』、『ピアノ協奏曲第1番』などの作品が同じ頃に作曲されており、ウィーンで師事していたことのあるフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの影響が見られます。このソナタは若々しい陽気さが全編で感じられ、大変印象的です。
このソナタはピアノによって演奏される第1主題で始まります。第2主題はヴァイオリンによって奏でられ、音楽は自然に流れていき、陽気な雰囲気とエネルギーに溢れています。続くアダージョはハ長調で書かれており、2つの楽器が交互に美しいメロディーを奏でていきます。なめらかで美しいメロディーは、気取りもなく率直な印象を与え、伴奏の牧歌的なリズムが効果的に使われています。
ロンドの主題は、覚えやすく、華やかで、師であるハイドンも好んだハンガリー的な雰囲気が漂っています。2つの楽器が色々な主題を入れ替り立ち替り演奏して、まるでお互いふざけあっているかのようです。至福、希望、喜びに満ちた20分あまりのこのソナタの最後を表現するのに”愉快”という言葉が一番ふさわしいように思われます。
2005年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第5番ヘ長調 Op.24『春』
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第5番ヘ長調 Op. 24『春』(1800-1801年作曲)
第1楽章:Allegro
第2楽章:Adagio molto espressivo
第3楽章:Scherzo: Allegro molto
第4楽章:Rondo: Allegro ma non troppo
ベートーヴェンは自然をこよなく愛し、特に森の中や星空の下にいると幸せに感じ、またインスピレーションも沸きました。彼は、自然の美しさから、より一層、神の存在を強く感じました。この穏やかな、牧歌的な、ロマンティックでやさしい一面は、極度の緊張感や激情的な雰囲気といったベートーヴェンの音楽の一般的なイメージとは対照的です。しかし、こうした一面は、彼の全作品を通しても感じられますし、作曲家の複雑な性格を理解する上で重要な要素と言えるでしょう。
レナード・バーンスタインは、「ベートーヴェンは、次にどの音がくるべきか熟知していた作曲家である」とその天才振りを語っています。確かに、ベートーヴェンのいかなる作品を聴いても、彼がはっきりと確信を持って一音一音書いていたことに気づきます。彼の音楽には確実な方向性があり、驚くほど自然に音楽が高まっていきます。ベートーヴェンの音楽が、奇跡的で、神聖なものと言われる所以でしょう。したがって、誰にも彼の音楽を模倣することは不可能で、横に並び立つ者もおらず、独自のカテゴリーに位置していると言えます。
ソナタOp.24の『春』は、全部で10曲あるベートーヴェンのピアノとヴァイオリンのためのソナタの中で5番目にあたります。1800年から1801年にかけて作曲され、Op.23の『ソナタ イ短調』とペアで、ベートーヴェンの最もよき理解者でパトロンであったウィーン在住のフライズ・モリツ公爵に献呈されました。この2つのソナタは、もともとOp.23-1とOp. 23-2として作曲されたものでしたが、記録係の誤りで、この『春』のソナタが作品24となってしまいました。
このソナタは、ベートーヴェンのピアノとヴァイオリンのためのソナタの中で最も人気のある作品の一つで、一度聴けば耳に残るような大変覚えやすい曲です。曲想は新鮮で、喜びと希望に満ち溢れており、サブタイトルの『春』にぴったりと合っています。曲全体を通じて、メロディーが直接的で、シンプルで優雅です。またユーモアを感じさせる瞬間や、ベートーヴェンには実は愉快な一面もあったことを思い起こさせるような瞬間もあります。
『ソナタ第7番 Op. 30-2』と『ソナタ第10番 Op. 96』と同様に、この『春』は、4楽章形式をとった作品で、ヴァイオリンによって奏でられる大変印象的なヘ長調のメロディーで始まります。ピアノが先行して奏でる第2主題は、ヴァイオリンの第1主題よりも力強く、確固としていて、第1楽章では、2つの対照的な主題が進行していきます。変ロ長調のゆっくりとした第2楽章は、シンプルで、ヴァイオリンとピアノが交互に少しずつ異なるヴァリエーションをつけた主題を流れるように奏でます。第3楽章は、スケルツォとトリオで、ヴァイオリンとピアノが、それぞれ相手の反応を楽しむかのように、まるで鬼ごっこでもしているかのようです。遊び心のあるおもしろいリズムが、この楽章のふざけているような印象をさらに強くしています。最終楽章はロンド形式で、3つのエピソードに続いて、叙情的な主題が現れます。楽天的な雰囲気が自然に感じられるこの楽章で、付点のリズムがベートーヴェンの創意に富んだユーモア感を具現しています
2004年1月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第6番イ長調 Op.30ー1
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第6番イ長調 Op.30-1(1802年作曲)
第1楽章: Allegro
第2楽章: Adagio molto espressivo
第3楽章: Allegretto con variazioni
1802年、ベートーヴェンはウィーン郊外のハイリゲンシュタットで数ヶ月を過ごしました。前年に、ごく親しい一部の友人にのみ打ち明けていた聴覚障害が深刻化しつつありましたが、作曲家、そして、ピアニストとしての彼の名声は着実に高まっていました。精神的に不安定で、耳が聞こえなくなってしまうことへの恐怖心の中で、自分自身に落ち着きを取り戻すためにハイリゲンシュタットに滞在していましたが、その間も作曲活動は続けられ、交響曲第2番やOp.30-1のピアノとヴァイオリンのためのソナタを含むいくつかの器楽曲が書かれました。
当時のロシア皇帝アレキサンダーに捧げられたこの曲は、最近ではほとんどコンサートで取り上げられていませんが、この曲の愛好者は、ベートーヴェンの室内楽曲の中で最も美しい作品だと評します。この曲では、演奏者が互いをよく聴きあうこと、そして、細部にまで細やかな注意を払うことが要求され、ベートーヴェンの音楽の典型とも言える激情のほとばしりとは明らかに異なった、大変優美な性質を持っています。
この作品は3つの楽章で構成されており、作品全体を通じて優雅さ、穏やかさ、やさしさ、そして、気品が感じられます。この曲では、演奏上の難しさを見せることなく、ピアノもヴァイオリンも同等に脚光を浴び、曲の美しさだけに注目が集まるような作品です。激しい曲想でよく知られているピアノとヴァイオリンのためのソナタ『クロイツェル』は、この作品が書かれて1年以内に同じイ長調で作られていますが、Op.30-1の特徴である牧歌的なスタイルは、ピアノとヴァイオリンのためのソナタの中で最後に作曲されたOp.96の穏やかな性質にヒントを得たピアノ・ソナタ第15番二長調Op.28『田園』の雰囲気によく似ています。興味深いのは、ベートーヴェンはもともとこの曲(Op.30-1)の第4楽章として考えていた楽章を『クロイツェル』の最終楽章に使ったことです。したがって、Op.30-1は3楽章のソナタとして出版されました。ベートーヴェンは、第2楽章によく使用したテーマとヴァリエーションの形式をこの曲では最終楽章に用いましたが、交響曲第3番『エロイカ』の最終楽章や独立して演奏される名曲の中でも同様にこの形式をうまく使用しています。
実際に、ベートーヴェンは最終楽章だけをテーマとヴァリエーションの形式に則り作曲しましたが、他の2つの楽章も漠然とヴァリエーションの形式になっており、彼がソナタ形式とロンド形式という作曲の慣習に長けていたことを象徴しています。第1楽章では、オープニングのピアノの低音に見られるリズムを重要視していることが、ヴァリエーションの構想からはっきりと見てとれます。このソナタはピアノによる高貴なテーマで始まります。このモティーフ(例)は、楽章全体で見られますが、冒頭の重要な役割に加えて、展開部の始まりや終わりに登場し、主要なテーマが戻る道筋を巧みに整えているような感じです。このリズムは、楽章の最後でも現れます。
(例1:第1楽章冒頭 小節番号1~2)

![]()
(例2:第1楽章 小節番号83~87)

(例3:第1楽章 小節番号247~249)

第2 楽章は、ロンド形式のコンビネーションで、A-B-A-C-Aの形式をとり、ベートーヴェンはヴァイオリンとピアノに平等に役割を与えるように特別な注意を払い、ヴァリエーションの手法にスポットライトが当たるようになっています。この形式では、忘れがたい旋律がヴァイオリンによって奏でられ、すぐにピアノによって繰り返されます。この組み合わせによる旋律はこの楽章中にさらに2回現れますが、その間には対照的な要素をもった部分が挿入されています。それぞれの部分は表面的には満ち足りていますが、まるで聴衆の関心をつなぐためかのように冒頭のテーマのヴァリエーションに戻ります。さらに、全ての重要な旋律の描写は2度行われ、通常最初はヴァイオリンによって、続いてピアノによって、装飾された形で繰り返されます。繰り返し部分を装飾するという伝統はオペラから来ており、この楽章の旋律のいくつかはイタリアのオペラに出てきそうなシンプルなメロディーに似ています。ベートーヴェンの一般的な“英雄”のイメージに相対して、満ち溢れた愛情と失われることのない情熱を持ち合わせたこの楽章は、叙情的な旋律を書く彼の別の才能を顕示しています。
最終楽章は、テーマとヴァリエーションの形式で、優雅なソナタにふさわしくシンプルなエンディングです。洗練されたドイツ舞曲の特徴を帯びたテーマで始まり、次にそのヴァリエーションが6つ続きます。最後のヴァリエーションは、Allegro, ma non tantoと表示され、劇的なクライマックスでグランド・フィナーレを飾ることはありませんが,むしろ、前向きで満ち足りた気分で幕を閉じます。
2004年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第7番ハ短調 Op.30-2
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第7番ハ短調 Op. 30-2 (1802年作曲)
第1楽章:Allegro con brio
第2楽章:Adagio cantabile
第3楽章:Scherzo
第4楽章:Finale: Allegro-Presto
18世紀や19世紀の頃の作曲法理論では、特定の調には独特の曲想があると考えられていました。例えば、ハ短調の場合は“悲劇、大きな不幸、英雄の死”という雰囲気があると言われていました。
これは1802年に作曲された『ソナタ第7番ハ短調Op.30-2』にも当てはまります。この作品は、ヴァイオリンとピアノのために書かれたデュオの名作の中でも元祖的存在と考えられています。ベートーヴェンは、同時期に7つの器楽曲を手がけていますが、その中で、このソナタと他の3つの作品(悲愴ソナタ、弦楽三重奏、ピアノ協奏曲)がハ短調で書かれている事実は注目に値します。難聴が深刻化していたベートーヴェンの心の動揺が、ハ短調の特徴である陰鬱で不吉とも言えるこの曲の雰囲気にぴったりと合っているように思われます。
第1楽章の冒頭の控えめなオクターブが明確に不吉な運命を予測し、すぐに激しくかきたてるような軍隊マーチに似た対照的なテーマにとってかわり、感情の爆発につながります。悲劇的な美しさとふざけたような旋律という相反する要素の混合は、偉大な力と結束力を生み出し、抒情詩のような雄壮な作品に仕上がっています。
2つの楽器はお互い補い合うような関係を終始保っていますが、色調としては、ピアノ寄りに感じられます。しかしながら、両パートの重要性という意味では、全く平等に扱われていると言えます。
ゆっくりとしたテンポの第2楽章のAdagio cantabileは、首尾一貫して穏やかな感情があふれ出ており、歌のようで心が動かされます。ピアノで弾かれる最初の牧歌的なテーマが様々な形に変化し、見え隠れします。ソナタの中で最も静かなこの楽章でさえも、突然の感情の爆発が2度もあり、上昇音階が不意に出てきます。しかし、その衝撃も瞬時で、叙情的なテーマが戻ってきます。
第3楽章のリズミカルなScherzoは、3拍子で書かれており、第1楽章の軍隊マーチを思い起こさせます。特に、真ん中のトリオの部分では、ドイツの田舎の踊りのような雰囲気があります。その前後の部分では、装飾音符がユーモアといたずらっぽさをつけ加えています。
最終楽章では、苦悶と恐怖に染まった雰囲気が戻ってきます。この楽章のテンポは息もつけないほど速く、突然の感情の爆発や休止は、テンポが速いだけに抜群の効果をあげています。Prestoと書かれたコーダでは、熱狂的気運が高まり、ハ短調の主和音でこの曲は終わり、不安や神経質な雰囲気が余韻として残ります。
2005年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第9番イ長調 Op.47『クロイツェル』
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第9番イ長調 Op.47『クロイツェル』(1803年作曲)
第1楽章:Adagio sostenuto-Presto
第2楽章:Andante con variazioni
第3楽章:Finale: Presto
ベートーヴェンはこの曲の完成を急がなくてはなりませんでした。実際に、デットラインを過ぎてしまい、1803年にウィーンで行われた初演の夜の幕が開くぎりぎりまでこの曲を書いていました。ピアノは作曲家自身が弾き、ヴァイオリンはジョージ・ブリッジタワーの演奏で初演されましたが、最初の2つの楽章は抜けている部分がところどころあり、大まかに書かれた手書きの楽譜をもとに即興的に演奏しなければなりませんでした。しかしながら、この曲は“クロイツェル”ソナタというサブタイトルをつけて出版され、ロシアの文豪トルストイを筆頭に偉大な人々に強い影響を与え続けています。
トルストイは1888年に“クロイツェル”ソナタの演奏を聴き、刺激を受け、同名の小説『クロイツェル・ソナタ』を執筆しました。この小説は、ある家庭を舞台に精神的・肉体的欲望の葛藤を描いたもので、夫が妻を殺害するという悲劇です。
“クロイツェル”ソナタは類稀なる名曲です。速いパッセージや激しい旋律、ピアノとの掛け合いが多く、演奏をする際には、私はいつも純然たるエネルギーに圧倒されると同時に激情を抑えるのに苦労します。技術的にも高度なテクニックが要求され、演奏者には精神的にも体力的にも極度の緊張が強いられます。
第1 楽章は、ベートーヴェンが手書きの楽譜に書き入れた「協奏曲形式で書かれた、華々しく(ベートーヴェン自身の手によって手書きの楽譜から削除される)、いわば協奏曲のようなピアノとヴァイオリンのオブリガート・ソナタ」という記述が最もよく表現しています。実際に、2つの楽器が対等に、生き生きと刺激的にコンチェルトのように演奏されますが、同時に室内楽特有の微妙な協調的な感性の繊細さも兼ね備えています。
序奏部のAdagio Sostenuto(遅く、音を十分に保って)は、合唱のようなフレーズで始まり、冒頭はヴァイオリンで、続いてピアノで奏でられます。冒頭のヴァイオリンの奏でるフレーズだけは明らかにイ長調ですが、この楽章のその他ほとんどの部分が短調で、タイトルにつけられている調名とは矛盾しています。序奏部に続くPresto(速く)では、調号がこれまでのイ長調(C(ド)とF(ファ)とG(ソ)の音にシャープ)からイ短調(シャープもフラットもなし)に変わります。プレスト冒頭の主題はヴァイオリンに始まり、次にピアノが同じフレーズを弾き、ピアノの小カデンツァのようなアルペジオで完結します。この楽章は、平穏をほのめかすような瞬間がいたるところにありながらも決してそれらは完全な平穏ではなく、ただ単に興奮がおさまらない瞬間を一時停止させているに過ぎません。この楽章の最後は激しい怒りで終わります。
第2楽章はAndante con Variazioni(やや遅く、変奏曲)で、4つの変奏曲からなっており、主にヘ長調です。この楽章は“ゆっくり”の楽章とみなされていますが、オフビートやピチカートやトリルの連続などを取りこむことによって、ベートーヴェンは楽章全体にユーモアを与えています。また、一般的には“速い”音符と考えられている16分音符、32分音符、64分音符が駆使されていますが、ベートーヴェンは楽章全体を漂う透明感溢れる美しさを維持するような音質、ゆとり、静けさを演奏に求めています。
最終楽章はPresto(速く)で、もともとは一年前に別のピアノとヴァイオリンのためのソナタ『イ長調 Op.30-1』の最終楽章として書かれたものを転用しています。以前に作曲した曲を引用し、変奏曲を作り上げ、“クロイツェル”ソナタを完成させました。ピアノの単純でありながら持続的で力強いイ長調の和音の後、ヴァイオリンが弾き始め、この楽章全体を支配する華やかで軽快な雰囲気を確立します。イタリアの民間伝承で、毒グモに噛まれた傷を癒すための非常にテンポの速い踊りと言われているタランテラと同様の形式です。タランテラの起源は決して楽しい出来事ではありませんが、この第3楽章は、陽気で、機知に富んでいて、軽快な曲想で、第1楽章の激しく、ドラマティックで、荒れ狂う特徴とははっきりとした違いが認められます。第3楽章は2つの楽器が一緒にダンスをするかのようにごく自然に優雅で、理性を保ちつつも喜びに満ちて輝かしい終焉を迎えます。
ブリッジタワーはプリンス・オブ・ウェールズに仕えていたヴァイオリンの名手で、この曲が初演されたときは、ベートーヴェンとは友好的な関係にありました。しかしながら、同じ女性に夢中になってしまったことから、二人の仲に亀裂が入り、このソナタが出版されるときには、ベートーヴェンは怒り狂い、ブリッジタワーではなく、別のヴァイオリンの名手、ルドルフ・クロイツェルに献呈しました。クロイツェルは、世界中のヴァイオリニストの間では『42の練習曲』を作ったことで知られていますが、このソナタを献呈されても演奏することはありませんでした。今日では、この作品は、数多いヴァイオリンとピアノのためのソナタの中でも最も重要な作品と一つとなっています。恐れられ、愛され、演奏する者にとっては、人の近づき難い神々しいオリュンポス山(ギリシャ神話の神々が住んだところ)のような存在です。
2003年1月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ベートーヴェン:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第10番ト長調 Op.96
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(1770年ドイツ/ボン生まれ;1827年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第10番ト長調 Op.96
第1楽章:Allegro moderato
第2楽章:Adagio espressivo
第3楽章:Scherzo: Allegro
第4楽章:Poco allegro
世界のどこで演奏しても、ベートーヴェンの名前と有名な作品の知名度には驚かされます。彼が名声を集めた理由を探ると、その広範に及ぶ好奇心と研究熱心な本性にたどり着きます。だからこそ、彼の人生をもとにした映画が何本も作られたり、『スヌーピー』のような漫画からクリムトやウォーホールの絵画に至るまで幅広い分野に影響を与え、モーツァルト同様にベートーヴェンは多くの専門家の研究対象となっています。
ベートーヴェンの作品や人柄について要約するとすれば、彼が慣習にとらわれない人物だったことです。音楽的側面から言えば、彼は作曲法の新しい基準を作り上げ、クラシック音楽のレベルを変えました。それまでの作曲家の多くが受け継いできた伝統の枠組みの中で創作活動を行っていたのに対し、ベートーヴェンはこの伝統の領域を越えて傑出した作品を生み出しました。
ベートーヴェンはピアノとヴァイオリンのためのソナタを10曲書きました。ベートーヴェン以前に書かれたものにはモーツァルト、それ以降に書かれたものに、ブラームスやシューベルトがあります。モーツァルトの19のソナタに比べると、ベートーヴェンのソナタは、ピアノとヴァイオリンがより同等に扱われています。二人ともピアニストの立場から作曲していますが、モーツァルトも含めた初期古典派の作曲家がピアノの補足的役割しかヴァイオリンに与えなかったのに対して、ベートーヴェンは、この古いスタイルを脱却し、ヴァイオリンにより重要な役割を与えました。
ベートーヴェンが全盛期のときはピアニストとしても活躍しました。その頃はちょうどピアノに新しい機能が加わり、演奏技術も向上しようとしている時で現在のピアノに大変近いものになりつつありました。その結果、現代のヴァイオリニストがこれらのソナタを弾く場合は、ピアノ的な音、色彩、アーティキュレーションを考慮に入れなければいけません。また、ピアニストも自分がやりたいこととベートーヴェンの時代にできたこととのバランスを考える必要があります。なぜなら現在では簡単にできることでも、1800年代に遡ると技術的に難しかったというようなこともあるからです。とりもなおさず、ベートーヴェンの意図することをたがわずに解釈することは今も重要であることにかわりありません。ベートーヴェンの作品には、しばしば難しいテクニックを弾きこなすための努力の跡が聴かれますが、これは彼の音楽に見られる独特の要素の一つと考えられています。
ベートーヴェンがまだ10代だった1787年のはじめ頃、彼は自分の内面の変動を感じ始めます。早くは1796年に聴覚に異常を感じ、1801年にはその問題は確実なものとなり、やがて耳が聞こえなくなります。もともとうつ病の傾向はありましたが、ますます怒りっぽくなり、精神的にも不安定になったのは、病状が進行していく恐怖からではなかったかと思われます。最近まで聴覚障害の原因が子供の頃に受けた父親からの虐待によると言われていました。彼の父親はお酒を飲むと、息子に長時間ピアノを練習させては暴力的罰を与えていたようです。現代医学の研究では、梅毒が原因なのではないかという仮設もあります。いずれにせよ、いまだにベートーヴェンの聴覚障害の原因やその死因は謎に包まれたままです。彼の聴覚障害が彼の情緒不安定に拍車をかけたことが、彼が書いた手紙や、特に兄弟に宛てたハイリゲンシュタットの遺書を読むとうかがわれます。
1798年から1812年にかけて書かれた10曲のピアノとヴァイオリンのためのソナタのうち第10番は最ものどかで抒情的な雰囲気をもつ曲です。ベートーヴェンの熱狂的なパトロンの一人であったルドルフ大公に捧げられ、1812年にルドルフ大公のピアノ、ピエール・ロードのヴァイオリンで初演されました。
第1楽章、アレグロ・モデラートは、4分音符-2つの8分音符-4分音符という3拍が、まずヴァイオリンによって奏でられ、次にピアノによって、同じ3拍が繰り返されて、この曲は始まります。この楽章全体は新しい違うメロディが前のメロディから派生するという規則にのっとって書かれています。全てのセクションが次から次へ流れるようです。特に目立つのは2番目のテーマで、遠くで軍隊が行進している感じを思わせます。
第2楽章のアダージョ・エスプレッシーヴォは賛美歌のような響きがあります。この楽章はベートーヴェンの室内楽の中で最も美しいゆったりとした楽章の一つと考えられています。演奏者は抒情的にフレーズを壊さないように演奏するため、ゆっくり息をします。第3楽章は軽快な3拍子のスケルツォではさまれた3つの部分で成り立っています。
最終楽章はポコ・アレグレットと表記されていますが、流れるようにフレーズからフレーズ、そしてヴァリエーションからヴァリエーションへとつながります。楽章の中程にアダージョ・エスプレッシーヴォがありますが、これは第2楽章と同様に賛美歌のようで抒情的です。この部分はカデンツァのような装飾が施されています。この楽章のテーマが再び奏でられるところは、次のヴァリエーションへ移行する前の断章的な間奏曲で、意外にも変ホ長調です。聴衆が、何が展開しているのか理解しようとしている間に、次のヴァリエーションが始まり、16分音符が間断なく弾かれます。そして、突然止まり、カノン形式のヴァリエーションにかわり、もとのテーマに戻ります。しかし、これで曲が終わるわけではありません。ポコ・アダージョが短い刺激的な8小節のプレストによって突然中断され、最後はト長調で終わります。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ヘンデル:ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ長調 Op.1-15 (HWV373)
ジョージ・フレデリック・ヘンデル
(1685年ドイツ/ハレ生まれ;1759年イギリス/ロンドンにて死去)
ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ長調 Op.1-15(HWV373)
ジョージ・フレデリック・ヘンデル(1685-1759年)は、生前はオペラ作曲家として大変有名で、生涯に45曲以上を手がけました。しかし、現在では、イタリア様式のバロック音楽の作曲家として、『メサイア』や『水上の音楽』などが最も知られています。ドイツ中部のハレという町で生まれ、後半生はイギリスに帰化し、ロンドンで亡くなりました。ヘンデルの父親は、音楽家になりたいという息子の希望には、職業として安定性がないという理由から猛反対しました。父親の夢は息子が法律の道へ進むことでしたが、ヘンデルの楽才を確信した父親の友人である公爵の強い説得で、一般の学業を続けることを条件に、仕方なく息子に音楽教育を受けさせました。
ヘンデルはハレで教育を受けていた幼少期から、多声音楽や和声、オルガンやハープシコード、ヴァイオリンやオーボエのレッスンで音楽の才能を発揮しましたが、大学では父親の希望通り法律を学びました。しかし、卒業後は法律の道には進まず、ハレの教会のオルガン奏者となり、この頃から音楽に全面的に打ち込むこととなりました。
その後ハンブルグに移り住み、1705年には彼のオペラ第1作目『アルミーラ』がハンブルグで上演され大成功をおさめ、作曲家として脚光を浴びました。それ以降、次から次にオペラを作曲し、また聖ヨハネの受難をもとにしたオラトリオも作曲しますが、翌年にはハンブルグを去り、イタリアに向かいます。
その後数年間ヘンデルはイタリアに滞在し、当時のイタリア音楽の巨匠アレッサンドロ・スカルラッティやアルカンジェロ・コレッリらと交流を持ち、イタリア伝統のバロック・オペラの基礎を深めました。この頃ヘンデルはオペラやカンタータやオラトリオを数多く作曲し、イタリア各地の宮廷で高い評価を受けました。
1710年にヘンデルはドイツのハノーヴァー選帝候の宮廷楽長に就任しますが、ほとんどそこでは仕事をせず、ロンドンで過ごしていました。1714年アン女王の死去によりハノーヴァー選帝候がイギリス国王ジョージ1世に即位したため、偶然ながらヘンデルは結局同じ人物に、ロンドンに残って宮廷で仕えることになります。
ヘンデルの『ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ』は、もともと『ハープシコードまたはヴィオラ・ダ・ガンバの通奏低音を伴った、ジャーマンフルート、オーボエまたはヴァイオリンのためのソロ曲集』という15曲セットの作品の一部として出版されました。この作品は“Opus(作品番号)1”とされていますが、最初に作曲されたというわけではありません。ヘンデルの場合、初期の作品を再利用する癖があったため、また出版者が順番を意図的に変えたために、作品番号が作曲された順番と対応しません。
17世紀初頭というと、現代のヴァイオリンの原型となるヴァイオリンの先祖がようやく出現した時代でもあり、ヴァイオリンと鍵盤楽器の作品は斬新なものでした。ピアノの原型である鍵盤楽器がそれから2,3世紀かけて改善され今のようなピアノになっていく一方で、弦楽器は既に現代に使われているものの面影があり、それまでは小さな音しか出なかったのが、旋律を奏でるにふさわしい音が出るように改善されていました。もちろん当時の楽器は、しっかりとした持続音を出すことができ、鳴り響くような現在使われている楽器とは若干違いますし、調弦も全体的に現在のものより低く設定されていたと思われます。
またこの頃音楽的にも変化が見られます。それまでは、音楽は対位法的に書かれ、複数の旋律が独立性をもって重ねられていました。しかしバロックの時代になると、ひとつの歌に従属する伴奏的和声が付けられるようになります。その和声は記号として書かれ、それを基に演奏者が独自のアレンジをする形でしたが、やがてその原則も変わり、従属楽器のためにもメロディが記されるようになってきました。ただ、それはあくまでも旋律と同じ和声に基づいたものでした。
この形式(伴奏を伴いソロが旋律を奏でる)は器楽曲にも用いられるようになりました。ヴァイオリンの音が弦楽器の中では一番人間の声域に近かったので、ヴァイオリン音楽はバロックの音楽の中で重要な位置を占めていたのです。
たとえば、ヘンデルの『ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ』のようなバロック・ソナタでは、旋律はヴァイオリンが担当し、通奏低音は鍵盤楽器や低音の弦楽器(ヴィオラ・ダ・ガンバ等)、またはその両方によって演奏されました。
ヘンデルの作品に限らずバロック・ソナタの場合、楽譜の下段(伴奏部分)を見てみると、演奏される特定の和音構成を示す数字が書きこまれています。鍵盤奏者の楽譜も、時々装飾的あるいは即興的な音符が右手用に示唆されているだけです。具体的に書かれたものは最小限にとどめられています。バロック・ソナタの通奏低音の楽譜は現代のポピュラー・ソングのギターや鍵盤楽器の楽譜と似ています。低音部分は、個々の演奏者によって奏でられる和音の種類が数字で明確に示されているだけで、高音部分は演奏者が作曲者の意図を理解するために装飾的な示唆がなされているだけです。ヴァイオリン奏者も即興的な演奏が求められますが、鍵盤奏者よりは少ないと言えるでしょう。
ヘンデルの音楽は、同時代に活躍したJ.S.バッハと違い、開放的な音楽です。本日演奏される『ソナタ ホ長調Op.1-15』は、テンポの遅い楽章と速い楽章が交互に構成されたバロックの教会ソナタ形式で作曲されています。楽章は、アダージョ、アレグロ、ラルゴ、そしてアレグロと続きます。
このソナタは、第1楽章が簡素な気品をもって始められ、途切れることのない落ち着いた優雅な旋律から、そのまま第2楽章の、楽しい躍動するエネルギーに溢れたアレグロへと続きます。第2楽章は2つのセクションに分かれ、それぞれ繰り返しがあり、演奏者は繰り返しを毎回違うように装飾してもよいとされています。しかも後半は、バロック時代の作曲法にのっとり、属調の変ロ長調で始まっています。第3楽章は、荘厳で憂いがあります。この楽章が楽譜に記載された情報がもっとも少ないだけに、演奏者にとっては最大限自由な創意をもって表現できるところです。最終楽章はジーグ(バロック時代の舞曲)です。第2楽章と同様に、この楽章も2つのセクションに分かれ、それぞれ繰り返されます。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ミヨー:ヴァイオリンとピアノのための『春』 Op.18
ダリウス・ミヨー
(1892年フランス/エクス・アン・プロヴァンス生まれ;1974年スイス/ジュネーヴにて死去)
ヴァイオリンとピアノのための『春』Op. 18 (1914年作曲)
根っからのフランス人であった作曲家のミヨーは、「春」や「復活」というテーマを好んで用いました。この風潮はセザンヌやピカソのような画家の間でも見られます。人間は、原点に戻り、再出発し、復活する必要があるという考えは古代社会から既に存在していましたが、南フランスでは、特に天の恵みによる自然現象が多く見られたので、こうした感覚が研ぎすまされたのかも知れません。ミヨーは生涯、故郷の南フランスの土地を心のよりどころとしていたことがその音楽に現れています。
ミヨーは、膨大な量の作品を残しました。彼の最後の作品は1972年に書かれたもので、作品番号は441となっています。この『春』という作品は若かりし頃の1914年に作曲されたものです。彼の後期の作品には、ジャズの影響やリオ・デ・ジャネイロに公使の秘書として滞在したときに聴いたラテン・アメリカのカーニバル音楽に感化された作品が目立ちますが、『春』は彼の初期の作品ですから、タンポポが咲き乱れるようなうららかな陽気、太陽、海、そして地中海文化の繁栄など、プロヴァンス地方の香りが色濃く、民俗音楽のメロディーにヒントを得て、この魅力的な短い曲は出来上がりました。
8分の5の複拍子で書かれており、流れの中で揺れ動く様子がこの曲の持ち味です。第一次世界大戦が忍び寄る緊張感の高まる中、世の中の惨事や厳しい天候とはかけ離れた、明るく、静穏な、のどかな別世界を想像させます。
2003年11月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
メシアン:主題と変奏
オリヴィエ・メシアン
(1908年フランス/アヴィニョン生まれ;1992年フランス/パリにて死去)
主題と変奏(1932年作曲)
オリヴィエ・メシアン(1908-1992年)は独創的な音楽でよく知られているフランスの作曲家です。メシアンは1908年にフランス南部のアヴィニョンで生まれ、7歳のときに既に音楽的天才ぶりを発揮し、作曲を始めました。ドビュッシーのオペラ『ぺレアスとメリザンド』に深い影響を受けて、将来は音楽家に、作曲家になろうと決心しました。これは10歳足らずの子供としては珍しい職業の選択でしたが、彼の決心は固いものでした。その後、彼はパリ音楽院で学び、大変優秀な成績をおさめ、学生時代の1928年に作品集を初めて出版しました。
メシアンはサン=サーンスやフランクといったフランコ=ベルギーの名だたるオルガニスト・作曲家の系譜の一端に属し、彼の作風にはその影響が色濃く出ています。彼は敬虔なカトリック信者で、音楽家であるためには「神の無限の力に感嘆させられた信者でなければならない」と言っています。彼はパリ音楽院を卒業後、パリにあるサン・トリニテ教会の主席オルガニストに就任し、40年間務めました。
1932年に作曲された『主題と変奏』は、彼の最初の妻でありヴァイオリニストで作曲家のクレール・デルボスに、結婚の贈り物として捧げられた曲であり、メシアン初期の作品で出版されているものの一つです。この曲は一つの主題と5つの変奏曲から構成されています。主題は3つの要素から成る単純な構成で、全部で28小節しかありません。主題は短く簡潔で、明瞭でわかりやすく、3つの要素のうちのまん中の部分は最も表情が豊かです。主題も他の変奏と同様に、未解決で終わりらしからぬ終わり方をします。次の変奏曲への移行を暗示するような、答えが出ない質問のような感覚が残ります。最初の変奏は単純で、主題と同じ構造ですが、テンポは少しだけ速く弾かれます。次に続く3つの変奏では、徐々に主題との関係を認識するのが難しくなっていきます。第2変奏は3声の対位法で書かれており、主題の部分で弾かれた3つの要素が同時に奏でられます。最もきらびやかな響きのある第3変奏は、リズムの対称性が崩れるように拍子が巧みに操作されています。第4変奏は、第3変奏から派生したもので、盛り上がりを見せる最後の変奏への掛け橋となっています。第4変奏の後半部分は、揺れ動きながらもだんだんとテンポが早くなり、タランテラと似ていなくもありません。ピアノは絶え間ない動きを見せ、ヴァイオリンによる主題が断片的に見え隠れします。最後の第5変奏で、主題がもとの形で1オクターブ高い音域でヴァイオリンによって奏でられます。しかし、再び現れるその主題は変奏を経たことで全く性質の異なるものになっています。威厳があり、神秘的で、厳粛な雰囲気がかもし出され、ヴァイオリンが奏でる旋律はピアノの壮大な低い和音の上で舞い上がっているようです。すでに耳に覚えのある要素が物悲しいまでに美しく取り扱われていてロマンティックですが、この曲は完結することなく、あたかも避けられない運命を感じるかのように終わります。
『主題と変奏』は、メシアン後期の作品に見られるような丹念な研究の跡は見られませんが、メシアンに特徴的な音楽的表現のルーツを力強く示しています。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
メンデルスゾーン:ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調
フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ
(1809年ドイツ/ハンブルグ生まれ;1847年ドイツ/ライプツィヒ死去)
ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調(1838年作曲)
第1楽章:Allegro vivace
第2楽章:Adagio
第3楽章:Assai vivace
フェリックス・メンデルスゾーンは子供の頃から才能を発揮し、4歳年上の姉ファニーとともに神童と呼ばれていました。ユダヤ系の裕福な家庭に生まれたメンデルスゾーンは、学問的にも文化的にもその当時最高の恵まれた環境の中で育てられました。彼はドイツの哲学者ヘーゲル(1770-1831年)や詩人のゲーテ (1749-1832年)のような偉人達とも親交を結び、思想的に強い影響を受けました。
メンデルスゾーンは、10代後半に既に彼のキャリアの中でも重要な位置を占める弦楽八重奏曲 (1825年作)とオペラ『真夏の夜の夢』の序曲(1826年作)を作曲しました。彼の家族は個人的なオーケストラを持っており、メンデルスゾーンは、若い頃、そのオーケストラで自分の作品を発表できるという、普通では考えられないような特権を与えられていました。
メンデルスゾーンの一家は、様々な理由でユダヤ教徒からキリスト教徒へと改宗しました。メンデルスゾーンという姓はユダヤ教徒の名前であったので、「バルトルディ(Bartholdy)」を姓に付け加え、名前からもキリスト教徒であることを世間に示しました。一家は改宗することで、社会に完全に同化することができるようになると考えました。
音楽史的には、メンデルスゾーンはロマン派の時代に位置しますが、作曲家としても演奏家としても、J.S.バッハや他の古典主義者を尊敬する新古典主義者でした。彼の作曲スタイルは対位法を重視しており、論理的で形式の美しさと優雅さが際立っています。
メンデルスゾーンの最も有名なヴァイオリンのための作品は『ヴァイオリン協奏曲ホ短調』で、彼の人生の終わりに近い1844年に完成されました。それ以前に、もう一曲『ヴァイオリン協奏曲ニ短調』を13歳のとき(1822年)に作曲し、ソナタも3曲(ヴァイオリン・ソナタ へ短調を1820年に、ヘ長調を1825年と1838年に)作曲しました。1838年に作られたヴァイオリン・ソナタヘ長調は1952年にユーディ・メニューインによって世に出たものです。
この作品は3つの楽章からなり、曲のあちらこちらで、他のメンデルスゾーンの有名なメロディーやフレーズが聞えてきそうです。雰囲気や印象の違うメロディーをちりばめながらも、曲としては一つにまとまっています。
第一楽章は、Allegro vivace(速く)で、冒頭ではピアノによって最初のテーマが奏でられます。喜びに満ちた陽気な旋律で、小規模な弦楽オーケストラを思わせるような音質です。メンデルスゾーンは、付点音符と短い音符の組み合わせを使うことで、特に前進する動きを表現しています(参考1)。重要な音を長くすることで強調し、その音に至るときには速度が増しているように感じます。この曲の冒頭部分(参考2)から2つの例を紹介します。
(参考1)
![]()
![]()
(参考2)ヴァイオリンとピアノ、小節番号1-5

例1: 最初の4つの和音を見てみると、2番目と3番目の和音は合わせて1拍分の長さになります。全ての和音に同じ長さを与えたならば4番目の和音にいくまでにもう1拍必要となりますが、ここでは付点8分音符と16分音符が使われています。この和音の進行は特に驚くべきものではありません。メンデルスゾーンはリズムの配置をうまく操作することで聴衆の関心を引き出しています。
例2: 4小節目にはスフォルツァンドのへ長調の和音があります。この和音はフレーズの中で一番高い音を含んでおり、その高音を目立たせるために8分音符2つではなく、長くして、付点4分音符と8分音符の組み合わせになっています。スフォルツァンドをつけるだけでなく、リズム的にも重要な音を長い音符で表すことによって強調しているのです。
このリズムパターン(参考1)は、楽章全体でたくさん見られます。2番目のテーマでも使われています(参考3)。
(参考3)ヴァイオリンとピアノ、小節番号35-38

この楽章の後半は、ピアノ・パートにもヴァイオリン・パートにも速い16分音符の連続が多く見られ、2つの楽器のためのコンチェルトのようになっていきます。だんだん興奮していきますが、熱狂的になるのではなく、気分がうきうきするような音楽です。この楽章では、ほとんどのところで旋律と伴奏がはっきりと分かれていますが、終わりが近づくにつれ、2つのパートが同じメロディーを奏でることが多くなり、最後はユニゾンで終わります。
第2 楽章はAdagio(遅く)と表記されていますが、この表示は、速度記号というよりも曲想的な意味合いを多く含んでいます。平和で牧歌的な雰囲気が漂い、コローの風景画を完璧に音楽で表現しているようです。こののどかさが楽章の後半で、午後の嵐によってかき消され、即興的で暗くなります。この憂鬱は長くは続かず、楽章冒頭のメロディーが再び奏でられ、嵐は夢だったかのようにこの楽章は終わります。
最終楽章はAssai vivace(非常に速く)で、鳥の羽のように軽く、空中を飛びまわっているような雰囲気です。いったん曲が始まると最後まで止まらず、一気に進みます。旋律がめまぐるしく奏でられますが、決して攻撃的になることはありません。堂々と気品高く、このソナタは、輝かしい響きの中で感動的に終わります。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
モーツァルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ハ長調 KV.296
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756年オーストリア/ザルツブルグ生まれ;1791年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ハ長調 KV.296 (1778年作曲)
第1楽章: Allegro vivace (速く、元気よく)
第2楽章: Andante sostenuto (遅く、なめらかに)
第3楽章: Rondeau: Allegro (ロンド:速く)
モーツァルトは、1778年3月、マンハイム(ドイツ)に滞在中、パリに出発する前の数日間で、この『ソナタ ハ長調』を作曲しました。このとき22歳だったモーツァルトは、将来の伴侶となるコンスタンツェの姉のアロイジア・ウェーバーに片想い中でした。
モーツァルトが父レオポルドに宛てた手紙には、経済状態も良好で、一時逗留を予定しているパリでは演奏依頼が殺到していると書かれており、その内容から、父レオポルドが上手く息子をコントロ-ルしようとしていたことや、彼がいかに強烈なキャリア志向の人物で、息子の成功で経済的にも楽になることを望んでいたかが伺われます。
3楽章で構成されているこのソナタは、全体的に屈託のない、喜びに溢れた雰囲気の曲です。ピアノとヴァイオリンが同じように重要な役割を果たし、2つの楽器の関係は、会話をしているようであり、支え合っているようです。
第1楽章は、攻撃的になることはありませんが、直接的でエネルギッシュです。この楽章は、無邪気な気持ちで天真爛漫に演奏されるべきだと思います。ヘ長調の第2楽章は、デュエットで歌っているようです。メロディーは舞い上がり、ユーモアが時々感じられます。
ロンド形式の最終楽章は、ハ長調に戻り、ソフトに、しかし確信的なエネルギーをもって演奏されます。他の楽章と同様に、2つの楽器のメロディーとリズムが戯れているかのように聞こえます。
2003年6月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
モーツァルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ト長調 KV.301
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756年オーストリア/ザルツブルク生まれ;1791年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ト長調 KV.301 (1778年作曲)
第1楽章: Allegro con spirito
第2楽章: Allegro
モーツァルトは、1777年に、ドイツの作曲家ヨーゼフ・シュスター(1748年-1812年)の『鍵盤楽器とヴァイオリンのための6つのデュエット』と出会い、姉に「僕も同じスタイル(デュエットの両方の楽器が平等に旋律を奏でるスタイル)で、6つの作品を書きたいと思っている」というメモをつけて、スコアを送りました。そして、最初に出来上がったのが『鍵盤楽器(ピアノ)とヴァイオリンのためのソナタ ト長調 KV.301』です。
モーツァルトは、6歳から20代前半まで、人生のほとんどを、生活のため、両親のどちらかと一緒に演奏旅行をし、音楽の見識も広がりました。1777年10月後半に、母親と一緒にマンハイムに到着したモーツァルトは、1778年の3月中旬にパリに向かうまで、そこに滞在し、1778年の初めに、4つのフォルテピアノとヴァイオリンのためのソナタ(KV.301、KV.302、KV.303とKV.305)を作曲しました。KV.304とKV.306は1778年の後半にパリで作曲されました。彼の母親は6月に病気になり、7月には亡くなってしまい、彼の人生に暗い影を落とします。
KV.301からKV.306 の6つのソナタは2つの楽章で構成されており、ヴァイオリンの代わりにフルートでも演奏でき、家庭で演奏されることを意図した典型的な作品です。それらは1778年にパリで出版され、2ヵ月後にその楽譜はプファルツ選帝侯妃マリア・エリーザベトに献呈されたため、『選帝侯ソナタ』とか『プファルツ・ソナタ』と呼ばれています。
それまでに作曲されたモーツァルトの『鍵盤楽器とヴァイオリンのためのソナタ』は、明らかにフォルテピアノかチェンバロ(鍵盤楽器)が重視されていましたが、このKV.301とそれに続く一連のソナタは、ほとんど均等に重きが置かれています。
第1楽章 (Allegro con spirito)は、ヴァイオリンによる繊細で楽しいメロディーで始まります。ピアノとヴァイオリンは、ときどき同じメロディーを奏でるとき以外は、ほとんどの部分で、どちらかがメロディー・ラインを演奏します。
第2楽章(Allegro)は、鍵盤楽器によるテーマで始まります。全体的に舞踏のような優雅な雰囲気があります。中間部は短調で、シシリエンヌの形式でより飾り気のない雰囲気が出ています。憂鬱でノスタルジックであるにもかかわらず、優雅で、この中間部は作品全体の核心であり、私のお気に入りです。
2011年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2011 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
モーツァルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ホ短調 KV.304
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756年オーストリア/ザルツブルグ生まれ;1791年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ホ短調 KV.304 (1778年作曲)
第1楽章:Allegro
第2楽章:Tempo di Menuetto
モーツァルト作曲『ホ短調ソナタ』の冒頭のメロディーは、ヴァイオリンとピアノの二重奏曲の中で最も印象的なテーマの一つで、ピアノの両手とヴァイオリンがオクターブでユニゾンを奏でる大変シンプルなものです。
雄弁で悲哀に満ちた冒頭の雰囲気が、楽章内で対照的な雰囲気へ発展していくことはありません。どちらかと言えば、楽章が進むにつれて、悲しみや切望の念が強くなっていきます。それは、モーツァルトの人生における困難な時期-母親がパリで亡くなるという悲劇-の憂鬱な気分と簡単に結びつけることができるでしょう。しかし、モーツァルトは、こういう時期でも、予想される気分とは完全に対照的な、明るく楽しい音楽を作曲したことで知られています。モーツァルトの真意はわかりませんが、重要なことは、この音楽から伝わる悲しみが純粋で深く心を動かすものであるということです。
第2楽章は、メヌエットのリズムでピアノがソロを奏でて始まります。直後に、ヴァイオリンが同じメロディーを奏でて加わります。第2楽章は3つのセクションに分かれ、最初と最後のセクションは胸を引き裂くような性質を帯びていますが、真ん中のセクションは、聴衆を楽天的な雰囲気が漂う美しい場所へ導いているようです。
全体的に、この作品はユニゾンとオクターブが多用されており、構成的には希薄であると言えます。しかし、結果として、決してシンプルになりすぎてもいないし、気取った感じもありません。実際には、この短いソナタに詰め込まれた複雑さに新たに気づくことになります。
1778年にパリで書かれた『ソナタ ホ短調』は、プファルツ選帝侯夫人エリザベート・アウグステに捧げられた鍵盤楽器とヴァイオリンのために書かれた6曲のソナタの一つです。モーツァルトのピアノとヴァイオリンのソナタの中で2曲だけが短調で書かれていて、この曲はその貴重な2曲の中の一つです。
2006年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2006 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
モーツァルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 KV.305
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756年オーストリア/ザルツブルグ生まれ;1791年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 KV.305 (1778年作曲)
第1楽章: Allegro di molto
第2楽章: Tema con variazioni
モーツァルトは、1777年から1778年にかけての4ヵ月半、母親と共にマンハイムに滞在していました。青年モーツァルトが父親のレオポルドのコントロールから逃れ、新しい世界へと羽ばたこうとしていたことが、ザルツブルクにいた父親に宛てた手紙から、はっきりと読み取れます。演奏家としてよりも作曲家として生きていく決意を固めたのもこの頃で、作曲することが彼の人生の使命だと感じるようになっていました。後に彼の妻となるコンスタンツェの姉で新進のソプラノ歌手であったアロイジア・ウェーバーに夢中になり、彼女とイタリアに旅行してそこで彼女が歌うオペラを作曲するという計画をでっち上げ、父親を失望させました。レオポルドは、すぐに親の権威を行使して、モーツァルトにお金を稼がせるためと、ウェーバー家から遠ざけるために、母親とともにすぐにマンハイムを出発させ、もともと予定していたパリへと向かわせました。パリ滞在中に、母親が病に倒れ、帰らぬ人になってしまいました。
モーツァルトはパリに出発する前に、4曲のピアノとヴァイオリンのための優雅なソナタを作曲しました。同じ頃、モーツァルトはドジャンという名前のオランダ人の委託でフルート奏者のヨハン・バプティスト・ヴェンドリングのためのシンプルで短いフルート協奏曲とフルート四重奏曲を作曲していたので、気分転換のために、これらのピアノとヴァイオリンのためのソナタを作曲したと思われます。モーツァルト自身はこれらの4曲のソナタを『(ヴァイオリンと)ピアノの二重奏曲』と呼んでいました。
マンハイムで作曲された4曲のソナタと、その後パリで作曲された2曲のソナタをあわせて、その頃よく見られた6曲セットのソナタ集KV.(ケッヘル番号)301~306として、プファルツ選帝侯夫人エリザベート・アウグステに献呈されました。これらの6曲のソナタは、すべて1778年の前半に作曲されましたが、KV.304とKV.306がパリで作曲されたもので、作曲された順番は必ずしもケッヘル番号の順と一致していません。
ソナタKV.305は、イ長調で書かれていて、2つの楽章で構成されています。両楽章とも元気よく、軽快に始まり、率直な雰囲気が、ダイレクトで単純なマンハイム滞在中に書かれた他の作品と共通した特徴となっています。(第1楽章は、)交響曲を思わせる響きがあるところもあり、その当時の慣例に従って、若干ピアノに比重が置かれているものの、2つの楽器の関係は対等に書かれています。楽章全体を通して、2つの楽器は補足し合い、まるで対話しているようです。
第2楽章は、優しいメロディーで始まり、その後に6つのヴァリエーションが続きます。この楽章では、第一楽章と比べると、2つの楽器は平等に取り扱われておらず、ピアノがヴァイオリンよりも好まれて使われています。実際に、テーマはピアノが主役でヴァイオリンは伴奏の役割にすぎません。第1ヴァリエーションは最初から最後までピアノのソロです。第2ヴァリエーションになって,初めてヴァイオリンがピアノを押さえてメロディーを奏でます。この楽章のスタイルは同じ頃に作られたピアノ・ソナタの響きによく似ています。第5ヴァリエーションは短調で書かれており、ユーモアを感じさせながらもこの曲にわずかな陰影を与えます。最後の第6ヴァリエーションでは、2つの楽器が追いかけあうようで、この短くて喜びに満ちたソナタは終わります。
2005年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
モーツァルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ソナタ 変ロ長調 KV454
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756年オーストリア/ザルツブルグ生まれ;1791年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 変ロ長調 KV.454 (1784年作曲)
第1楽章: Largo-Allegro
第2楽章: Andante
第3楽章: Allegretto
神童として誉れの高かったモーツァルトは1784年には、ウィーンで一流の大人のピアニストとして活躍していました。演奏依頼が殺到していたにもかかわらず、多額の借財があり、それを返済するために、6曲のピアノ協奏曲(第14番~第19番)を1年で書き上げるようなこともありました。1784年3月と4月の2ヶ月間に、3曲のピアノ協奏曲(変ロ長調 KV.450、ニ長調 KV.451、ト長調 KV.453)、『ピアノと管楽器のための六重奏 変ホ長調 KV.452』、『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 変ロ長調 KV.454』を作曲しました。
モーツァルト自らがピアノを弾き、ヴァイオリニストのレジーナ・ストリナザッキと初演したときには、ピアノ・パートはまだスケッチの段階で、創造力半分、記憶を頼りに演奏したそうです。しかも、それは皇帝ヨーゼフ2世の御前演奏だったのですから、モーツァルトがいかに自分に自信をもっていたかが窺い知れます。
このソナタは3楽章から成り、第1楽章はヴァイオリンとピアノが平等な立場で完璧なハーモニーを奏でるラルゴのイントロダクションで始まり、その美しさは光り輝いています。続くアレグロは、ラルゴとは対照的で、2つの楽器が生き生きとしていて、陽気な音階とアルペジオのような音符が続く元気のよい楽しい雰囲気です。
第2楽章のアンダンテは、モーツァルトの真髄とも言える深い感情の表現が印象的な旋律となって美しく流れます。
アレグレットの最終楽章は、ロンド形式で書かれ、モーツァルトの茶目っ気のある一面がよく表れています。オフビートのスフォルツァンド(sf)や臨時記号(#や♭)のついた半音階が最初のテーマの中に出てきて、ロンドのテーマも挿入部もその流れはとまりません。そして、この作品は高貴にエレガントに終わります。
2004年5月/2016年5月改訂 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
モーツァルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 KV.526
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
(1756年オーストリア/ザルツブルク生まれ;1791年オーストリア/ウィーンにて死去)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 KV.526 (1787年作曲)
第1楽章: Molto allegro
第2楽章: Andante
第3楽章: Presto
モーツァルトの晩年は、彼の人生の中で作曲家として充実していた時期でした。『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 KV.526』、ハイドンに献呈された6曲の『弦楽四重奏曲』、『フィガロの結婚』、『ドン・ジョバンニ』、『コジ・ファン・トゥッテ』や後期に書かれた秀作の『ピアノ協奏曲(KV.466、KV.467、KV.482、KV.488)』などは、まさにこの時期の作品です。この頃には、モーツァルトはもはや雇われ作曲家ではなく、フリーランスで作曲活動を行っていました。
モーツァルトは、雇用主の多くと常に問題を起こし、その度に父親を落胆させていました。彼が天才である証拠とも言えますが、その時代の音楽のトレンドや好みに合わせることを拒否したのか、できなかったのか、主人の趣味や要求を満たすことはありませんでした。
モーツァルトは若い頃から、ヴァイオリンとピアノの作品を多く書いており、最初に出版されたのも『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ集』でした。そのうちの最初の2曲の作品KV.6とKV.7は、ヴァイオリンのパートが目立たないピアノのための作品と言っても過言ではありません。後に書かれた6曲の『プファルツ・ソナタ (KV.301-KV.306)』は、ヴァイオリンとピアノが同等に扱われているものの、ヴァイオリン・パートはフルートでも演奏することが可能です。
1787年に作曲された『KV.526』は、2つの楽器の演奏者の卓越した才能を思う存分発揮できる作品です。モーツァルトが作曲したヴァイオリンとピアノのためのソナタの中で、技術面でも精神面でも演奏者に最も高度な技量が要求される作品です。モーツァルトはアマチュアのためにではなく、自分がピアノを演奏することを想定して作曲したようです。実際、初演はモーツァルトのピアノで行われたのですが、ピアノ・パートが初演時にはまだ書き終えておらず、致し方なくピアノ・パートは、簡単なスケッチから演奏しなければならなかったという事情がありました。
Molto allegroと表記された第1楽章は、ソナタ形式で書かれており、提示部、展開部、再現部で構成されています。オフビートが強調されたアーティキュレーションが、陽気な雰囲気をかもし出しており、リード役とサポート役を2つの楽器が巧みに交互に受け持っています。エレガントでありながら、エネルギーに満ち溢れ、生き生きとした曲調です。著名な音楽学者であるアルフレート・アインシュタインは、この作品を「バッハのようでありながら、完璧にモーツァルト」、「古典と古典以前の対位法形式を見事に調和させた事例」とコメントしています。
Andanteの第2楽章は、ゆったりとしたカンタービレの曲調ですが、歌うような伴奏がメロディーにうまく組み込まれています。第2主題は、大部分がイ短調で書かれていますが、途中でイ長調や嬰へ短調に移調されているところもあり、その当時の習慣として、第2主題はイ長調で書かれることが多かったことを考えると、特徴的と言えます。第2主題が再び現れるときは、ニ短調で書かれており、最後は始まりと同じようにニ長調で終わっています。アルフレート・アインシュタインはこの楽章を「徳ある者が人生のほろ苦い甘さを享受できるように、全能の神がしばしすべての動きを止めてしまったかのような魂と
芸術の絶妙なバランスを表現している」と絶賛しています。
Prestoの最終楽章が始まると同時に、モーツァルトはピアノを“制御”できなくなります。ピアニストの手は文字通り目もくらむようなスピードで鍵盤の上を行き来します。この楽章は、C.P.E.バッハの親しい同僚であったカール・フリードリヒ・アーベル(1723-1787年)作曲の『ヴァイオリンとチェロと鍵盤楽器のためのソナタ』のロンドの楽章を引用したように見受けられます。モーツァルトは若い頃の演奏旅行中にアーベルと親交があり、彼の作品に尊敬の念を抱いていました。アーベルが1787年1月に亡くなったので、モーツァルトは彼への敬意を払ったのでしょう。ロンド・ソナタ形式で書かれており、主題は新しいアイディアが断続的に盛り込まれて表現されています。再現部は、一般的なイ長調ではなく、ニ長調で書かれており、陽気に、スタイリッシュにこのソナタは終わります。
2011年 五嶋みどり
(編・訳:オフィスGOTO)
Notes © 2011 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ヤナーチェク:ヴァイオリン・ソナタ
レオシュ・ヤナーチェク
(1854年モラヴィア(チェコ)/フクヴァルディ生まれ;1928年モラヴィア/オストラヴァにて死去)
ヴァイオリン・ソナタ (1914作曲/1921年改訂)
第1楽章: Con moto
第2楽章: Ballada:Con moto
第3楽章: Allegretto
第4楽章: Adagio
レオシュ・ヤナーチェクは、民族主義と政治的不安が増大してきたモラヴィアで1854年に生まれました。母国への愛着が大変に強く、民族色豊かな独自の音楽を作り上げた作曲家です。合唱の指導者として、教師として、モラヴィアの民族音楽学の権威として活躍し、文節を単位とした話し言葉のパターンや、語りかけの音声の抑揚に強い関心を持ちました。そして、研究を重ね、ついには話し言葉の旋律の理論を確立しました。その結果、単語や文のピッチ(音の高さ)の変動が彼の音楽旋律の一部となっています。
作曲家として、ヤナーチェクが認められたのは、かなり遅くなってからでした。彼が60代になって、そろそろ引退しかかっていた頃、彼のオペラ『イェヌーファ』がついにプラハとウィーンで上演され、漸く国際的に名前が知られるようになりました。彼の作風は、心理学的な本性が極めて生き生きと描写されていると非常に強く感じられるところにあります。感情が剥き出しで、ぞっとするような、耐えがたい、追いつめられたようなところもあれば、弱々しく、失意のどん底にいるような悲劇的なところもあります。彼の音楽を取り乱した狂気の音楽と呼ぶ者もいれば、人生の苦悩や恐怖に真正面から向き合った音楽と評価する者もいます。
ヴァイオリン・ソナタは、彼の器楽曲の中でも演奏される機会の多い作品の一つで、1914年に最初のスケッチができ、いくつかの改訂を経て、1921年についに完成されたものです。4楽章から構成される曲で、第一次世界大戦の暴力や不安定な状況をほのめかしています。
第1楽章は、con moto(動きをつけて・速めに)と表記されており、ヴァイオリンの序奏的な大胆なソロで始まり、すぐに最初のテーマが現れます。この楽章は全体的に、断片的な謎めいた主題が長いフレーズと絡み合って構成されています。楽章が終わりに近づくに連れ、緊張感が増しますが、最後には意外にも心地よい変ニ長調の和音で静かに終わります。
第2楽章のBallada(バラード)は、単純で優しい感じのする楽章です。このソナタの中では最も抒情的な楽章で、音符が次から次へと自然に流れていくようです。楽章の終盤に向かうところで、即興的に不安な要素が現れ、牧歌的で平和な雰囲気を乱しますが、すぐにこの楽章を支配する平穏さが戻ってきます。
第3楽章のAllegretto(やや速く)は、スケルツォ(軽快で諧謔的な3拍子の曲)です。この楽章は3つの部分から成り、最初と最後の部分は、同じ題材を取り扱っており、ざわめくような連続的なトリルをバックに、ピアノが民族音楽の旋律を短く弾むような音で奏でます。これに対し、ヴァイオリンは、断続的に鋭い音で半音階を弾き、妨害します。中間部は、見せかけのロマン主義を思わせる雰囲気が漂います。
最終楽章のAdagio(遅く)は、このソナタの中で最も狂想曲的な楽章です。ピアノの心に迫る旋律を鋭くさえぎるように、ヴァイオリンが、攻撃的に、しばしばミュート(弱音器)をつけて短いフレーズを奏でます。このヴァイオリンによる連続的な妨害が、この楽章の主要なモチーフです。この主要なモチーフに挟まれるようにして、2種類の対照的な雰囲気をもつ旋律が現れます。一つは人生の希望と熱望に満ち溢れた明るい陽気な旋律で、もう一つはロシアの自由軍がモラヴィアに進軍してきたことをヤナーチェクが描いたものです。この作品は、必然的に起こる惨事から逃れられないという緊迫感がどんどん増していく雰囲気の中で、主要なモチーフが音量的に弱まり、消え入るように終わります。
2003年3月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ユン:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
イサン・ユン
(1917年韓国/統営(トンヨン)生まれ;1995年ドイツ/ベルリンにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ(1991年作曲)
(楽章についての記述なし)
イサン・ユンの『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』が始まると、聴衆は即座に緊迫感と何かに対する反発心を感じるでしょう。2つの楽器は持続的に激しさを増しながら、ドラマチックに影響し合います。最初のクライマックスでは、主役のヴァイオリンが高い悲鳴のような音を奏で、敵対者のピアノは権威をかざします。そして、ヴァイオリンは気力を失い、ピアノが暴力的な興奮した雰囲気を押し付けているかのようです。
音楽は音楽家の人生を形作るとか、逆に人生における経験が作曲家の音楽を形作るとも言われていますが、ユンの個人的・政治的バックグラウンドは、その両方が真実で当を得たものであることを確信させます。
ユンは第一次世界大戦(1914-18年)の末期に韓国で生まれ、帝国主義時代の日本による植民地化の全盛期に成人しました。若い頃から政治活動に参加し、生涯政治活動家であり続けました。解放や民主主義、朝鮮半島の統一は、彼にとって緊急の問題でした。彼は生涯で二度、最初は占領中の日本軍によって、二度目は1960年代に朴大統領の軍事独裁政権の秘密警察によって、投獄されました。そのときユンは死刑を求刑されましたが、カラヤンやストラヴィンスキ-を中心とした国際的に活躍する音楽家達の抗議の結果、後に解放されました。
ユンは、40 歳になる頃、初めてヨーロッパに渡り、パリと後にベルリンで学びますが、既にその頃までに、韓国では作曲家としての確固たる地位を築いており、勲章も受け取っていました。ユンは、「私は韓国で生まれ、韓国の文化をはっきりと提示していますが、音楽的にはヨーロッパで培ったものが多いのです。私は、異なる文化の要素を取りまとめたり、分別したりする必要を感じません。私は一人の単純な人間です。それが統合ということです。」と述べています。自分自身の音楽がヨーロッパの聴衆には“外国”の音に聞こえることもあることを踏まえた上で、自身の作品の全てが韓国の伝統に起源を発するとは考えていないし、その中核を担う無調性と修辞的側面を指摘し、韓国の楽器のために書いたのではない、と1986年のインタビューで答えています。そして、様式的な見地に立って、彼の音楽の本質がどこに起源を発するのか、聴衆の皆さんは思いを巡らさざるを得ないでしょう、と言っています。
音楽学者や評論家の中には、ユンの音楽と韓国(または中国/韓国)の伝統的宮廷音楽と楽器とを結びつける意見も多いのは確かです。特にヴァイオリン・ソナタでは、この作品に頻出するトリルの起源と思われる、オーボエのようなピリという韓国の伝統楽器についてや、書道の一筆を思わせるようなヴァイオリンの運弓について言及がなされています。ユンの音楽には、滞るような音符は一つもなく、絶え間なく変化する表現とエネルギーがフルに充満しています。
晩年に書かれたヴァイオリン・ソナタは、1990年に作曲された『弦楽四重奏第5番』の中でも使われた自叙伝的手法とも言える標題音楽の様式を構造的には受け継いでいます。最初のクライマックスの後に、短いながらも鳥の歌のような甘く美しいところが出てきます。どちらかというと叙情的であるこの部分がしばらく続く一方で、音楽の進行上の主役であるヴァイオリンが、お祭り気分の背景の中で、解放を求める気持ちの起伏が、音符のアーティキュレーションの勢いに表され、人生の荒波に身を投げ出しているかのようなところがあります。3つに分かれる部分の最後の部分で、正義をめぐる定義の複雑さと自身の力不足を悟り、静寂の中に内面の平和を徐々に見出していきます。これは決してハッピー・エンディングではありません。むしろ、‘生きてきた’ことを通じて体得した静穏と悲劇と言えます。このソナタは2つの深いため息をつき、消え入るように終わります。
2004年10月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ラヴェル:ツィガーヌ
モーリス・ラヴェル
(1875年フランス/バスーピレネ生まれ;1937年フランス/パリにて死去)
ツィガーヌ(1924年作曲)
モーリス・ラヴェルの『ツィガーヌ』は、サン=サーンスの『序奏とロンド・カプリチオーソ』やサラサーテの『ツィゴイネルワイゼン』と同じようにピアノやオーケストラの伴奏で演奏されます。この曲は、『ツィゴイネルワイゼン』と同様にハンガリーのロマ(いわゆるジプシー)の伝統をたたえる作品です。「ツィガーヌ」という言葉はフランス語で「ジプシー」という意味です。
ラヴェル(1875-1937年)は、指揮者としてもピアニストとしても活躍したフランスの作曲家です。1875年にスペイン国境に近いピレネー山脈の麓の片田舎に生まれました。両親は幼いラヴェルの音楽の才能を理解して支え、文化活動に積極的で、芸術的にも恵まれた家庭環境に育ちました。幼少時代のほとんどを、音楽や芸術の中心地であったパリで過ごしました。その当時(19世紀後半)のパリは知識人の宝庫で、様々な経歴を持った芸術家が多く集まり、それぞれに独自の新しい表現方法を模索していました。
ラヴェルは、ドビュッシー(ラヴェルより13歳年上)と並んで、印象派を代表する作曲家とされています。お互いの作品を賞賛しあいながらも、それぞれはかなりの相違点をもちあわせています。例えば、ラヴェルはリストやサン=サーンスやフォーレの路線に近いのに対し、ドビュッシーはショパンやマスネと関連付けられています。ドビュッシーは、音の色彩や厚み、透明感に魅了されていたのに対し、ラヴェルは主題の展開に強い関心を寄せました。
ラヴェルはリストに傾倒しており、リストへの敬意と憧れの気持ちが『ツィガーヌ』にはよく表れています。リストはハンガリー音楽の旋律を取り入れて『ハンガリー狂詩曲』を作曲しましたが、同じようにラヴェルの『ツィガーヌ』にもハンガリー的な要素が強く感じられます。
ロマと彼らの生活様式を主題に選んだこの曲は、ハンガリーの大ヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムの遠縁にあたる、同じくハンガリーの女性ヴァイオリニスト、イェリー・ダラーニに捧げられました。ラヴェルがこの作品を作曲したのは40代の頃ですが、作曲家が(特に名声を得た後に)作品を誰かに捧げる場合、その人物がパトロンであるとか、友人であるとか、愛する人物であるケースが考えられます。また、偉大な演奏家の演奏技術の高さに刺激され作曲した場合も、その人物に初演してもらいたいという動機から献呈することも考えられます。バルトークの『ヴァイオリン協奏曲第1番』が、成就することのない恋の相手に捧げられたことを考えると、おそらくラヴェルとダラーニの間にも恋愛感情があったのではないかと想像しがちです。残念ながら、この点について確かな証拠はどこにもありません。事実、生前ラヴェルの多数の恋愛関係についての噂はありましたが、どれについても確証を得ることはできませんでした。ユダヤ人であるとか、同性愛者であるとかといった彼にまつわるゴシップも、はっきりした根拠のないものでした。
私は、『ツィガーヌ』はラヴェルの恋愛感情から生まれたものではなく、彼のロマやハンガリー的なものに対する関心から作曲されたものであると思います。この作品は、カデンツァとカデンツァ後の大きく2つの部分に分けられます。冒頭のカデンツァは、ロマが自らの人生を語っている独白と考えられます。この哀歌の中で、困窮、情熱、追慕の情、取り巻く環境、夢などを伝えているようです。カデンツァが終わると、次にロマが住む田舎の世界に誘導されます。そこでは、お祭りや熱狂的な踊りに代表されるようなロマの陽気な生活が語られています。ここでは、カデンツァですでに聴かれた素材と、中間部以降に表れる新しい素材の2つが使われています。
この作品には、ヴァイオリニストが超絶技巧を披露し、名人ぶりを印象付けるいろいろなトリックが含まれています。個人的な意見としては、カデンツァの解釈とその秘密にあるように思います。下手に弾かれてしまうと、このカデンツァは果てしなくダラダラと続くものになってしまいます。自然さ、独自性、技術と音楽性の調和が要求されるこの作品は、思ったよりも難しい曲です。美しい音で弾いただけでは問題の解決になりません。まるでヴァイオリン奏法を根本から見直さなければならないような作品です。一般的にカデンツァは、ヴァイオリン奏法を完全に習得し、自分なりの法則を見つけ出さない限りは意味がありません。「一日がめまぐるしくて落ち着かないときには、ツィガーヌのカデンツァの下手な演奏を聴こう(下手なカデンツァほど、延々と続いて時間が止まるような気がするよ)」。これは我が家でよく言われるジョークです。
2002年 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ラヴェル:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト長調
モーリス・ラヴェル
(1875年フランス/バスーピレネ生まれ;1937年フランス/パリにて死去)
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト長調 (1923-1927年作曲)
第1楽章: Allegretto
第2楽章: Blues: Moderato
第3楽章: Perpetuum mobile: Allegro
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、フランスの作曲家によって数多くの素晴らしいヴァイオリンとピアノのためのソナタが作曲されました。1876年にフォーレが『ソナタ イ長調』を作曲した後、約50年の間に、フランク、サン=サーンス、ドビュッシー、そしてラヴェルへと続き、これらのソナタは現在でもよく演奏されています。
音楽愛好家のフランス人とバスク人の両親にパリで育てられた、モーリス・ラヴェルは、その頃流行していた異国風で神秘的な作風に影響を受け、また印象派のドビュッシーに傾倒していました。彼の作品の多くにも、ジャズやロマ音楽、極東からの音楽といった様々な音楽要素が取り入れられています。
『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』は、晩年に作曲されました。この作品は健康状態の悪化でなかなか進まず、完成されるまでに4年を要しました。その頃には、ラヴェルは印象主義から離れ、もはやその影響が作品に色濃く出ているわけではありませんが、この作品の中にも深く刻み込まれた印象派のスタイルがくっきりと姿を現している部分が少なくありません。2つの楽器の関係について、ラヴェルは「ヴァイオリンとピアノという2つの根本的に相容れない楽器のためのソナタを書く場合、それらの性質の違いに安定をもたらすのではなく、独立性を認め、融和しがたい要素を強調することが大切であると考えている」と述べています。
第1楽章のアレグレットは、典型的な古典形式で書かれており、ロマンティックな色合いのそよ風のような雰囲気を醸し出すピアノのソロで始まります。優雅で、威厳があり、かつ官能的で、とどまることなく音楽は流れていきます。ヴァイオリンとピアノの両者が主要なテーマを交互に奏で、このテーマを構成する対位モティーフは曲全体に何度も登場する印象的なものです。
「ブルース:モデラート」と表記された第2楽章は、複数の調が織り交ぜられ、表記が示すとおり、ブルースの影響を強く感じさせる楽章です。複調性は、楽器ごとに違った調性を与える作曲法の一つで、それぞれの楽器に特徴を持たせるために用いられます。複調性を使うことで、ラヴェルが伝統的な形式の中で何か新しい試みをしようとしているそぶりが窺えます。また、ブルース形式の構成要素は、この楽章に陰鬱な影を与えています。ここでは、彼は1920年代に盛んだったブルースのメロディーを引用しています。テーマはサクソフォーンのような音でスライドするか、物憂げな低い声でささやくように、奏でられます。ヴァイオリンは、鼻にかけたような音を作り出すのに、ゆっくりとした上昇音階を奏で、上りきるとエキゾチックな様相を呈します。
華々しい最終楽章は、「ペルペトゥム・モビーレ」(始めから終わりまで同じ速度で)と表示されており、ヴァイオリニストの技量が限界まで試されるような楽章です。第1楽章の始めに置かれた印象的だったモティーフが、燃え立つように16分音符の中で輝き意気高揚とした終焉に向かっていきます。
ラヴェルはこのソナタをヴァイオリニストのエレーヌ・ホルダン=モランジェに献呈しました。彼女はもともとラヴェルにコンチェルトの作曲を依頼していましたが、彼はその代わりにこのソナタを作曲しました。不幸なことに、この曲が完成した1927年には、彼女はひどい関節炎のため、この曲を弾くことは出来ず、同年5月パリで、ルーマニア人の作曲家兼ヴァイオリニストのジョルジュ・エネスコ(1881-1955年)とラヴェルのピアノで初演されました。
2004年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ラウタヴァーラ:ディテュラムボス Op.55
エイノユハニ・ラウタヴァーラ
(1928年フィンランド/ヘルシンキ生まれ・在住)
ディテュラムボス (Dithyrambos) Op. 55 (1970年作曲)
エイノユハニ・ラウタヴァーラは、今の時代を代表する傑出した作曲家で、おそらくシベリウスに次いで、作品が演奏される機会の多いフィンランド出身の作曲家です。彼は、“いろいろなパーソナリティをもった作曲家”と言われるように、新ロマン主義や新古典主義から、セリエリズム(十二音技法)やロシア正教的要素の強い音楽まで、様々なジャンルで、多様なスタイルを用い、数多くの作品を作曲しています。ラウタヴァーラは、オペラや協奏曲、室内楽、交響曲だけでなく、吹奏楽や合唱の曲も作曲しています。
Dithyramb (ディシラム/ディテュランブ)は、2000年以上昔の古代ギリシャの熱狂的で恍惚の神、Dionysus(ディオニュソス)を讃える歌(賛美歌)でした。ラウタヴァーラの『ディテュラムボス』は、ユーモアとウィットに富んだヴァイオリンとピアノのための作品で、演奏時間は約3分です。1970年に作曲され、同年に行われたシベリウス国際ヴァイオリン・コンクールの準決勝で初演されました。
『ディテュラムボス』は、大部分が7/8拍子で書かれており、その急激に変化する典型的なリズムが、意気高揚とした雰囲気の中で、ディオニュソスの軽快で激しい気質を反映しています。冒頭と終わりのセクションでは、絶え間ない動きが続きますが、冒頭はヴァイオリンで、最後はピアノで演奏されます。中間部に出てくるハーモニックスの一連のスライド(グリッサンド)で作られる特別な音響効果が印象的です。
ラウタヴァーラは、もともとピアニストとしての教育を受けましたが、ヴァイオリンのための作品の作曲にも秀でており、ヴァイオリンを自然な形で慣用的な方法で取り扱っています。『ディテュラムボス』の他に、ヴァイオリンのための作品としては、1975年のシベリウス・コンクールのために書かれた『Variétude』と1977年に作曲された『ヴァイオリン協奏曲』が代表的です。最近書かれた作品としては、オペラの『ラスプーチン(2001- 2003年作曲)』やオーケストラのための『Book of Visions (2003-2005年作曲で、2005年4月に初演予定)』やオーケストラのための『Manhattan Trilogy(2003-2005年作曲で、2005年10月に初演予定)』があります。
2005年2月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2005 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ラウタヴァーラ:ロスト・ランドスケープス
エイノユハニ・ラウタヴァーラ
(1928年フィンランド/ヘルシンキ生まれ・在住)
ロスト・ランドスケープス (Lost Landscapes)(2005年作曲)
第1楽章: Tanglewood
第2楽章: Ascona
第3楽章: Rainergasse 11 Vienna
第4楽章: West 23rd Street NY
「記憶は、我々が持ち歩くことの出来る日記である」オスカー・ワイルド『真面目が肝心』より
ヴァイオリニスト五嶋みどりの委嘱で、エイノユハニ・ラウタヴァーラは『ロスト・ランドスケープス』を2005年に作曲しました。2006年11月に行われたドイツのミュンヘンにあるヘラクレス・ホールでの五嶋みどりのリサイタルで、ロバート・マクドナルドのピアノで初演されました。
ラウタヴァーラは、交響曲から合唱曲、器楽曲にいたるまで、スタイルで言えば、半宗教的なものから神秘主義的なものや新ロマン派のものまで多種多様な作品を生み出しています。多才で多面な様相を持つ作曲家としての名声は確立しており、シベリウス以降、最も成功したフィンランド出身の作曲家と言えます。ラウタヴァーラの最近の作品では、2003年に初演されたオペラ『ラスプーチン』、2005年に初演された2曲のオーケストラ曲『Book of Visions』と『Manhattan Trilogy』があります。
ラウタヴァーラのヴァイオリンのために書かれた曲としては、ソロ・ヴァイオリンのための『Variétude』、ヴァイオリンとチェロのための『Varian Dialogue』、ヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリンとピアノのための『Notturo e Danza』と『Dithyrambos』の5曲があります。『ロスト・ランドスケープス』もヴァイオリンとピアノのための作品ですが、前述の『Notturo e Danza』や『Dithyrambos』のような小品ではない、初めての本格的な作品で、ラウタヴァーラの多くの作品と同様に、音楽言語は極めて個人的なものです。
『ロスト・ランドスケープス』は4つの楽章があり、作曲者自身が“過ぎ去りし想い出の日々”に滞在した場所の名前がつけられています。
ラウタヴァーラは、「この4つのランドスケープは、私が修業中の“さすらいの時代”に過ごした重要な場所です。1955年と1956年の夏は、私の師であるロジャー・セッションズやアーロン・コープランドが滞在していたアメリカのタングルウッド音楽センターで過ごしました。次の年はスイスのアスコナに行き、ウラディミール・フォーゲルに師事し、12音技法を学びました。ライナーガッセ11番地は、ウィーンにある昔の趣が偲ばれるバロック様式のシェーンブルク宮殿の大変ロマンティックな住所です。ウェスト23丁目はニューヨーク市の私の住んでいたところです。これらすべての“ランドスケープ”には、視覚的にも聴覚的にも思い出と特別な雰囲気があり、私にとっては音楽的なテーマなのです」と語っています。
ラウタヴァーラが抱いている4つの場所に対する愛情は、この曲の中に顕著に表れています。作品全体を通して、想い出がセピア色のフラッシュバックのようによみがえり、作品の性質を特徴付けています。途切れなく流れるノスタルジックな想い出の中に、様々な感情や体験、驚きやチャレンジといったものが絡み合っているようです。音楽の勢いが止まることはありませんが、深呼吸して、瞑想にふけることができる余裕が常にこの曲にはあります。一番スピードが速い楽章は、絶え間ない動きがある最終楽章で、おそらく、作曲者は偉大なメルティング・ポットと呼ばれた1950年代半ばのニューヨーク市の喧騒を憶えていたのでしょう。ラウタヴァーラは、“全ての想い出は記憶の中で甘いものへと変わる”というコンセプトを貫いています。
このように、『ロスト・ランドスケープス』は、ひたむきに苦節の時を過ごした日々を慈しむ気持ちが表現されています。独自の構造を呈しながら大胆に、全ての聴衆の心の琴線を打つ作品です。
2006年9月五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2006 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
リスト:ヴァルス・カプリース第6番
フランツ・リスト
(1811年ハンガリー/ライディング生まれ;1886年ドイツ/バイロイトにて死去)
『ウィーンの夜会』S.427より
『ヴァルス・カプリース』第6番 <シューベルト原曲> (1846-1852年作曲)
リストは幼い頃よりピアノの才能を認められ、ウィーンやパリ、イタリア、ウクライナ、イギリスなどに旅をしながら育ちました。ピアノの巨匠としてヨーロッパ中で名を馳せ、当時のピアノの芸術的・技術的水準を飛躍的に高めただけでなく、指揮者でもあり、作曲家、既成の作品の編曲者でもありました。音楽や宗教についても著書を残す一方で、教育者としてもジュネーブ音楽院や個人的に後進の指導を行い、ハンガリーのブダペストとドイツのワイマールで音楽院の創立に関与しました。ワーグナー(1813-1883年、ドイツの作曲家・指揮者)やスメタナ(1824-1884年、チェコの作曲家・指揮者・ピアニスト)など他の音楽家を援助したことでも知られ、慈善家でもありました。
その人物像は悪魔のようだとも、エレガントでロマンティックだとも言われ、またロマ的 な面があるかと思えば、時に修道士のような一面もあったなど、一見矛盾しているようですが、神秘的で他人に対して寛容な性格は、人々を魅了し続け、恋愛や子供達を通じての人間関係は、ハンス・フォン・ビューロー(1830-1894年、ドイツの指揮者・ピアニスト、次女コジマの初婚相手)、前述のリヒャルト・ワーグナー(次女コジマの再婚相手)、ジョルジュ・サンド(1804-1876年、フランスの女流作家、リストの恋愛相手)、そしてエミール・オリヴィエ(1825-1913年、フランス首相、長女の結婚相手)にまで及びます。リストはあらゆる形容詞を駆使しても語り尽くせないような人物なのです。作曲家 としてのリストは、サリエリ(1750-1825年、リストの師の一人)やベートーヴェン(1770-1827年)、シューベルト(1797-1828年)らが活躍した古典の時代とワーグナーのドイツロマン派、宗教音楽とハンガリーの作曲家をつなぐ掛け橋とも考えられています。リストの作品の中心はピアノ曲で、主として3つのカテゴリーに分類することができます。オリジナル曲、トランスクリプション(管弦楽曲のピアノへの編曲)、そして他の作曲家のテーマに基づいた幻想曲があり、『ヴァルス・カプリース』はこのカテゴリーに属します。
ピアニストとしては1847年に活発なコンサート活動から引退し、指揮者の職を得たワイマールで、シューベルトのピアノ・ワルツ集をもとに9曲セットの『ウィーンの夜会』を書き上げました。この第6番はシューベルトの『高雅なワルツ』第9番と第10番、『感傷的なワルツ』第13番の3曲から題材を取り入れており、リストは亡くなる前の1885年に、ピアニストとして最後の公の舞台(チャリティー・コンサート)でこの曲を演奏しました。今回は、ヴァイオリンとピアノのために自由にアレンジして演奏します。とても 贅沢な貴族の舞踏会の様子が伝わってきます。
2002年/2016年5月改訂 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2002 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ルトスワフスキ:スビト
ヴィトルト・ルトスワフスキ
(1913年ポーランド/ワルシャワ生まれ;1994年同地にて死去)
スビト(1992年作曲)
ヴィトルト・ルトスワフスキは、ショパンやシマノフスキと並ぶ偉大なポーランドの作曲家の一人で、彼の作風は他に類を見ず、反ロマン主義の語法で独特の音楽を作り上げています。
ルトスワフスキは激動の時代を生き抜き、二つの世界大戦、スターリンの共産主義による支配、冷戦の終結と共産主義の崩壊を経験しました。政治運動をしていた家庭に生まれ、常に政治的混乱や悲劇的事件と直面しているような緊張状態の中で育ちました。ルトスワフスキ自身は第2次世界大戦の捕虜収容所から脱走した経験を持ち、父も兄弟も戦死しました。
ルトスワフスキは、幼い頃にピアノの勉強を始め、後に作曲とヴァイオリンを学びました。ドイツ人ヴァイオリニストのアンネ・ゾフィー・ムターの芸術的才能に触発され、1984年に71歳で初めてヴァイオリンのための曲を手がけ、生涯で3曲のヴァイオリン曲を完成させました。そのうち2曲がムターによって初演され、彼女によって世界に広められ、現代ヴァイオリニストに知れ渡るようになりました。3曲目の『スビト』は、ルトスワフスキが第4交響曲を作曲した1992年に作曲されました。この作品はインディアナポリス国際ヴァイオリン・コンクールから委託されたもので、彼の最後の完成された作品となりました。ルトスワフスキは、ムターに献呈するはずだったヴァイオリン・コンチェルトを作曲中に亡くなりました。
政治的抑圧が続いていたポーランドで、ルトスワフスキは密かに新しい半音階主義に基づく作曲技巧を探求し、作り上げていきました。新しいものをおおっぴらに追求し、紹介することは政治的・文化的抑圧の時代にあって不可能なことでしたが、彼は独自の作曲技巧に磨きをかけ、その成果の一部は『スビト』の中で顕著に表れています。この作品はリフレイン-エピソードのパターンが繰り返される形式をとっています。
『スビト』は、5つのリフレイン(主題の部分)と、その間に挟まっている4つのエピソード(2つの主題の間に挿入された自由な内容をもった部分)で構成されています。全てのリフレインは、ヴァイオリン・パートがffで始まり、最初の1小節は36分音符の連続で、大胆に力強く、D(レ)から1オクターブ下のD♭(レ♭)への半音階的な下行(例1)で始まるという共通点があります。それに対してエピソードは毎回様子が異なりますが、リフレインとは、はっきりと区別できます。
ルトスワフスキはヴァイオリン・パートに半音階主義を取り入れることで、リフレインの部分を特徴付けましたが、ピアノは2小節目で両手とも和音を奏でます(例1)。この和音は、それぞれ3つの音から構成されており、右手で弾く和音は、下からD♭(レ♭)-B♭(シ♭)-D♭(レ♭)で、それぞれの音程差を数値で表した場合、6度と3度になります。これに対して、左手で弾く和音は、下からB♭(シ♭)-D♭(レ♭)‐B♭(シ♭)で、それぞれの音程は3度と6度になり、この点で、右手と左手が対称的になっているのが特徴です。
(例1) 小節番号1-4

エピソードの中では展開や転調が全体的に見られます。リフレインがその部分だけで完結しており自己充足しているのに比べて、エピソードはその中で展開されていくので、転調などがより多くなり、したがっていろいろなことがエピソードの中で起こります。エピソードはリフレインよりも長く変化に富んでいます。
しかしながら、オープニングのリフレインで導入される主要なアイディアが後にエピソードの中で展開させられるものであるということは、興味深い事実で、モチーフの半音階主義などが様々な形で演奏されます。
この曲は論理的にも形式的にも複雑な曲なので、これまでの説明では、この曲を解釈する上でヒントを与えただけに過ぎません。調和のよくとれた職人技のような作曲技巧で書かれた名作中の名作と言えるでしょう。技術面を入念に研究していけばいくほど、畏敬の念が募ります。しかしながら、作品の構造についての完璧な知識がなくても、『スビト』には、ずば抜けた新鮮さがあり、この曲から受ける衝撃の大きさからも、人を引きつける力を十分にもった作品だと思います。
2003年5月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2003 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.
ルトスワフスキ:パルティータ
ヴィトルト・ルトスワフスキ
(1913年ポーランド/ワルシャワ生まれ;1994年同地にて死去)
パルティータ(1984年作曲)
第1楽章: Allegro giusto アドリブ・セクション
第2楽章: Largo アドリブ・セクション
第3楽章: Presto (コーダの前のアドリブ・セクションを含む)
ルトスワフスキ作曲のパルティータは、ヴァイオリンとピアノのために書かれた傑作で、深い感動を与えるこの作品には、大曲にふさわしく、想像できる限りの全てが含まれています。この作品は生気にあふれ、非常に力強く、演奏者も聴衆もそのパワーに圧倒されます。
この作品は、ミネソタ州のセント・ポール室内楽オーケストラが当時音楽監督であったヴァイオリニストのピンカス・ズッカーマンとピアニストのマーク・ナイクルグのためにルトスワフスキに委嘱し、1984年に作曲され、作曲家自身が「代表作の一つである」とコメントしています。1985年1月セント・ポールでズッカーマンとナイクルグのデュオによって初演され、この作品は、現代曲のジャンルでは、頻繁に演奏される作品となりました。1988年にアンネ・ゾフィー・ムターのリクエストでオーケストラ版が作られてからは、急速に人の知るところとなりました。
ルトスワフスキはピアノとヴァイオリンの両方を学びましたが、ポーランドの旧国家体制による政情不安や抑圧のため、音楽教育の環境としては恵まれたものではありませんでした。また、ルトスワフスキは、長い間、新しい試みによる作品を公表することすらできませんでした。彼の倍音の多用も含めた非伝統的な技巧や偶然性の手法は、晩年の作品にのみ顕著に現れていますが、検閲が厳しかった時期にも自分自身でそれらの手法に磨きをかけていたことは明らかです。
1980 年代に入り、ポーランド政府が検閲政策を緩和してから、ルトスワフスキは、それまで30年余り手がけていなかったヴァイオリンの作品を発表し、パルティータの他にも2曲のヴァイオリンのための作品を残しました。1994年に亡くなったときは、ヴァイオリン・コンチェルトを作曲中でした。
パルティータは、3つの主要な部分が、偶然性の手法で書かれた半即興的な2つのアドリブ・セクションによって結合されています。それぞれの楽章とアドリブ・セクションは休みなく演奏されます。作品全体を通して、情熱がみなぎり、ドラマが感じられ、調性とは関係のない半音の動きや、音符の繰り返し、クロス・リズムといった要素が多く見られます。しかしながら、その結果、重い響きになったり、無調のコードやリズムの混乱に陥ったりするわけではなく、確信と感性に満ちた出会いと別れが、驚くほど独立したピアノとヴァイオリンの2つのラインに存在しています。
第1 楽章のアレグロ・ジュストは、抑えがたい勢いをもって始まり、ピアノとヴァイオリンは主として緊迫した音を奏でます。印象的な歌のように感じられる瞬間や強く好奇心をかきたてられる神秘的な瞬間が点在するのは、ヴィブラートなしの奏法やグリッサンド、四分音(半音のさらに半分の音程にある音)が、この楽章では考慮の末に使われていることの成果でしょう。
アレグロ・ジュストとラルゴをつなぐアドリブ・セクションは、この作品の後半に回想される他の2つのアドリブ・セクションと同様に、偶然性によるパッセージの典型的なもので、ルトスワフスキ自身が演奏者に対して、「ヴァイオリンもピアノもいかなる方法でもコーディネートされるべきではない」と明確に指示しています。ですから、演奏者はそれぞれのパートを即興のカデンツァを弾くかのように演奏します。曲想は徐々に高揚して、ラルゴを迎えます。
この作品の感情的な中核を担うのは、このラルゴのセクションです。力強い生命力を感じさせながら、音楽の内に秘めたエネルギーは増していきます。ラルゴの後には別のアドリブ・セクションが続き、不規則なリズムが陽気でエネルギッシュな最終楽章への道筋を整えます。短い中間部分は、シマノフスキのヴァイオリン音楽を思い出させ、演奏可能な一番高い音域で弾かれる、限界に近いカンタービレとヴァイオリンのハーモニックスが印象的です。最後のアドリブ・セクションの直後にこの楽章のコーダが続き、壮観なエンディングへと進んでいきます。
2004年8月 五嶋みどり
(編・訳:花田由美子)
Notes © 2004 by Midori, OFFICE GOTO Co. Ltd.
Referential sources available on request.